工場や事業所で使用したペンキ・塗料・ニス(いずれも塗膜形成材)は、成分や性状によって処理方法が変わります。まず 水性塗料 は水で希釈するため揮発性物質は少ない一方、廃棄時に残った水分・顔料を分離する必要があります。一方 油性塗料・溶剤系塗料(油性ペンキ、ニスなど)は揮発性・引火性が高く、廃棄物処理時に厳重な管理が必要です。これらを適正に分類・処理するために、以下のような手順が一般的です。
- 少量のペンキ:新聞紙やキッチンペーパーに塗り広げて自然乾燥させ、乾燥した塗料片を可燃ごみ(一般廃棄物)として処分できます。引火性の高い油性ペンキやニスの場合は、屋外の風通しの良い場所で十分乾燥させます。
- 大量のペンキ:廃液が多い場合は、塗料固化剤(高吸水性ポリマー)を利用します。廃ペンキをバケツに集め、少しずつ固化剤を混ぜてしっかり攪拌すると、数分で液状が固形化します。固まった後はゴミ袋に入れ、乾燥してから一般ごみとして出せます。この手法は専門業者でも推奨されており、処分前に塗料を固化することで廃棄しやすくなります。
- ニス:木工用ニスなども基本的に油性・溶剤系なので、油性ペンキと同様の扱いになります。少量なら新聞紙で乾燥固化し可燃ごみへ、大量の場合は塗料固化剤で固めてから廃プラスチック類として処理します。
- 下水への流出禁止:いずれも「下水道に流してはいけません」。塗料は水道管で固まりトラブルの原因になるほか、有害成分が含まれている場合は水質汚染・環境汚染につながるため、絶対に下水放流しないでください。
以上のように、適切に乾燥・固化させることでペンキの捨て方は自治体の指定方法に従って一般廃棄物扱いが可能ですが、工場・事業所から出る廃塗料は産業廃棄物として処理する必要があります。
塗料関連排水の処理技術
塗装工場では、塗装ブースや器具洗浄で大量の排水(汚水)が発生します。これらは有機成分や顔料を多く含み、通常の生物処理だけでは汚濁負荷が大きいため、物理化学処理が一般的です。代表的な技術には次のものがあります:
- 凝集沈殿法:凝集剤(フロック剤)を投入して微粒子や顔料をフロック化(凝集)させ、沈殿分離させる方法です。たとえばアクトの無機系凝集剤「水夢」は、含まれる有機・無機物質を同時に沈殿・分解してBOD/CODを低減し、生成するフロックも安定で崩壊しにくい特長があります。
- 活性炭吸着:溶解した有機成分(溶剤や染料成分など)を高比表面積の活性炭で吸着除去します。凝集処理だけでは除去しきれない溶解性有機物をターゲットにします。
- 膜分離(膜ろ過・逆浸透):微細な固形物や溶質を分離するため、膜フィルターを通して透過水と濃縮液に分離します。膜処理により排水中の全懸濁物質や重金属を除去し、水を再利用・放流しやすくします。
これらの方法を組み合わせることで、塗料廃水中の汚濁物質を効果的に除去できます。アクトでは「水夢」等を用いた凝集法の実績が豊富で、処理後の排水は下水に流せるほどまで浄化できます。たとえば、水夢処理を施すと固まったフロックの含水率は約60~70%程度にまで抑えられ、処理水は基準をクリアできるレベルになります。
産業廃棄物としての塗料処理
工場・事業所から出る廃塗料は産業廃棄物(法定20種類)に分類されるため、適切な業者での委託・処理が必要です。ただし廃棄物処理法には「廃塗料」という区分はなく、その性状に応じて既存の種別で扱います。主な分類例は次の通りです:
- 固形状の廃塗料・廃インキ:乾燥固化した塗料カスはプラスチックと同様の性状のため、「廃プラスチック類」に区分されます。
- 泥状の廃塗料:粘度のある泥状の場合は「汚泥」に分類されます。ただし油分が概ね5%以上含まれる場合は、「汚泥と廃油の混合物」として扱われます。
- 液状の廃塗料:
- 水性エマルション塗料(成分が水溶性)…「廃プラスチック類+廃酸または廃アルカリ」の混合物になります。
- 有機溶剤系塗料…「廃プラスチック類+廃油」の混合物となります。
- 溶剤の引火点が70℃未満の塗料(高揮発・高引火性)は「廃プラスチック類(産業廃棄物)+引火性廃油(特別管理産業廃棄物)」とされ、特別管理産廃として厳しい基準で処理します。
- 水性エマルション塗料(成分が水溶性)…「廃プラスチック類+廃酸または廃アルカリ」の混合物になります。
- 空缶・ドラム缶:一斗缶やドラム缶に塗料が残ったまま廃棄すると、廃塗料に加えて「金属くず」として混合物扱いになります。廃棄時には内容液を取り除き、容器は空にして処分することが求められます。
廃塗料の最終処理方法としては、セメント固化埋立や焼却処理後の埋立処分が一般的です。多くは最終処分場への埋立に回され、再資源化は難しいとされています。そのため、廃棄前に塗料を分離・固化処理することで埋立量を削減する工夫が重要です。また、塗料には有害物質や揮発性溶剤が含まれる場合が多く、特別管理産廃に該当しないか事前に成分を確認する必要があります。塗料や溶剤によってはハロゲン系物質も含まれるため、セメント固化での処理可否にも注意が必要です。
塗装工場の排水処理システム
塗装工場では、湿式塗装ブースや洗浄槽などから大量の排水が発生します。湿式ブースでは塗料ミストを水膜で捕集し、ブース下の循環槽に戻ります。循環システムではポンプで水をくみ上げ、凝集槽や沈殿槽で塗料成分を除去して再利用します。刷毛・エアガン洗浄槽の排水は粘性が高いため、専用の洗浄槽を設けて予め凝集剤で固液分離を行い、清水部分だけを下水へ放流する事例もあります。システム全体では、汚泥やスラッジを取り出して脱水・乾燥し、固形化して産廃処理します。可能であれば微細ろ過膜や遠心分離機を用いてさらに水分と塗料成分を分離し、効率的な循環・再利用を図ります。このような設備設計により、塗装工場の洗浄排水・循環システムは省エネ・低コストで運用されます。
塗料処理の法規制対応
塗料・ペンキの廃棄・排水には各種法令が適用されます。廃棄物処理法では、塗料廃棄物は事業系廃棄物としてマニフェスト管理下で処理が義務付けられます(特に油性溶剤系は特別管理産廃の可能性あり)。水質汚濁防止法では、排水時にBOD、COD、pH、ばっ気禁止物質などの排出基準を満たす必要があります。塗料廃水は濃度が高いため、浄化槽や処理施設で基準以下まで処理してから下水に排出します。また、大気汚染防止法や有機則(揮発性有機化合物規制)では、揮発性溶剤の使用量制限や排出量把握が定められています。これに対し水性塗料の導入はVOC排出量を大幅に低減でき、環境負荷を削減します。さらに、石綿法や建築物のシックハウス対策(F☆☆☆☆表示制度)などでも塗料に含まれる成分が規制対象となるため、成分表示を確認して法令遵守に努める必要があります。
アクトの塗料処理支援実績
アクトでは長年にわたり塗料廃液処理技術を研究・提供してきました。特に水性塗料廃液の処理を目標に開発した無機系凝集剤「水夢(SUIMU)」は、ゼオライトを主成分とした中性凝集剤で、ペンキ・塗料廃水中の有機・無機汚濁物質を同時に沈殿・分解し、BOD/CODを大幅に低減します。水夢は用途別に多数の品番が用意されており、例えば工事現場の濁水用(ST-2502P)や左官道具洗浄水用(ST-4002H)など、具体用途向けの製品が積算資料にも掲載されています。アクトはこれら凝集剤の実績が豊富で、他社と比べて水性塗料廃液処理に強みがあります。お客様ごとに実際の排水を使った無償テストサービスを行い、最適な処理条件・薬剤品番を提案して適正処理とコスト削減を実現する成功事例が多数あります。さらに現在は塗料固化剤の開発にも着手しており、今後は廃塗料の現場固化処理技術にも対応していきます。
これらの技術力・実績を生かし、アクトではお客様の塗料・廃液処理課題に対して最適なソリューションを提供しています。法規制を遵守しつつコスト最適化するためのご相談も承りますので、塗料処理でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

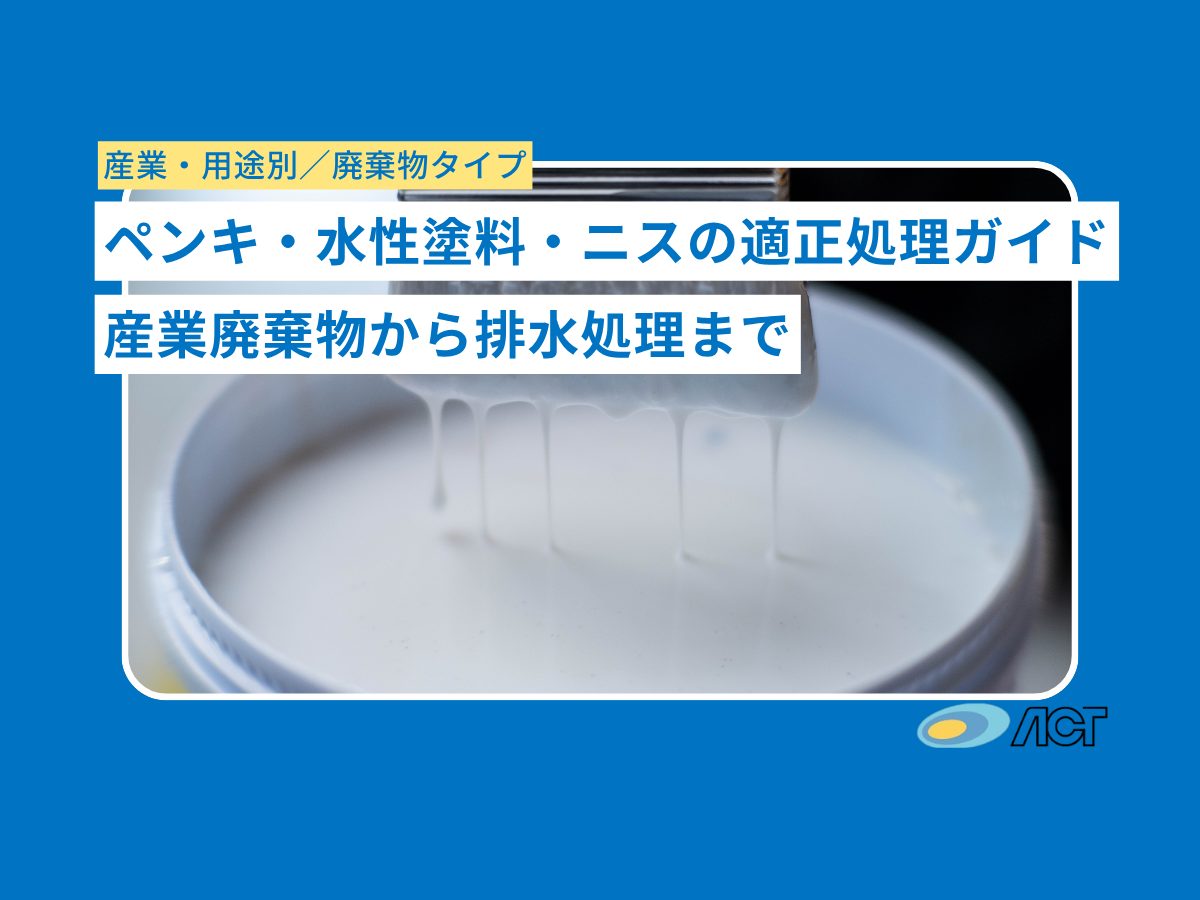
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)