建設工事では地盤掘削や水中作業に伴い、大量の泥水(どろみず)や浚渫土(しゅんせつど)、さらには処理過程で発生するし渣(しさ)が生じます。これらはそのままでは環境汚染や処理コスト増大の原因となるため、効率的な脱水・減容化や適切な分類・処理が不可欠です。本ガイドでは、建設現場の泥水の特徴と課題、浚渫土の処理技術、し渣(スクリーンかす・沈砂・汚泥)の適正処理方法、泥水の脱水技術比較、関連する法規制への対応、そして株式会社アクトが手掛けた効率処理と環境負荷削減の実績について、初心者にもわかりやすく解説します。工場・事業所の排水管理担当者の方はぜひ参考にしてください。
建設現場泥水の特徴と処理課題|高SS・粘土分・重金属含有への対応
建設工事の掘削現場や山留め工事、トンネル工事などでは、土砂や粘土が混じった濁った排水、いわゆる建設泥水が大量に発生します。この泥水の特徴として、以下の点が処理上の課題となります。
- 高濃度の懸濁物質(SS)の存在: 建設泥水には微細な土粒子や粘土分が大量に含まれ、濁度が非常に高くなります。自然沈降だけでは微細粒子がなかなか沈まず、透明な水に浄化するには時間がかかります。そのため、凝集剤を用いた凝集沈殿処理が有効です。例えば、地下工事で発生する泥水に無機系凝集剤を投入すると、微細な粘土粒子が瞬時にフロック(粒子の塊)化し、沈殿槽で澄んだ水とスラッジに分離できます。凝集沈殿法を用いることで、濁度が数百~数万NTUにも及ぶ泥水でも短時間で環境基準レベルまで浄化することが可能です。
- 粘土分による処理の難しさ: 泥水中の粘土成分は粒径が極めて小さく、比重も水とあまり変わらないため、放置しても沈降しきらないことがあります。このため、前処理段階で凝集剤の併用や、十分な滞留時間の確保が重要です。沈殿槽を大きくとり、ゆっくり水を流すことで粒子の沈降を促し、必要に応じて凝集剤で粒子同士をまとめて沈みやすくします。粘土質の泥水処理では、このような物理化学的処理の工夫が不可欠です。
- 重金属等の有害物質含有: 掘削場所の地質によっては、泥水中にヒ素・鉛・六価クロムなどの重金属や有害物質が自然由来で含まれる場合があります。これらは処理水の放流基準だけでなく、分離後の汚泥(建設汚泥)の処分においても問題となります。重金属を含む汚泥を再生利用(土質改良材など)する場合、環境基準を満たすことが必須です。実際、国のガイドラインでも改良汚泥を土質材料として利用する際は「有害物質が含まれていてはならない」とされており、利用前に金属等の基準値を満足しているか確認する必要があります。重金属濃度が高い汚泥は安易に埋立てず、薬剤沈殿等で無害化処理を施すか、特別管理産業廃棄物として適正に処理することが重要です。
- pHや油分など他の汚染要素: 建設泥水には、場合によってはセメント系のアルカリ成分(高pH)や地下水由来の有機物・油分が混入することもあります。特にコンクリート工事の泥水は強アルカリ性になりやすいため、中和剤でpHを調整してから沈殿処理を行います。油分については浮上分離槽での油回収や吸着剤の使用など、泥水中の成分に応じた対策が求められます。
以上のように、建設現場の泥水処理では高濃度SSへの対策(凝集沈殿等)や粘土・重金属対策(長時間沈降・薬剤処理)、さらにはpH調整など多面的な処理が課題となります。適切な処理を行わず未処理の泥水をそのまま河川等に放流すれば、生態系への被害や環境汚染を招くおそれがあるため、水質汚濁防止法の基準を満たすまで浄化してから排水する必要があります。このような泥水処理の課題に対し、株式会社アクトでは無機凝集剤「水夢(すいむ)」などを用いた効率的な処理ソリューションを提供しており、たとえば高濃度の建設泥水でも短時間でクリアな水に浄化し、汚泥量を削減するといった成果を上げています。
浚渫土の処理技術|脱水・固化・改良・リサイクルの最適選択
河川や港湾などの底に堆積した土砂やヘドロを掘り取る浚渫(しゅんせつ)作業では、浚渫土と呼ばれる大量の軟弱土が発生します。浚渫土は水分を多く含み軟らかいため、そのままでは運搬・処分が困難ですが、適切な処理を施すことで資源として再生利用できる可能性もあります。浚渫土の代表的な処理技術と最適な選択肢について解説します。
- 脱水による減容化: 浚渫土は含水比が非常に高く(泥状~ヘドロ状)、まず脱水処理によって水分を絞り出し、体積と重量を減らすことが重要です。脱水方法としては、泥水処理と同様に遠心分離脱水機やフィルタープレス、ベルトプレス、大型の脱水槽の利用、さらにはジオテキスタイル脱水袋(Geotube)に浚渫土を充填して自然排水させる方法などがあります。脱水により含水率を下げて泥土を土塊状にすれば、ダンプでの運搬や重機による扱いが容易になり、後工程の処理や処分場での埋立ても行いやすくなります。特に遠心脱水機は処理スピードが速く、1時間に数トン規模の泥土を処理でき、大規模浚渫現場で有効です。
- 固化処理(安定化処理): 脱水後の浚渫土や、脱水せず泥状のままの浚渫土に固化材(セメント系粉体など)を混ぜ込み、土質を改良する方法です。固化材を添加・混練することで、泥土中の水分が結合・硬化して強度が増し、流動性のない固形の土塊(改良土)に変化します。固化処理した浚渫土は安定処理土とも呼ばれ、盛土材や埋め戻し材、路盤材など土木資材として再利用することも可能です。粒状固化処理工法などにより、高含水比の泥土を扱いやすい粒状の材料へと再生する技術も開発されています。最適な固化材の選定(例: セメント、石灰、石膏系副産物の利用など)や添加量の設計がポイントで、対象土の性状に応じて固化材を調整します。
- 土質改良・改質(泥土改良)による再利用: 浚渫土を土質改良して有効利用する取り組みも進んでいます。固化処理と似ていますが、より用途に応じた改質を行う点で特徴があります。たとえば、有機質を含む軟弱な浚渫泥土に繊維質系の改良材(紙くず由来の繊維など)とセメントを添加し混合することで、扱いやすく強度のある改良土に変える技術があります。このように改良した泥土は、建設現場の埋め戻しや地盤改良材として再利用が図られています。実際、国土交通省のガイドラインでも建設汚泥や浚渫土の再生利用が推奨されており、多くの現場で改良処理を施して再利用する取り組みがなされています。ただし、都市部など大量の浚渫土が出る場合は改良にかかる手間・コストも大きいため、効率的な改良方法の模索が課題です。
- リサイクルと資源化: 脱水・固化・改良した浚渫土を、さらにリサイクル資源として有効活用する最適策も検討されます。例えば、海底から浚渫した砂質土であれば洗浄・脱水後に建設用の砂や造成用土として利用するケースがあります。また、有機質ヘドロの場合は堆肥化して緑化土壌にする試みや、焼成して軽量人工骨材にする研究もあります。近年では、災害廃棄物処理の一環で浚渫土等の泥土を資源として再利用する取り組みも報告されています。リサイクルの可否は浚渫土の性質や含有物によりますが、適切に処理すれば「捨てずに使う」ことも可能であり、持続可能な資源循環の観点からも最適な処理法を選択することが重要です。
以上のように、浚渫土の処理技術は脱水→固化・改良→再利用という段階的なプロセスで検討されます。現場の条件や泥土の汚染状況によって最適解は異なり、例えば汚染物質を含む港湾ヘドロであればセメント固化等で有害物の溶出を抑え管理型処分場に埋立て、きれいな砂質浚渫土であれば脱水して建設材料として再利用、といった選択がなされます。浚渫土の処理は一つの技術で完結せず、「脱水で量を減らす」「固化や改良で性状を変える」「可能ならリサイクルする」という複数の手段を組み合わせて最適解を見出すことが求められます。
し渣の分類と処理方法|スクリーンかす・沈砂・汚泥の適正処理
「し渣(しさ)」とは、一般に泥水や排水の処理過程で生じる残渣(ざんさ)を指す用語で、建設現場の泥水処理においても以下のような副産物が発生します。
- スクリーンかす: 泥水中に混入している木片・プラスチック片・紙くず・石ころなどの大型ごみは、最初にスクリーン(格子)やフィルタでこし取られます。これがスクリーンかすで、泥水処理の前処理段階で生じる粗大残渣です。スクリーンかすには可燃性のごみ(木片や紙)と不燃物(石や金属片)が混在することが多いため、適宜分別して処理します。可燃物は焼却処理、不燃物は埋立処分されるのが一般的です。建設現場から出るスクリーン残渣は産業廃棄物(廃プラスチック類や木くず等)として扱われるため、許可業者に委託し適正処理する必要があります。
- 沈砂(ちんさ): 泥水中の砂や比重の大きい土砂は、沈砂池や沈殿槽で沈降させて除去されます。こうして回収された砂分が沈砂です。沈砂は比較的粒径が大きく水分を含んだ砂利状の物質で、性状としては元の土砂に近いため、汚染がなければ再利用も検討できます。例えば、沈砂を脱水・乾燥させれば埋め戻し材や路盤材に転用可能なケースもあります。ただし、下水処理場由来の沈砂など有機物を含む場合や悪臭を伴う場合は、石灰で安定化処理したうえで埋立処分することもあります。建設現場の泥水処理で出る沈砂は「がれき類」に該当することもありますが、含まれる泥分によっては汚泥に分類されることもあります。いずれにせよ、回収した沈砂は場内で乾燥させてできるだけ水分を切り、飛散や流出を防ぎつつ、産業廃棄物として適切に処理します。
- 汚泥(凝集沈殿 sludge): 泥水処理の最終段階で沈殿槽等から排出される沈殿汚泥がこれに当たります。凝集剤を使った場合はフロック化した微細粒子や凝集剤の反応生成物がこの汚泥中に含まれ、泥状~ケーキ状の脱水汚泥として回収されます。建設現場由来のこの汚泥は法令上「無機性汚泥(建設汚泥)」として扱われ、建設廃棄物の一種です。処理方法としては、前述のように脱水処理をして含水率を下げ、体積を減らした上で、セメント固化等による安定化処理を経て埋立処分するか、改良材として他現場で再利用するかの選択になります。再利用する場合は重金属等の含有に注意が必要で、適宜、分析を行って安全性を確認します。処分する場合でも、運搬時には密閉式の泥土専用ダンプ車を使い、マニフェストを発行して許可業者に委託するなど、廃棄物処理法に則った適正処理が求められます。
以上のスクリーンかす・沈砂・汚泥(建設汚泥)が、建設泥水処理における主な「し渣」です。これらは種類ごとに性質も処理方法も異なりますが、共通して重要なのは適正に分類・処理することです。具体的には、スクリーンかす等の固形残渣は産業廃棄物(がれき類や廃プラ類等)として焼却・埋立て処分し、沈砂・汚泥など泥状のものは汚泥処理のフローに則って脱水・安定化しつつ処分または有効利用する、という形になります。特に汚泥については不適切に野積みすると周囲の土壌・地下水を汚染するリスクがあるため、仮置きする場合も防水シートを敷く、雨水流入を防ぐなどの管理が必要です。また最終処分においても、含有する有機物・有害物質に応じて安定型・管理型埋立地を使い分け、安全に処理しなければなりません。し渣を適正に処理することは、法令遵守はもちろん、周辺環境への配慮や地域住民の安心につながる重要なステップです。
建設泥水の脱水・減容化技術|遠心脱水・ベルトプレス・天日乾燥の比較
泥水や汚泥の脱水・減容化は、処理コスト削減と適正処分の観点から非常に重要です。泥水をそのまま捨てれば大量の液体産業廃棄物となりますが、固形分と水に分離して脱水ケーキ(固形物)にすれば、運搬・処分すべき量を大幅に減らせます。ここでは建設泥水や汚泥に用いられる代表的な脱水方式である遠心脱水機、ベルトプレス脱水機、天日乾燥の特徴を比較します。
- 遠心脱水機による脱水: 円筒状の容器を高速回転させ、その遠心力によって泥水中の固形物と水分を分離する方式です。泥水(スラリー)を投入すると比重差で固形分が外側に押し付けられ、水分が分離・排出されます。メリットは処理速度が速く、コンパクトな装置で連続処理が可能な点です。設置スペースが小さいため、狭い現場や大量処理が必要な場合にも対応しやすく、密閉構造で悪臭漏れも少ないといった長所があります。一方、デメリットとして消費エネルギーが比較的大きく、装置の振動・騒音対策やメンテナンスに注意が必要です。運転コストが高めですが、多様な種類の汚泥に対応できる適応力の広さもあり、建設現場でも掘削泥水の処理などにしばしば用いられます。
- ベルトプレス脱水機による脱水: 2本の無端ベルト(ろ布)の間に泥水を挟み、圧搾力をかけながら脱水する連続式の機械です。泥水はまず重力濾過部で自由水を切り、残ったフロックをベルトでサンドイッチしてローラーで圧縮することで水分を絞り出します。メリットは構造がシンプルで処理状況を目視確認しやすく、連続的に脱水ケーキを排出できる点です。また遠心力や真空を使わないため省エネルギーで、振動や騒音も少なめです。装置自体の価格(イニシャルコスト)も比較的低い傾向があります。デメリットとしては、高含水の泥水を処理する際にベルト(ろ布)が目詰まりしやすいため、洗浄水で定期的にベルトを清掃する必要があります。油分を多く含む汚泥ではベルトが滑って脱水できない場合もあり、汚泥の性状によっては不向きです。それでも建設現場で発生する無機系の泥水処理には適用しやすく、遠心脱水より電力を抑えて大量の泥水を比較的低コストで処理できる点から、多くの下水処理場やプラントで採用されています。
- 天日乾燥(自然乾燥)による脱水: 太陽熱と蒸発を利用して自然に水分を飛ばす方法です。屋外の乾燥床(オープンな砂利床やプール)に薄く泥土を広げ、太陽光と風で水分を蒸発させて乾燥させます。メリットは機械設備を使わないためコストが低く、エネルギーを必要としない点です。十分な面積と時間さえ確保できれば、最終的な含水率は機械脱水より大幅に下げることも可能です(例: 含水率83%の脱水ケーキを、天日乾燥で10%程度まで下げれば重量は5分の1以下になります)。乾燥が進めばスコップや重機で固形土として扱えるようになるため、処分量・運搬回数の劇的な削減につながります。デメリットは広い土地と長い時間を要することです。一般に下水汚泥を含水率85%程度まで乾燥させるには、夏場でも2~3週間程度の晴天が必要とされます。また雨天時には乾燥が進まないどころか泥が再び水分を含んでしまうため、天候に左右されやすい欠点があります。臭気の拡散やハエ発生など衛生面の課題もあるため、市街地や大量発生する現場には不向きです。しかし小規模な工事や仮設の泥置き場では、シートを掛けて雨を防ぎつつ天日に晒す簡易乾燥が行われるケースもあります。環境負荷が低く設備費もかからないため、条件が許せば検討したい方法です。
これら3つの脱水手法は一長一短があり、現場の状況に応じて使い分けられています。遠心脱水は装置コンパクトで迅速だが高コスト、ベルトプレスは経済的だがお手入れ必要、天日乾燥はコスト最小だがスペース・天候がネック、といった具合です。それぞれのメリット・デメリットをまとめると下記のようになります。
脱水方法が…
・遠心脱水機
【メリット】処理スピードが速い(大量処理向き)、設置面積が小さい、密閉構造で臭気漏れが少ない
【デメリット】電力消費が大きい、振動・騒音対策が必要、設備・運用コストが高め
・ベルトプレス脱水機
【メリット】構造が簡単で操作・監視が容易、省エネ・低振動で連続処理可能、装置コストが比較的安価
【デメリット】高圧洗浄などベルト清掃が必要、油分を含む泥は処理困難、ろ布の定期交換が必要
・天日乾燥
【メリット】ランニングコストほぼゼロ、機械設備不要でシンプル、最終含水率を大幅低減できる可能性
【デメリット】広い乾燥ヤードと長期間が必要、天候に左右される(雨天不可)、悪臭・害虫対策が必要で都市部不向き
建設現場では、処理スピード重視なら遠心脱水機、維持管理や経済性重視ならベルトプレス、規模が小さく時間に余裕があれば天日乾燥、といった使い分けがされています。近年はこれらの中間にあたるスクリュープレス脱水機やフィルタープレス、多重円盤脱水機など新たな方式も実用化されていますが、基本的な考え方は同じです。「いかに効率よく水分を除去し、廃棄物容量を減らすか」が泥水・汚泥処理の成否を握るポイントであり、適切な脱水技術の選定が求められます。
建設系廃棄物の法規制対応|建設リサイクル法・廃棄物処理法・土壌汚染対策法
建設現場の泥水や汚泥、浚渫土などを適正に処理・処分するには、関係する法規制を十分に理解し遵守する必要があります。ここでは特に重要な「建設リサイクル法」「廃棄物処理法」「土壌汚染対策法」のポイントを解説します。
- 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律): 建設リサイクル法は、特定の建設資材(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材、建設混合廃棄物など)の分別解体と再資源化を義務付けた法律です。建設汚泥自体は法律上の「特定資材」には含まれていませんが、国交省のガイドラインにより建設汚泥や浚渫土の再生利用が強く推奨されています。例えば、改良処理した建設汚泥を他の工事の埋め戻し土に利用する場合、建設リサイクル法の精神に則ったリサイクルとみなされます。実際に国交省「建設汚泥リサイクル事例集」では、建設汚泥処理土を盛土材として活用した事例などが紹介されています。したがって、泥水や浚渫土も可能な限り発生抑制と再資源化を図ることが望ましく、法の趣旨に沿った対応として現場での泥水再利用システム導入や汚泥の改質リサイクルが求められる傾向にあります。
- 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律): 建設現場から出る泥水・汚泥・し渣類は、多くが産業廃棄物に該当します(事業活動に伴う汚泥、ごみ類など)。とりわけ泥水を処理して得られる建設汚泥は「無機性汚泥」という産業廃棄物として扱われ、処理・運搬には許可業者への委託とマニフェスト(産廃管理票)の交付が必要です。廃棄物処理法上、地山から掘削された土砂そのものは廃棄物ではなく有価物として扱えますが、含水率が高く流動状のもの(=建設汚泥)は明確に汚泥廃棄物と定義されています。したがって、掘削時点で泥状になったものを場外搬出する場合は産業廃棄物処理のルールを守らねばなりません。具体的には、現場外へ運ぶ際は泥水用の密閉ダンプ(フタ付車両)を用いて飛散や漏洩を防止し、受入先の中間処理業者や最終処分場が適正に許可を得た施設であることを確認します。また、建設廃棄物処理指針では建設汚泥の減量化・再生利用が求められており、排出事業者(工事発注者・受注者)は発生抑制と適正処理に責任を負います。違法な投棄や不適切処理を防ぐためにも、廃棄物処理法に則った計画・管理を徹底することが重要です。
- 土壌汚染対策法: 土壌汚染対策法は、一定規模以上の土地の形質変更時や有害物質使用特定施設の廃止時に土壌調査を義務付け、汚染が判明した土地の適正管理・浄化を図る法律です。建設現場の泥土処理に直接適用されるケースは限定的ですが、例えば重金属等で汚染された建設汚泥を埋立処分した先の土地が将来利用される場合、この法律の規制を受ける可能性があります。汚染土壌を埋め戻したことで環境基準超過の有害物質が地下に残存すれば、その土地は知事指定を受け、周辺へのリスク低減措置や掘削土の搬出規制などが課されます。したがって、建設発生土や処理汚泥を現場内外で再利用する際には有害物の含有や溶出が基準以下であることを確認し、安全な形で利用することが求められます。土壌汚染対策法の観点からも、重金属等を含む可能性がある泥水・浚渫土は闇雲に埋め立てず、必要に応じて浄化処理(例:薬剤固定化や洗浄)を施してから処分・利用することが望ましいと言えます。なお、工事に伴う土地改変で有害物質が露出した場合(例えば、掘削により鉛汚染土が出てきた等)は、法的義務はなくとも自主的に土壌分析を行い適正処理することが環境リスクマネジメント上重要です。
以上のように、建設系廃棄物に関する法規制は多岐にわたりますが、要約すれば「発生抑制」「再資源化」「適正処分」の3点がキーワードです。建設リサイクル法の理念に沿って、泥水・汚泥も可能な限りリサイクルを図り、どうしても廃棄する部分については廃棄物処理法を厳守して無害化・安定化処分することが求められます。加えて、環境リスクが残らないよう土壌汚染の視点も持ちながら処理計画を立案することが、これからの建設現場には求められているのです。
アクトの建設現場支援実績|効率的処理と環境負荷削減の成功事例
建設現場の泥水・汚泥処理において、株式会社アクトは豊富な実績と独自技術で数多くの課題解決に貢献してきました。その技術力と環境配慮型ソリューションの実例をいくつかご紹介します。
- 官公庁プロジェクトへの採用実績: アクトが開発・提供する無機系凝集剤「水夢(すいむ)」は、その高い処理性能と環境安全性が評価され、2004年には徳島県の橋梁工事に伴う泥水処理で国土交通省から環境配慮型凝集剤として採用されました。また2015年には、東京電力福島第一原子力発電所事故後の汚染水処理対策において農林水産省から指定を受けるなど、公的機関の大規模プロジェクトにも起用されています。これは「水夢」の確かな性能が公式に認められた証であり、環境中の有害物質を的確に除去しつつ処理水を再利用するというアクトの技術力の高さを物語っています。
- 多業種・多現場での課題解決: アクトは創業以来、340社以上の企業に廃水・汚泥処理技術を提供してきた実績があり、その適用分野は製造業の塗装廃水から食品工場排水、さらには土木建設業のトンネル工事泥水や生コン車洗浄水処理まで多岐にわたります。いずれのケースでも、従来は処理が難しかった廃水・泥水に対し、オーダーメイドの薬剤処方や小型凝集沈殿装置の提案などで顧客の課題解決に寄与しています。例えばトンネル工事由来の高濃度泥水処理では、「水夢」による高速凝集沈殿によって濁水を短時間で基準内に浄化し、現場での再利用や安全放流を可能にしました。生コンプラントの洗浄排水では、金属系顔料を含む強アルカリ廃水を中和剤「融夢」と「水夢」の組み合わせで無害化し、沈殿スラッジを大幅減容化するといった成果を上げています。これらの実績は、単に法規制をクリアするだけでなく現場のコスト削減や環境負荷低減にもつながるソリューションとして高く評価されています。
- コスト50~70%削減と環境負荷低減の両立: アクトの無機凝集剤ソリューションは、単なる薬剤費の安さではなく「トータルでの処理コスト低減」を実現する点が強みです。実際の導入事例では、従来高額だった液体廃棄物の処理費用を固形化による産廃量削減で50~70%カットしたケースもあり、難処理廃水を無害化することで企業の環境コンプライアンス強化と処理コスト圧縮を両立させています。例えばある工場では、重金属を含む排水を水夢で処理して排出水を再利用可能なほど浄化し、一方で出てきた脱水ケーキは安定化処理して埋立処分量を最小化しました。その結果、水道代・排水処理代の大幅削減とゼロエミッションに近い形での廃棄物管理が実現しました。こうした事例は、単に法律を守るだけでなくESG経営の観点からも環境負荷の本質的低減につながる取り組みとして注目されています。
- 技術開発とカスタマイズ対応: アクトが支持される理由の一つに、廃液ごとのオーダーメイド対応があります。同社は300種類以上の廃水試験データに基づき、凝集剤「水夢」を様々なタイプの汚水に合わせてカスタマイズ調製できる体制を整えています。小ロット(1kg)からの注文にも対応し、試験→処方設計→現地適用まで一貫してサポートすることで、「泥水処理なんて初めて…」という現場担当者でもスムーズに導入できる仕組みです。さらに、必要に応じて同社開発の小型凝集沈殿装置「ACT-200」や簡易ろ過セット等も取り扱っており、工事現場にも省スペースで設置可能な処理システムを提供しています。これにより、狭小地や都市部の仮設ヤードでも泥水処理を自前で完結でき、産廃の外部搬出量を削減して環境リスクとコストの低減を図っています。
以上のように、株式会社アクトは高度な水処理薬剤技術と現場対応力によって、建設現場における泥水・浚渫土処理の数々の成功事例を築いてきました。その取り組みは、単なる汚泥処理に留まらず「再利用型処理システム」で現場の水を循環利用する提案へと進化しており、効率的処理と環境負荷削減の両立という現代の要請に応えるものです。建設業界においても持続可能性やSDGsが重視される中、アクトの技術力は他社との差別化ポイントとなっており、今後ますます多くの現場で安全・確実・経済的な泥水処理のソリューションとして活躍が期待されています。

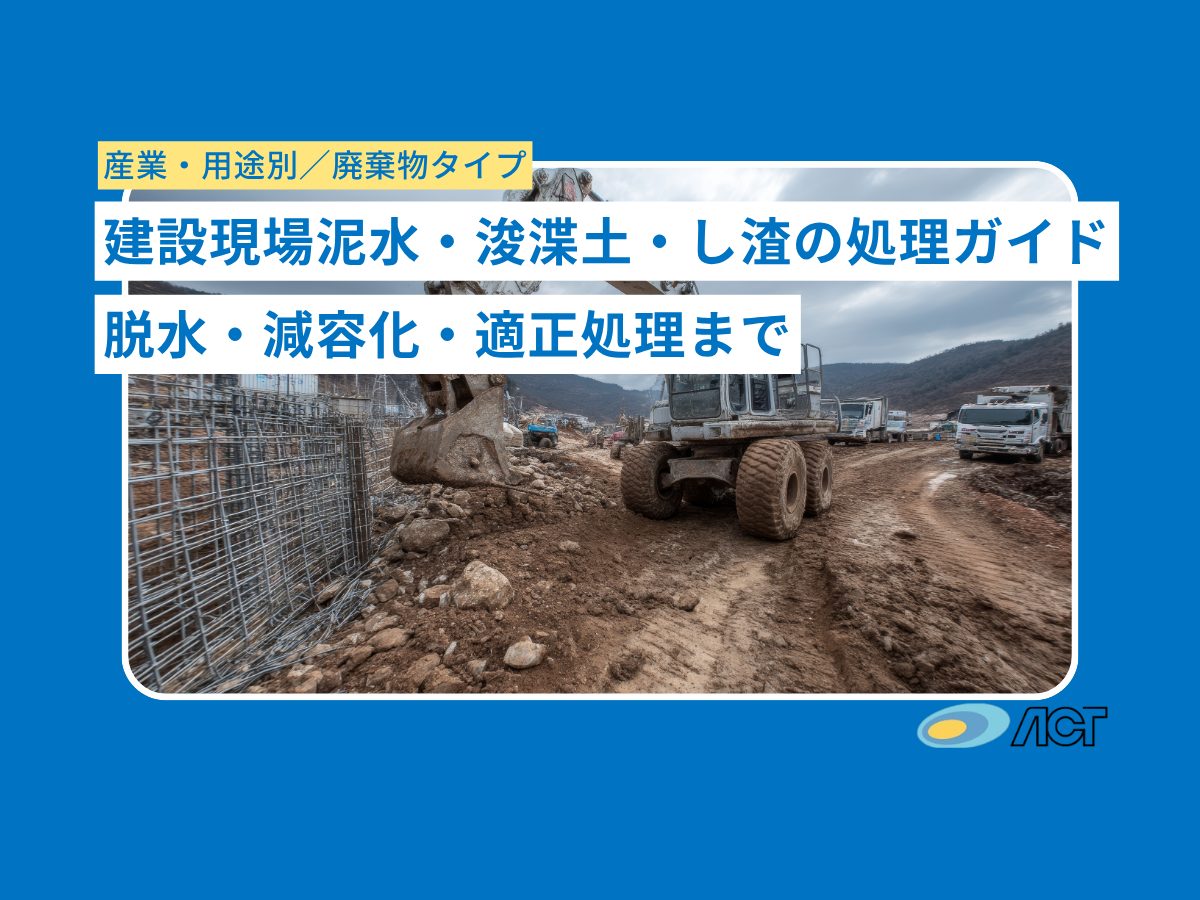
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)