工場や事業所の排水処理で広く採用されているCAS法(活性汚泥法)は、有機汚濁物質の効率的な除去が可能な生物処理プロセスです。しかし、最適な運転には微生物の管理や設備制御に関する専門的なノウハウが不可欠です。適切なMLSS(混合液浮遊物質)濃度の維持や返送汚泥の調整、エネルギー消費の抑制など、管理すべきポイントは多岐にわたります。また、バルキングや泡立ち等のトラブル対策も安定運転の鍵となります。本ガイドではCAS法の基本原理からMLSS管理の最適化、返送汚泥システムの運用ポイント、省エネルギー運転の方法、さらにバルキング・泡立ち対策まで分かりやすく解説します。排水管理担当者の方はぜひ参考にしてください。
CAS法の基本原理|活性汚泥・微生物・有機物分解のメカニズム
活性汚泥法(CAS法)とは、排水中の有機物を好気性微生物(活性汚泥)に分解させて無害化する処理方式です。まず排水を曝気槽(エアレーションタンク)に導入し、空気を送り込んで酸素を溶解させます。槽内では微生物が酸素を利用して排水中のBOD成分(有機汚濁物質)を取り込み、代謝によって二酸化炭素と水へと分解します。微生物は増殖しながら汚泥フロック(塊状の凝集体)を形成し、有機物を効率良く除去します。
標準的な活性汚泥法(CAS法)のプロセスフロー:原水は最初沈殿池で大きな固形物を除去された後、曝気槽(反応タンク)に送られます。曝気槽内では活性汚泥により有機物の分解が行われ、処理後の混合液は最終沈殿槽へ移動します。最終沈殿槽で活性汚泥が沈降分離し、上澄みの処理水が得られます。一部の沈殿汚泥は返送汚泥として再び曝気槽へ戻し、微生物濃度(MLSS)を維持します。残りの沈殿汚泥は余剰汚泥として系外に排出・処理されます。沈殿槽を設けて汚泥を返送することが活性汚泥法の必須要件であり、返送がない方式は生物膜法など別のプロセスになります。このように循環させることで微生物量を高く保ち、効率的な有機物分解を可能にしている点がCAS法のポイントです。
活性汚泥法は高い有機物除去効率と大量処理への適応性を備え、下水処理場から産業排水まで幅広く利用されてきました。適切に管理された場合、BOD除去率95%以上といった高い処理水質も達成可能です。一方で課題としてエネルギー消費が大きいことや、運転管理の難しさが挙げられます。曝気に電力を要するため運転コストが高く、管理が不十分だと処理効率が低下する恐れがあります。また、沈殿分離工程を要するため設備が大掛かりで、汚泥の沈降性悪化によるトラブル対策も必要です。つまりCAS法は実績豊富で有効な処理法である反面、安定稼働のためには的確な汚泥管理と設備制御が求められると言えるでしょう。
MLSS管理の最適化|濃度制御・SVI管理・汚泥齢調整
MLSS(混合液浮遊物質量)は曝気槽内に浮遊する活性汚泥(微生物+未分解有機物)の濃度を示す指標で、単位はmg/Lです。この値が槽内の微生物量を表しており、適正範囲に維持することが処理プロセス安定化の基本となります。一般的な標準活性汚泥法ではMLSS約2,000~4,000mg/Lが目安とされ、長時間曝気方式では4,000~8,000mg/L程度まで高濃度で運転する場合もあります。MLSS濃度が高すぎても低すぎても問題であり、過剰な場合は沈降しにくくなって汚泥の沈降性能(SVI)が悪化し、反対に低すぎると有機物負荷に対して微生物数が不足して分解能力を発揮できません。したがって設計上定められた範囲内にMLSSを制御することが重要です。運転管理では定期的に混合液を採取してMLSSを測定し、数値の推移に応じて余剰汚泥の引き抜き量を調整します。例えば、排水負荷の増加でMLSS低下傾向が見られる場合は汚泥引き抜きを減らして微生物量を増やし、逆にMLSS過多で沈降不良の兆候があれば引き抜きを増やして汚泥を若返らせる、といった具合です。日々の測定・調整によって狙った濃度に維持することが安定運転の第一歩となります。
MLSSの質にも目を配る必要があります。測定した懸濁固形物量のうち有機性微生物由来の成分(MLVSS)の割合や、顕微鏡観察による微生物群集の健康状態などもチェックし、フロックの状態を把握します。フロックが適度な大きさと密度を保っていることが沈降分離には重要で、崩壊しかけた微細なフロック(ピンフロック)が多い場合は処理水の清澄度悪化に繋がるため対策が必要です。
次にSVI(汚泥容積指数)の管理です。SVIは活性汚泥の沈みやすさを示す指標で、混合液を静置30分後の沈殿汚泥体積(SV)[%]をMLSS濃度で割って算出します(単位mL/g)。数値が小さいほど同じ濃度の汚泥がコンパクトに沈降する(沈降性良好)ことを意味し、正常な活性汚泥のSVIはおよそ50~150 mL/gの範囲です。この範囲に収まっていれば沈殿分離は順調と判断できますが、SVIが200を超えると沈降性の悪化した状態であり、汚泥が膨張して沈まないバルキング発生の兆候となります。実際、糸状性菌が増殖する糸状性バルキングや、汚泥がゲル状に膨れて比重が低下する非凝集性バルキングではSVIが300以上に達するケースもあります。SVIが高騰し沈殿槽の汚泥界面が上昇してきたら、原因を調査して早急に対策を講じる必要があります。対策例としては以下のようなものがあります:
- 溶存酸素(DO)不足の解消 – 酸素供給が不十分だと糸状菌が繁殖しやすいため、曝気量を増やす・散気装置を点検する等でDOを適正値まで高めます。
- 栄養バランスの是正 – 廃水中の窒素やリンが極端に不足している場合、微生物の増殖が滞りフロック形成不良に陥ることがあります。必要に応じて窒素源(尿素など)やリン酸塩を添加し、BOD:窒素:リンのバランス(一般に100:5:1程度)を整えます。
- 有機負荷の抑制 – 一時的な高負荷流入が続くと微生物群集のバランスが崩れ沈降性悪化を招くため、調整槽での平均化や流入量コントロールにより負荷変動を緩和します。
- 最終手段 – フロックを橋架けする糸状菌(例えばノカルジア等)が大量発生して手に負えない場合、塩素剤の投与で糸状菌のみを選択的に死滅させる方法も実務上行われます。ただし効果は一時的で根本解決にはならないため、並行して原因除去策を講じることが重要です。
このようにSVIは活性汚泥の健康状態を示す重要なバロメーターであり、定期的に測定して適正範囲(50~150程度)に収まるよう運転条件を調整することが、生物処理を安定化させる鍵となります。
最後に汚泥齢(SRT, Sludge Retention Time)の管理です。汚泥齢とは汚泥(微生物)がシステム内に留まる平均日数を指し、「槽内の微生物量」を「1日あたりに排出される微生物量」で割ることで求められます。要するにどのくらいの期間、微生物を活かせておくかという指標です。一般的な有機物除去目的の活性汚泥法では汚泥齢5~15日程度に設定されるケースが多く、これにより増殖の早い異養菌が主役となってBOD分解が進みます。一方、窒素の硝化などを行う高度処理では硝化菌の世代時間が長いため15~30日程度の汚泥齢が必要になることもあります。汚泥齢が長すぎる場合、微生物が老朽化して内生呼吸による減量が進み、フロックの凝集性低下や栄養塩不足による糸状菌増殖(=バルキング)を招きやすくなります。逆に短すぎる場合、増殖の遅い硝化菌などが系内に蓄積できず、窒素除去性能の低下や、生物種の多様性低下による処理の不安定化が起こりえます。適正な汚泥齢は処理目的によって異なりますが、運転上は余剰汚泥の引き抜き量を調節することで実質的にコントロールできます。日々の汚泥引き抜き操作によって微生物の平均滞留日数を調整し、自施設の目標とする汚泥齢(=処理性能と汚泥生成量のバランス)に維持しましょう。例えば高度処理が不要な場合は汚泥齢を短めに保って過剰な老化を防ぎ、必要最小限の微生物量で効率的にBOD除去することが省コストにも繋がります。反対に、処理水質に余裕がある範囲で汚泥齢を長めにとれば汚泥発生量を減らす効果も期待できます(微生物自身が分解され減量するため)。このように汚泥齢は処理性能と汚泥処理コストのバランスを左右する重要因子であり、自施設の排水特性に応じた最適値を見極めることが肝要です。
返送汚泥システム|返送比・濃縮・余剰汚泥引抜の最適化
活性汚泥法では、最終沈殿槽で分離した汚泥の一部を曝気槽へ戻す返送汚泥(RAS: Return Activated Sludge)の仕組みが不可欠です。返送汚泥の主目的は曝気槽内の微生物濃度(MLSS)を必要値に保持することであり、これによって原水BODを処理できるだけの十分な生物量を確保します。一般に返送量は原水流量の50~100%程度(返送比50~100%)に設定されることが多く、例えば処理水量が1,000 m³/日の場合、500~1,000 m³/日の汚泥を返送する計算になります。適切な返送比の設定は、沈殿槽内の汚泥滞留を防ぎつつ、曝気槽への微生物補充を安定させる上で重要です。
返送汚泥量の制御方法には、流入量に対して一定割合で返送する方式(返送率一定制御)と、常に一定量を返送する方式(返送量一定制御)があります。一般的には流入変動に応じて自動的に比例制御する「返送率一定」が採用されることが多く、原水量が増えたときは返送量も増やして汚泥流出を防ぎ、減ったときは返送量を絞って沈殿槽内で汚泥が滞留しすぎないようにします。一方、小規模施設などで流量が安定している場合には「返送量一定」でも問題なく、運転が簡易になるメリットがあります。いずれにせよ大切なのは、沈殿槽内の汚泥層の厚み(汚泥界面高さ)を監視し、適切な範囲に収まるよう返送ポンプを調整することです。沈殿槽底部の汚泥が増えすぎれば返送量を増やして引き抜き、逆に底部がスカスカであれば返送量を減らすなどして、沈殿槽内の滞留汚泥量をコントロールします。沈殿槽で維持すべき汚泥層については、汚泥の沈降性や脱窒による浮上現象の有無などを踏まえて各施設ごとに基準値を決めると良いでしょう。
返送汚泥の濃縮もポイントの一つです。返送される汚泥はできるだけ濃度が高い方が望ましく、含水率の高い希薄な汚泥を大量に送り返すと曝気槽の有効容量が減ってしまいます。通常、最終沈殿槽からくみ上げる返送汚泥は底部高濃度層から採取されますが、それでも濃度が不足する場合は汚泥濃縮槽で一旦濃縮してから曝気槽に戻す方法もあります。特に大規模処理場では、最終沈殿池の汚泥と初沈殿池由来の生汚泥を集めて重力濃縮し、上澄みを分離した上で必要量を返送するシステムが採用されています。濃縮によって返送汚泥の体積を減らせればポンプ動力の節減にもなり、省エネ効果が期待できます。
一方、汚泥循環の過程で常に増え続ける微生物を系外に排出する必要があり、これが余剰汚泥の引き抜きです。余剰汚泥は先述の通りMLSSや汚泥齢の調整弁として機能します。引き抜き量が少なすぎると汚泥が系内に蓄積してMLSS過多・汚泥齢長期化による処理悪化を招き、逆に引き抜きすぎると生物量不足で処理不良や微生物の若返りすぎ(未熟汚泥化)による沈降不良を引き起こします。適正な引き抜き量の決定には、試行錯誤しつつ経験を積むことが大切です。基本的には「目標MLSS濃度に対する現在の乖離」を基準に増減させますが、急激な変更は避け、日々少しずつ調整していくのが安全です。例えば汚泥引き抜きポンプのタイマー時間を1日に数分単位で増減させ、その効果を数日観察する、といった手法で適正点を探ります。また引き抜きのタイミングも考慮しましょう。負荷が低い深夜帯に集中して引き抜く、あるいは連続ではなく間欠的に排出することで、処理水質への影響を緩和できます。余剰汚泥管理の最終目標は、処理性能を維持しつつ汚泥を過剰に溜め込まないことです。そのために日常からMLSS・SVIの動向を把握し、前述のとおり汚泥引き抜き量で微生物量と汚泥齢をコントロールすることが求められます。
CAS法の省エネルギー運転|曝気制御・負荷調整・電力削減
活性汚泥法の運転コストの中でも特に大きな割合を占めるのが曝気に要する電力です。一般に排水処理プラント全体の電力使用量のうち30~60%程度が曝気工程で消費されていると言われており、省エネルギー化を図る上で曝気の効率向上は避けて通れません。幸いにも、近年は溶存酸素計(DO計)やインバータ制御ブロワなどの導入によって必要な時に必要な量の空気だけを供給する運転が可能になってきています。米国EPAの試算によれば、DOセンサーによる自動制御を導入した結果、曝気に伴うエネルギーコストを最大50%削減できた例もあるとのことです。このように、従来は常に全開で運転しがちだった送風機を、処理状況に応じてきめ細かく制御することで大幅な電力削減が可能です。
省エネ運転の第一のポイントはDO(溶存酸素)制御の最適化です。好気性微生物が十分な代謝活動を行うには概ね2mg/L程度のDOが必要とされるため、多くの処理施設では曝気槽DO=2mg/L前後を目標値に設定しています。DOがそれ以上に高すぎても微生物の活動が劇的に向上するわけではなく、単に余分な電力を消費するだけでなく一部の糸状菌増殖を促す可能性も指摘されています。そのため「必要以上に酸素を送り込みすぎない」という発想が省エネには重要です。具体的には、自動DO調節機能を活用し、ターゲット値を維持するようブロワの風量をリアルタイムで可変制御します。負荷が低下してDOが上昇傾向になればブロワ回転数を絞り、逆に負荷増大でDO低下時には増量するといった具合に、自動制御が常に適切な酸素レベルを守ってくれます。手動操作の場合でも、処理水質やSVIに問題がない範囲でDO目標値をやや低めに設定し直すだけでも省エネにつながります。注意すべきは、DOが2mg/Lを下回って長時間推移する状況です。DO不足は微生物の代謝低下を招くだけでなく、フロック内部が無酸素化して一部の微生物が死滅・フロック崩壊する恐れがあります。加えて、低酸素下では嫌気性を好む糸状菌(例えばミクロトリクスやノカルジア類)が異常繁殖し、前述のバルキングや泡沫トラブルの原因となります。したがって省エネとは言えども必要最低限のDOは確保するというバランスが重要です。近年はブロワの回転数制御だけでなく、槽内に設置した酸素フィードバック制御型の曝気装置(例: AQUABOY®など)によって微生物周辺のDOをきめ細かくコントロールする技術も普及しています。これらを活用し、「微生物が快適に働ける環境を保ちつつ無駄なエアを送らない」運転を目指しましょう。
次に負荷調整による省エネです。排水の流量・水質は時間帯や操業状況によって変動します。日中に高負荷の工場では夜間に負荷が下がることも多く、その間も同じ曝気量で運転するのはエネルギーの無駄になります。対策として、調整槽を用いて原水負荷を平準化する方法があります。例えばピーク時の高負荷を一部貯留して夜間に回すことで、一日を通じて比較的一定の負荷で処理系を運転できます。これにより、ピーク対応のために過大な曝気設備を常時稼働させる必要がなくなり、結果的に平均風量を下げて省エネに繋げられます。また、段階曝気や交互曝気の導入も負荷変動への柔軟な対応策です。複数の曝気槽を直列配置し段階的に負荷を処理するステップフィード方式や、1槽内で曝気と撹拌を切り替える間欠曝気方式(疑似的なSBR運転)によって、不要な全槽曝気時間を減らすことができます。さらに機器の高効率化も基本施策です。老朽化した散気管を新型の微細気泡ディフューザーに更新すれば酸素移行効率が向上し、同じDO維持に必要な空気量を減らせます。ブロワも、従来のレシプロ式やルーツ式から近年主流のターボブロワに置き換えることで、省電力かつ細かな風量制御が可能となります。これら設備面の投資は初期費用がかかりますが、電力削減効果で中長期的に十分ペイできるケースも多いため検討の価値があります。
最後に汚泥処理側の工夫も間接的な省エネに寄与します。例えば余剰汚泥を濃縮・脱水する際、凝集剤の最適投入や脱水機の効率運転によって含水率を下げられれば、後工程の乾燥や焼却に必要なエネルギー削減に繋がります。また、汚泥処理量そのものを減らすこと(=汚泥減量化)も有効で、前述のように適切な汚泥齢管理により発生汚泥を減らせれば、脱水・処分にかかる電力や燃料の節約となります。近年では嫌気性消化による汚泥減量と併せて消化ガスをエネルギー回収する試みも増えており、CAS法と組み合わせた汚泥消化プロセスでエネルギーの自給を図る高度な事例もあります。総じて、CAS法プラントの省エネ運転は「曝気工程の効率化」が中心となりますが、「負荷の平準化」と「設備更新」、さらに「汚泥処理の効率化」まで含めた包括的な視点で取り組むことが求められます。これらを実践することで、安定した処理水質を維持しながら電力コストを大幅に削減することが可能となるでしょう。
CAS法のトラブル対策|バルキング・泡立ち・処理不良の解決
活性汚泥法では様々な原因で処理状態の悪化が起こりえますが、代表的なトラブルとして汚泥膨化(バルキング)、曝気槽の発泡(泡立ち)、および処理水質の処理不良が挙げられます。それぞれの現象と対策のポイントを確認しておきましょう。
- バルキング(汚泥膨化): 最終沈殿槽で活性汚泥が沈まずに膨張・浮遊し、処理水中に流出してしまう現象です。バルキングはSVIの項でも触れましたが、糸状性細菌の増殖やフロックの非凝集化によって引き起こされます。原因として多いのは低DOや栄養塩不足による糸状菌(例: ミクロトリクス、ノカルジア)の異常増殖、または負荷急変や有機酸蓄積による粘性物質の過剰生成などです。対策は前述のSVI管理と重なりますが、まずDOを適正に維持し(目安2mg/L以上)糸状菌が好む低酸素環境を避けます。次にBODに対する栄養塩(窒素・リン)の比率を確認し、不足があれば添加して微生物の増殖環境を整えます。加えて、負荷変動の緩和やpHの安定化も有効です。負荷ピーク時には原水調整や段階給水でショックを和らげ、pHは中性付近(6.5~7.5)に維持して微生物へのストレスを減らします。これらの基本対策で改善しない頑固な糸状性バルキングには、塩素剤の投与による糸状菌の選択的除去も検討されます(一時しのぎであり根本対策と併用する必要あり)。いずれの場合も、バルキングを放置すると処理水質の悪化と環境流出リスクが高まるため、日々のSV30試験や顕微鏡観察で兆候を掴み早期に手を打つことが重要です。
- 泡立ち(曝気槽の発泡): 曝気槽の表面が泡で覆われ、汚泥を含む泡が外部にあふれ出すトラブルです。発泡の原因はいくつかありますが、一つは原水への発泡性物質の流入です。工場排水中の界面活性剤や油分は泡を安定化させるため、洗浄剤・切削油などが大量に流入すると激しい泡立ちを招くことがあります。この場合、該当工程の排水を分離・前処理するなどして発泡物質の流入抑制を図ることが根本対策となります。また、微生物の代謝異常も発泡要因です。負荷の急変や温度変動で処理バランスが崩れると、微生物が発泡性の中間代謝物(例えば過剰な多糖類など)を生成し泡立ちを引き起こすことがあります。これは一時的な現象である場合が多いものの、発泡中は処理機能が低下するため、負荷変動の抑制や温度管理で運転条件の安定化に努めます。さらに厄介なのが放線菌(ノカルジア等)の異常増殖による泡立ちです。放線菌は糸状性菌の一種で強い疎水性物質を産生し、これが泡と汚泥を結び付けて粘性の高い泡沫を形成します。放線菌は低栄養・高DO条件や長い汚泥齢で優占しやすいため、対策として汚泥齢を適正範囲に保ち、必要に応じて栄養塩を補給します。また曝気量を適切化し過剰曝気を避けることも放線菌の抑制に有効です(放線菌は好気性ですが増殖速度が遅く、汚泥日齢が長くなりすぎると優位になる傾向があります)。現に「低負荷(=エサ不足)状態で泡立ちが発生しやすい」ことが知られており、過度な過曝気でBODを使い果たしてしまわないよう注意が必要です。発泡への対処法としては、消泡剤の散布が即効性を持ちます。シリコーン系の消泡剤を噴霧すれば瞬時に泡は消えますが、同時に曝気槽内のDO低下を招く副作用もあるため、使用量・頻度は必要最小限に留めます。機械的手段では、泡を掻き落とす泡沫除去装置の設置や、水噴霧による泡消しも有効です。いずれにせよ、泡立ちを軽視すると作業環境の悪化(悪臭・汚泥の飛散)や処理水質の悪化(泡と共に汚泥が流出してSS上昇)につながるため、原因に応じた適切な対策で早期に沈静化させることが求められます。
- 処理不良(有機物除去の悪化): BODやCODの除去率が低下し、処理水質が基準を満たさなくなる状態です。代表的な原因としては、①処理能力オーバー(負荷過大)と、②汚泥の活性不足の二つが挙げられます。前者の場合、単純に現行設備の能力以上の汚濁負荷がかかっているため、酸素供給量不足や反応時間不足に陥っています。対策としては流入負荷を下げる(生産工程の排水発生量を削減する、希釈する等)か、設備能力を高める(ブロワを増強する、曝気槽容積を増やす等)ことになります。一時的な負荷オーバーであれば調整池への分流や流入カットも検討します。後者の「汚泥の活性不足」とは、微生物が元気に働けない状態に陥っているケースです。原因の一つは過曝気による飢餓です。BOD負荷が少なすぎる環境で長時間曝気を続けると微生物が餓死状態となり、外見的にはMLSSは十分あっても実際の分解能力が低下します。この場合、前段で述べたように汚泥齢を下げる(引き抜きを増やす)か、一部曝気槽を止めて休止槽にするなど運転モードを見直します。次に栄養塩不足。BODに見合った窒素・リンが供給されないと微生物が増殖できず、結果的に有機物分解が進みません。工場排水では高BODかつ窒素ゼロということもあり得るため、その際は適量の窒素源やリン酸を補給します。さらに阻害物質の流入も重大な原因です。重金属や殺菌剤、溶剤などが流入すると微生物が中毒を起こし処理が止まります。これについては事前の有害物質の除去・希釈やpH中和などの前処理を徹底し、本来生物処理にかけてはいけない負荷を遮断することが最重要です。処理不良が起きた場合は以上の観点から原因を調べ、必要に応じて活性汚泥の増強も行います。他所から健全な活性汚泥を種汚泥として導入したり、自社内で休止中の予備槽があればそちらで培養・増殖させてから主反応槽に戻すなど、微生物そのものを補充する対策です。加えて、水質悪化が環境基準超過につながる恐れがある場合には、応急処置として処理水の再循環(最終処理水を調整槽に戻し二次処理する)や活性炭の併用(溶解性の残留CODを吸着除去する)なども検討します。最も避けるべきは未処理のまま放流してしまう事態ですので、処理不良の兆候を感じたら早めに専門家に相談し、適切な是正措置によって法令順守と環境保全を最優先してください。
アクトの技術力と実績: アクトは20年以上にわたり水処理技術の研究開発を続け、「一つとして同じ廃液はない」という理念のもとで培ったカスタマイズ対応力を強みとしています。これまでに1,000社以上、延べ10,000種類を超える廃液に向き合い最適処理法を提案してきた実績があり、その膨大なデータベースに基づくノウハウは他社にない財産です。実際、官公庁・公共事業への技術採用(国土交通省・農水省の認定)や福島第一原発の汚染水処理への協力といった重大案件にも関わっており、累計340社以上の企業がアクトの製品・サービスを導入して排水課題を解決してきました。これはアクトの提供するソリューションが高い品質基準を満たし、信頼性が高いことの証と言えるでしょう。
生物処理最適化の成功事例: 例えば、ある水性塗料工場では従来の活性汚泥処理だけでは対応が難しかった高濃度の顔料含有排水に対し、アクト開発のゼオライト系凝集剤「水夢(SUIMU)」を用いた前処理と小型沈殿装置「ACT-200」を組み合わせるソリューションを提供しました。これにより、活性汚泥法では沈降しにくかった微細な顔料を効果的に固液分離することに成功し、同工場では年間処理コストを720万円から250万円へ約65%削減、廃液発生量も月20トンから1トンへ約95%削減という劇的な効果が得られました。さらに処理水の全項目で排水基準を余裕でクリアし、作業時間も大幅短縮(1日3時間かかっていた処理が30分に短縮)されるなど、法令遵守と経済的メリットを同時に実現した好例となっています。現場担当者からも「驚くほど処理が簡便で、短時間で誰でもできるようになった」という喜びの声をいただきました。
他社との差別化ポイント: アクトが選ばれる理由は、単に排水基準の数値をクリアするだけでなく処理コスト削減と環境負荷低減の両立を実現できる点にあります。自社開発した凝集剤「水夢」は無機系の材料で構成されており環境に優しく、また、お客様それぞれの排水成分に合わせたオーダーメイド調合が可能です。加えて従来の高分子凝集剤では処理が難しかった水性塗料・インキ排水や重金属含有排水にも対応でき、将来さらに規制が厳格化しても耐えうる高い浄化力を備えています。
これからますます企業には環境への責任が求められ、排水処理の最適化は事業継続における重要課題となっていきます。アクトではこれまで培った高度な技術力と豊富な実績をもとに、お客様の安定操業と環境保全を力強く支援いたします。廃液処理にお困りの際は、ぜひ私たち株式会社アクトにご相談ください。貴社の排水処理を一歩先のレベルへと導きます。
※本記事で紹介した数値・事例は一般的な参考値および一例であり、実際の最適値は処理対象や設備構成によって異なります。不明点や具体的な改善検討事項がございましたら専門家へお問い合わせください。また、記事内の社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

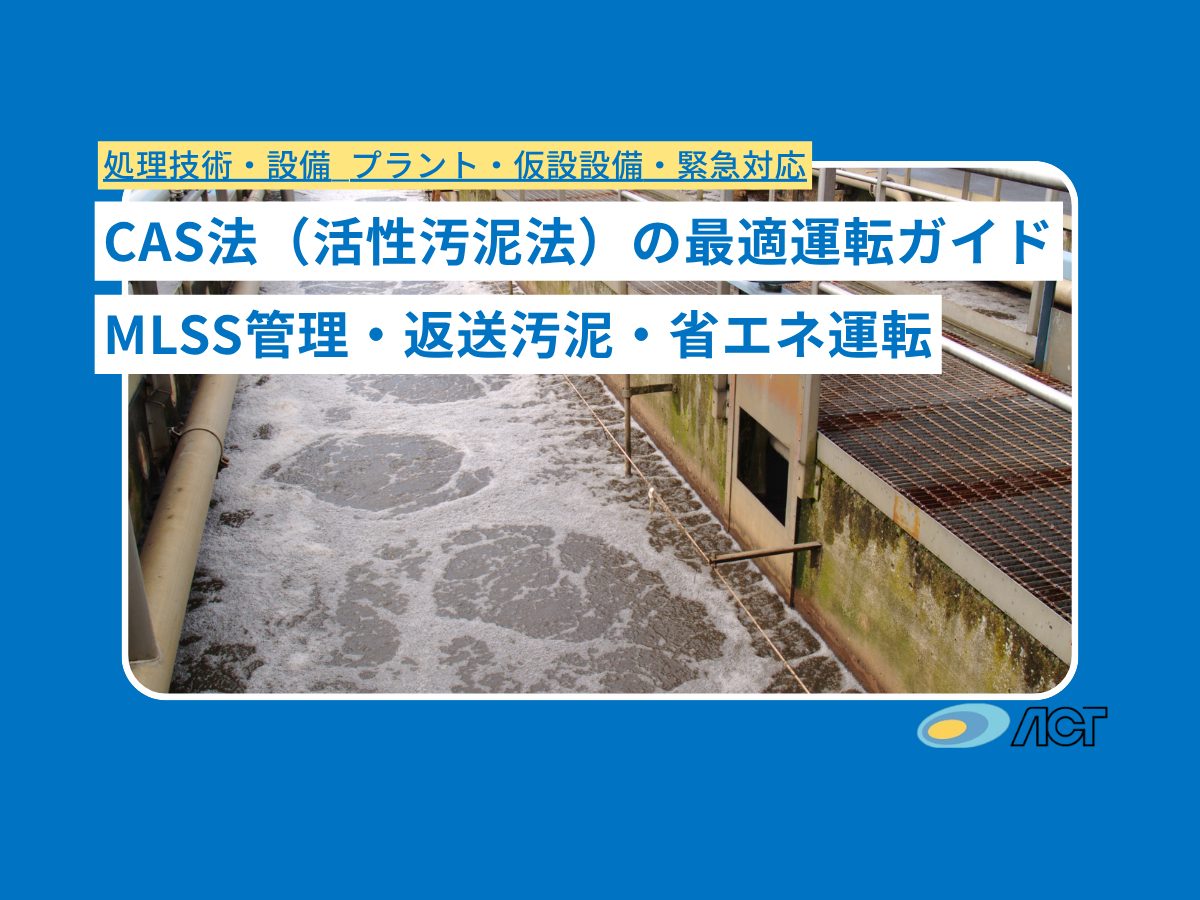
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)