BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中に含まれる有機物を好気性微生物が分解する際に必要とする酸素の量を示す水質指標です。単位は通常 mg/L(1リットルの水中で消費される酸素のミリグラム)で表され、BOD値が大きいほど水中の有機物汚染が深刻で水質が悪いことを意味します。言い換えれば、BODは水中の汚れ(主に有機汚濁)の度合いを示す代表的な指標であり、河川や排水の水質管理に広く使われています。工場や事業所の排水管理においても重要な監視項目で、環境基準や排水規制の対象となっています。
本記事では、BODの基本的な定義とその水質指標としての意味から始め、BODの測定方法と注意点、日本におけるBOD基準値と関連する法規制、そしてBOD値が高くなる原因とその影響について順を追って解説します。また、BODを低減するための技術と処理方法を紹介し、業界別に見たBOD管理のベストプラクティスや、排水処理におけるコスト最適化の戦略についても触れます。最後に、株式会社アクトのBOD改善実績と効果事例を取り上げ、同社の技術力がどのようにBOD問題の解決に貢献しているかをご紹介します。工場や事業所の排水管理担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
↑ 廃水処理に最適な凝集剤・アルカリ中和中和剤はこちら ↑
※モノタロウで購入するよりアクトから直接購入する方がお買い得。アクトから直接購入するにはinfo@act-yume.comに「購入希望」とメール
BODの基本定義と水質指標としての意味
BOD(Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量)は、水中の有機物質が微生物によって分解されるときに消費される酸素量を示したものです。特定の化学物質そのものの濃度を測っているわけではなく、「ある水試料を一定条件下で微生物に分解させたときにどれだけ酸素が減るか」という試験結果を指標化したものです。このため水質の汚れ具合、特に有機汚濁の程度を表す代表的な数値となっています。一般にBOD値が高い水ほど有機物による汚染が大きく、水質が悪化していると判断されます。
例えば、家庭排水や食品工場の排水のように有機物を多く含む水では、川のきれいな水に比べてBODが高くなります。微生物が有機物を盛んに分解する過程で水中の酸素が大量に消費されるためです。逆に、有機物の少ないきれいな水(山間部の清流など)はBODが低く、酸素が十分に残ります。BODは水質汚濁の程度を客観的に示す指数として、環境基準や排水基準にも採用されています。特に河川の水質環境基準では、用途に応じてAA類型(最も厳しい)~E類型までBODの目標値が定められており、清浄な水ほど低いBOD基準値(例:AA類型は1 mg/L以下、C類型で5 mg/L以下など)が設定されています。BODはこうした水環境レベルの評価だけでなく、工場や施設からの排水の規制値や、排水処理設備の性能評価にも用いられている重要な指標です。
BODという概念は19世紀末~20世紀初頭に水質汚濁が深刻化したイギリスで考案され、5日間培養による測定法(後述)が標準となりました。日本には戦後に導入され、水質汚濁防止法など各種法令で採用されています。現在ではCODと並んで代表的な水質指標となっており、水環境の保全と排水管理の双方で重視されています。
BOD測定方法と測定時の注意点
BODの測定方法は、一定の条件下で水中の酸素消費量を測定するというものです。一般的な手順は以下の通りです。
- 測定したい水の試料を採取し、必要に応じて希釈します(汚れが強い場合は薄め、きれいな場合はそのまま)。希釈にはあらかじめ酸素を飽和させた清浄な水(場合によっては活性汚泥由来の微生物を含めた「種水」)を使います。これは高濃度の排水ではそのままだと酸素がすぐ無くなってしまうため、測定レンジに入るよう薄めるためです。また微生物がほとんどいない水(例えば高度処理水や特殊な産業排水)の場合、適切な微生物を“植種”して測定することもあります。
- 調整した試料をBODボトル(フラン瓶)と呼ばれる密閉できるガラス瓶に入れ、20℃の恒温下で暗所にて5日間静置・培養します。培養前に溶存酸素量(DO)を測定し、5日間培養後にも再度DOを測定します。
- BOD値の算出:培養前後のDOの減少量から、希釈倍率を考慮してBOD(5日間で消費された酸素量、すなわちBOD_5)を計算します。例えば、培養前のDOが8.5 mg/Lで5日後に4.5 mg/Lまで低下していれば、酸素は4.0 mg/L消費されたことになります。もし試料を5倍に希釈していたなら、BOD_5は4.0×5=20 mg/Lという具合です。
このようにBOD測定には5日間という比較的長い時間がかかるため、結果が出るまでに日数を要します。その間、試料は一定温度で厳密に管理され、外部から酸素が供給されないよう密閉して行います。測定時の注意点として、ボトル内に気泡が入ると正確な酸素減少が測れないため注水時に細心の注意を払うこと、試料のpHや温度を所定条件(20℃、中性付近)に調整すること、必要に応じて硝化抑制剤を添加して炭素系BODのみを測るなどの配慮があります。BOD試験は特定の物質を直接測るのではなく微生物の働きを利用した試験結果ですので、手順を誤ると大きな誤差や再現性の低下を招くことになります。たとえば充分な希釈をしなかったために5日後にDOがゼロになってしまった場合や、逆に汚れが少なすぎてDOの減少がごくわずかしか起きなかった場合などは、再試験が必要です。
近年では5日間も待てない場合のために、短時間で結果を推定する簡易法も利用されています。例えば、試料中の有機物をセンサーでリアルタイムに酸化分解して酸素消費を測定する装置や、化学的酸素要求量(COD)や全有機炭素(TOC)から経験的にBODを推定する方法などがあります。ただし公式の環境分析や法規制の監視項目としては、依然として**5日間BOD測定(BOD_5)**が標準です。測定結果の信頼性を確保するため、試料採取から測定までの保管方法(温度保持や暗所保管)にも注意が必要です。また、工場排水などでは測定前の試料前処理として、大きな固形物や油膜を除去したり、必要に応じpH中和を行っておくことも正確な測定のためには重要です。
BOD基準値と法規制の詳細
BODの基準値について、環境行政上は大きく二つの観点があります。一つは先述した環境基準(公共用水域の水質目標値)で、もう一つが工場や事業場から出る排水に対する規制基準です。
まず環境基準では、人の健康保護や生活環境の保全のため、河川や湖沼・海域の水質目標が定められており、BODは河川の生活環境項目として採用されています。河川の場合、利用目的に応じてAA~Eの類型ごとにBOD目標値が設定され、例えば**AA類型は1 mg/L以下、A類型は2 mg/L以下、B類型3 mg/L以下、C類型5 mg/L以下…**といった水準になっています。これらはあくまで河川など受け入れ水域の望ましい環境レベルですが、この基準を守るために各地の下水処理場や流域全体での汚濁負荷削減が図られています。
次に工場や事業所の排水に関する法規制です。日本では主に水質汚濁防止法に基づき、公共用水域へ排水を行う事業場に対して排水基準が全国一律で定められています。BODについては、海や湖を除く河川等への排水では「1リットルあたり160 mg以下(1日平均120 mg/L)」という基準値が設定されています。つまり工場排水などを川や用水路に直接放流する場合、BODが160mg/Lを超えてはいけない(かつ日平均では120mg/L以下に抑える)という規制があります。これは全国一律の最低基準であり、地域によってはさらに厳しい基準が適用される場合があります。たとえば、東京や大阪などの大都市圏では水質総量規制の指定地域となっており、流域ごとにBOD排出負荷総量の削減計画が進められています。また、一部の地域では流域の環境容量に応じて個別に排水基準を強化しているケースもあります。
工場排水のBOD規制値160 mg/Lというのは、一見高い数値に思えるかもしれません。しかし、これは最低限守るべき基準であり、環境への影響を考えると多くのケースで実際の許容濃度はもっと低い値が求められます。たとえば公共用水域が湖沼や内湾の場合はBODではなくCODの基準が適用されたり、上水道の取水源付近ではBODの基準が強化されたりします。また、河川へ流すのではなく下水道に接続して排水する場合は水質汚濁防止法ではなく下水道法による規制(下水道への排除基準)が適用されます。この下水道への排水基準においてもBOD項目があり、一般的には600 mg/L以下程度の基準が設けられています。ただし下水処理場の能力を超える負荷が集中しないよう、工場系排水については地域条例でさらに厳しい値が定められることも多く、例えば東京都23区では製造業からの排水にはBOD 300 mg/L以下という厳しめの基準(上記600の半分)を適用しています。下水道に流す場合は、水質汚濁防止法上の160 mg/L基準は直接適用されませんが、下水処理場で処理しきれないような高濃度排水は受け入れてもらえないため、各事業者は下水道法の範囲内でBODを十分下げてから放流する必要があります。
まとめると、事業所の排水管理では「BOD 160 mg/L(日平均120 mg/L)」が最低限守るべきラインとなり、さらに地域や排出経路(直接放流か下水道接続か)によって厳しい目標値が課されることがあります。実際には多くの企業が環境負荷低減のため、社内基準としてこれよりかなり低いBOD値(例えば20~30 mg/L以下)での排水を目指しています。特に食品工場など有機物排水の多い業種では、自主的に10~20 mg/L程度まで処理した上で放流する事例もあります。これは環境への配慮だけでなく、悪臭防止や水辺環境の保全、そして近隣住民との関係構築の面でも望ましいからです。
なお、BODに関連する量としてBOD負荷量という考え方もあります。これは排水量(流量)にBOD濃度を掛け合わせたもので、一日あたり何kgのBODを環境に出しているかを示します。総量規制ではこちらの負荷量ベースで管理し、流域全体のBOD総排出量を抑える取り組みがなされています。排水処理設備の設計や運転管理でも、処理すべきBOD負荷(kg/day)が重要な指標となります。例えば「日量50 m^3の排水にBOD 200 mg/Lが含まれている場合、BOD負荷は10 kg/day」であり、これに対応できる処理施設を設ける必要があるという具合です。
BOD値が高くなる原因と影響
工場や事業場の排水においてBOD値が高くなる原因の多くは、排水中に大量の有機物質が含まれていることです。具体的には食品の残渣や動植物油脂、糖分・デンプン・タンパク質など、生物分解されやすい有機成分が水中に混入するとBODは上昇します。例えば食品加工工場では原料や製品のくず(野菜くず、血液、乳製品の漏れなど)が洗浄水とともに排水に流れ込むことがあります。また、畜産系の排水(牛舎や豚舎からの糞尿の混じった水)も非常に高濃度の有機物を含み、高BODの典型です。さらに、レストランや給食センターの雑排水も調理くずや油分が多く含まれるためBODが高くなりがちです。排水処理設備の能力以上に有機物負荷がかかると、処理後の水でもBODが下がりきらず高くなってしまいます。例えば本来BODを20 mg/L以下に処理できる施設でも、想定の倍以上の汚れ負荷(高濃度の排水や処理量オーバー)があると、処理水のBODが基準を超えてしまう恐れがあります。
また、排水以外にも環境中の水質でBODが高くなるケースとして、生活排水や産業排水が未処理で河川に流入すると河川のBOD値が上昇することが知られています。これは水中に流れ込んだ有機物を分解するため微生物が酸素を消費し、水域全体の溶存酸素量が減少するためです。特に夏場など水温が高い時期は微生物の活動も活発になり酸素消費が大きくなるため、汚濁の影響が顕著に現れます。
BOD値が高いことの影響は二つの面で考えられます。一つは環境への影響、もう一つは法規制上・事業運営上の影響です。
環境への影響としては、高BOD排水がそのまま放流されると受け入れ先の水域で溶存酸素の枯渇を引き起こし、生態系に深刻なダメージを与えます。水中の酸素が不足すると魚やエビなどの好気性の水生生物が生存できなくなり、最悪の場合大量の魚のへい死や水生生物の消失を招きます。さらに酸素が完全になくなると水中で嫌気的な腐敗が進み、硫化水素などの悪臭を発生させ「水が腐った」状態になります。一般に魚類が生息可能なDO(溶存酸素)濃度の下限は約3~5 mg/L程度と言われています。これを下回ると多くの魚は棲めなくなり、水環境としては死んだも同然の状態です。そのため環境基準でも最低ラインとして「DOがなくならない程度」(=BODでいうとE類型10 mg/L以下)が設定されているわけです。言い換えれば、高いBODの水を垂れ流すことは局所的に見ても川や湖を死滅させる行為であり、長期的・広域的に見れば水系全体の生態系バランスを崩し、人間社会にも悪臭や衛生被害をもたらします。
法規制・事業運営上の影響としては、まず排水基準の超過による罰則や操業停止リスクが挙げられます。水質汚濁防止法に基づく排水基準(BOD 160 mg/Lなど)を守れないまま排水すると、行政指導や勧告を受け、改善命令が出されることがあります。悪質な場合や改善命令に従わない場合は罰金刑等もあり得ますし、最終的には事業の継続が困難になる恐れもあります。また、たとえ法的基準内であっても、著しくBODの高い排水を出していると近隣住民からの苦情(臭気や河川の汚染に対する)が発生したり、企業イメージの悪化につながったりする可能性があります。環境意識が高まる現在、排水の適切管理は企業のCSR(企業の社会的責任)やESG評価の観点からも重要です。
さらに、BOD値が高く有機物まみれの排水は、配管や設備にも悪影響を及ぼします。配管内で汚泥やスライムが堆積・腐敗して詰まりや悪臭の原因となったり、既存の排水処理設備に負荷がかかりすぎて故障や処理不良を招いたりします。例えば油分や有機物が多い排水を放置すると、配管内壁に生物膜(バイオフィルム)が厚く形成され、流下能力の低下や閉塞を引き起こします。また処理施設では、活性汚泥法なら汚泥負荷オーバーで微生物のバランスが崩れ**汚泥の膨化(バルキング)**や悪臭の発生を招くかもしれません。こうした内部的なトラブルは、結局は処理コストの増大や維持管理手間の増加につながります。
以上のように、BOD値の高さは環境面・法規制面・設備管理面すべてでマイナスの影響があります。したがって事業者は原因となる有機汚濁の発生を抑制するとともに、発生した有機物を適切に処理してBODを低減する必要があります。
BOD低減技術と処理方法
BODを効果的に低減するには、排水中の有機物を除去または分解する処理が必要です。幸い、有機物汚濁は生物処理を中心に比較的対策技術が確立されており、多くの工場や下水処理場で活用されています。ここでは代表的なBOD低減技術と処理方法を紹介します。
- 一次処理(前処理)による有機物の除去: 排水中の大きなゴミや浮遊物をスクリーンやフィルターでこし取ったり、沈砂・沈殿槽で重い固形物を沈降分離することは、BOD削減の第一ステップです。大きな残渣や泥・砂が除去されるだけでも、それらが後続処理で分解されて消費する酸素量を減らせます。また、食品工場や飲食店の排水ではグリストラップ(油脂分離槽)を設置して油脂類を捕捉することが重要です。油脂は分解しづらく悪臭の原因にもなるため、前処理段階で除去しておけばBOD負荷低減と後工程の負担軽減に繋がります。
- 好気性生物処理(曝気による分解): 活性汚泥法に代表される好気性生物処理は、BOD除去の中核的手法です。これは排水を大きな槽(曝気槽)に入れて空気(酸素)を送り込み、そこに棲みつく微生物(活性汚泥)に有機物を分解させる方法です。微生物たちは有機物を餌に増殖しながら酸素を消費して汚濁成分を二酸化炭素と水に変えていきます。その結果、排水中のBOD(=有機物による酸素要求量)は大幅に減少します。活性汚泥法では適切に管理すれば90%以上のBOD除去率を達成でき、処理水のBODを20 mg/L以下程度にまで下げることも可能です。事実、イギリスで20 mg/Lという排出基準が定められたのも活性汚泥法の性能を踏まえてのことでした。活性汚泥法以外にも、散水ろ床法(生物膜法の一種)や回転円板法などの好気性処理法がありますが、いずれも酸素を供給して微生物による有機物分解を促す点は共通です。好気性処理の利点は比較的短時間で効率よくBODを減らせることですが、その反面副生成物として汚泥(余剰汚泥)が発生するため、定期的な引き抜きと処分が必要です。また、ブロワーなどで空気を送るため動力エネルギーを多く消費します。大規模な処理場では電力コストの半分以上が曝気に費やされるとも言われます。そのため、後述のコスト最適化では省エネ型の曝気方法や高度制御技術の導入が検討されます。
- 嫌気性生物処理(メタン発酵など): 濃度の高い有機排水(BODが数千~数万mg/Lにも達するような廃液)の処理には、嫌気性処理も有効です。嫌気性処理とは酸素を使わない微生物(嫌気性菌)の力で有機物を分解する方法で、代表例がメタン発酵です。嫌気性菌は有機物を分解してメタン(CH_4)や二酸化炭素(CO_2)を生成します。このプロセスでは空気を送り込む必要がなくエネルギー消費が少ないうえ、発生するメタンガスをエネルギー源(バイオガス)として回収できます。例えば食品加工の高濃度排水や酪農の糞尿処理では、大型のUASB(上向流嫌気性汚泥床)リアクターや嫌気性消化槽を用いてメタン発酵処理が行われています。嫌気性処理の欠点は、処理に時間がかかることと、動植物油など一部の物質は分解しきれないこと、そして低温では反応が鈍くなることです。そのため、一般に嫌気性処理だけで直接排水基準に適合させるのは難しく、嫌気性処理でBOD負荷を大幅に減らした後で好気性処理を組み合わせるという手法がとられます。これにより高濃度有機排水でもエネルギーを回収しつつ、最終的な排水を安全なレベルまで浄化できます。
- 凝集沈殿法(薬品による有機物の固形化・除去): 水中の微細な有機物質やコロイド状の汚濁成分を、凝集剤を使って固めて沈める方法もBOD低減に役立ちます。凝集剤(無機系や高分子系の薬剤を使用)を排水に添加すると、ばらばらに溶けていた汚濁粒子が互いにくっついて大きなフロック(塊)を形成し、重力沈降や浮上分離で除去しやすくなります。こうして取り除かれたフロック中に有機物が封じ込められるため、水中に残るBODが減ります。凝集沈殿法は化学的処理の一種で、短時間で効果を発揮する点がメリットです。特に食品加工排水など、固形物や油分が混ざって濁った排水では凝集剤の投加で劇的にBOD・CODが下がることがあります。一方で凝集処理を行うと薬剤に由来する**スラッジ(凝集汚泥)**が発生し、その処分費用がかかるのと、薬剤コストが継続的に必要になる点は注意です。したがって、薬品単価だけでなくトータルの処理費用対効果を見ながら導入を判断する必要があります。
- 高度処理・その他の方法: 上記の生物処理・凝集処理以外にも、排水のBODを下げる高度な手法があります。たとえば活性炭吸着は、細孔の多い活性炭に有機汚濁物質を吸着させて水から除去する方法です。活性炭自体はBODを分解するわけではありませんが、水中の残留する溶解性有機物を吸着除去できるため、生物処理後のトリハロメタン前駆物質や色素成分の除去などに使われます。規模が小さい施設で生物処理が設置困難な場合、活性炭カラムによる処理でBOD対応するケースもあります(ただし活性炭は定期交換が必要)。また、オゾン処理や過酸化水素などの酸化剤を使って有機物を化学的に分解・無毒化する高度酸化処理もあります。これらはコストが高めですが、通常の微生物では分解しにくい難分解性物質や有毒な有機物を処理する際に組み合わせられます。さらに、近年では**膜分離活性汚泥法(MBR)**のように、生物処理と膜ろ過を組み合わせて高品質な処理水を得る技術も普及してきました。MBRでは微細な膜フィルターで微生物と水を分離するため、従来より高濃度の微生物で処理でき、BODやSSを非常に低く抑えることができます。ただ膜の目詰まり対策やエネルギーコストの点で留意が必要です。
以上のように、BOD低減の技術は多岐にわたります。現場ではこれらを組み合わせて多段階で処理することが一般的です。たとえば「スクリーン+沈殿」で前処理をした後「好気性生物処理」、さらに必要に応じて「凝集沈殿」や「活性炭処理」で仕上げる、といった流れです。排水の性質(BODの初期濃度や油分・毒性物質の有無など)によって最適なプロセスは異なりますので、専門家の判断のもと処理フローが設計されます。重要なのは、各工程でのBOD削減効率やコストを把握し、無理なく安定して基準を達成できる処理組み合わせを選ぶことです。適切な処理技術を導入することで、BOD値が高い難処理排水であっても確実に基準内に収めることが可能です。
業界別BOD管理のベストプラクティス
排水中の有機物の種類や濃度は、事業の業種によって大きく異なります。それぞれの業界・業種に適したBOD管理のポイントやベストプラクティスを押さえることが、効果的かつ経済的な排水処理につながります。ここでは主な業界別に、BOD低減のための対策や工夫を紹介します。
食品・飲料製造業
食品加工や飲料製造業では、原料や製品由来の有機物が大量に排水に出るため、BOD対策が特に重要です。例えば、清涼飲料水やビールの工場では糖分や有機酸が排水に含まれ、乳製品工場では乳糖や乳脂肪、食肉加工場では血液や脂肪分が排水に混入します。こうした業種のベストプラクティスとしては:
- 製造工程でのロス削減: まず汚れの発生源対策として、製造ラインからの製品ロスや原料の漏出を極力減らします。例えばこぼれた原料を都度回収する、液体原料の配管を洗浄する前にできるだけ内容物を回収する等で、排水に流れる有機負荷を減らします。
- 固形物の分別回収: 排水に流す前に篩(ふるい)やストレーナーで固形の食品残渣を取り除くことは必須です。これら固形物は飼料化や堆肥化に回すことで廃棄物削減にもつながります。固形物を除去するだけでもBOD負荷のかなりの部分を減らせる場合があります。
- 均等化槽(調整槽)の設置: 食品工場では操業時間帯によって排水の水量・水質が大きく変動します。調整槽で排水を一時ためて均一化し、後段の処理施設に一定負荷で流すことで、生物処理の効率を保ちます。急激な負荷変動は活性汚泥のショックを招きBOD除去率低下につながるため、均等化は重要なベストプラクティスです。
- 高負荷排水の分流と段階処理: 工場内で特に濃い排水(例えばシロップタンクの洗浄廃液など)が出る場合、薄い排水と分けて処理する方が効率的なことがあります。高濃度の部分だけ嫌気性処理でメタン発酵させ、残りを通常の好気処理に回すなど、汚れの濃度に応じた段階処理が有効です。実際、多くの飲料メーカーではUASB反応槽(嫌気)+活性汚泥法(好気)を組み合わせてエネルギー回収と高度処理を両立しています。
- 油脂の管理: 食品工場では油脂分もBODに影響します。揚げ物工程のある工場などでは排水中の油が配管に蓄積しないよう、グリストラップやオイルセパレーターでしっかり分離します。油分は微生物処理でも分解に時間がかかるため、前処理でできるだけ除去するのがコツです。
- 定期的な水質モニタリング: 食品工場は季節商品や生産量の変動で排水負荷が変わることがあります。週単位・月単位でBODやCODを測定し、設備の能力とのバランスをチェックします。傾向を把握することで早めの対策(例えば生物処理槽への栄養塩添加や、負荷ピーク時の一時貯留の検討など)が可能になります。
畜産・酪農業
畜産系の排水(牛・豚・鶏の飼育施設からの排水や、酪農の乳牛舎から出る排水)は、非常に高濃度の有機物と窒素分を含みます。糞尿や敷料、餌の食べ残し、牛乳のしずくなどが混ざり合った排水は、生の状態ではBODが数万mg/Lにも及ぶことがあります。この分野のベストプラクティスは、農業系廃水の特殊性に対応したものになります:
- 固液分離(スラリー分離): 牛や豚の糞尿はまず固形物と液体に分離することが基本です。スクリュープレスやデカンターによって繊維質の固形分(おがくずや糞など)を取り出し、残った液体部分を処理します。固形分は堆肥化することで肥料として再利用できます。分離により液体側のBOD負荷を大幅に下げ、後段の処理負担を軽減します。
- 嫌気性処理による負荷低減: 畜産排水は高濃度なため、嫌気性消化槽を用いてまず有機物をメタン発酵させる手法がよく使われます。大規模酪農では糞尿やミルク成分をメタン発酵させてバイオガスを回収し、残液を次の処理工程へ送ります。バイオガスは発電やボイラー燃料に活用でき、エネルギーの地産地消につながります。
- 低温対策: 酪農が盛んな北海道などでは、冬場の低温で処理効率が落ちることが課題です。ベストプラクティスとして、寒冷地対応の微生物(耐低温性の菌株)を活用したり、処理槽を断熱・加温して温度低下を防いだりする工夫がされています。例えば南極の湖から分離された耐寒性酵母を用いて、真冬でも活発に有機物を分解できるようにした事例があります。株式会社アクトが開発したパーラー排水浄化システムは、そうした低温耐性微生物と特殊担体を組み合わせることで、従来困難とされた「牛乳混じりの排水」を冬季でも浄化可能にした画期的な例です。
- 窒素・リンの除去: 畜産排水はBODだけでなく窒素(アンモニア由来)やリンも高濃度です。環境放流するには脱窒やリン除去も必要になる場合があります。そのため、好気性処理槽を二段階(硝化・脱窒)に分けてアンモニアを窒素ガスに変えるプロセスを組み込んだり、凝集沈殿でリンを化学的に沈殿させたりすることが行われています。
- 臭気対策: 畜産系では排水処理と臭気対策が切り離せません。嫌気性処理槽や汚泥貯留槽からの臭気(硫化水素、アンモニアなど)をバイオフィルターや活性炭で処理したり、消臭剤を散布するなどの対策が講じられます。臭気の発生を抑えることは周辺環境との共生に不可欠であり、結果的に処理プロセスの安定維持にもつながります。
化学工業・医薬品製造業
化学工場や製薬工場では、有機系排水でも成分が多岐にわたります。生物分解しやすい糖分やアルコール類が排出される場合もあれば、難分解性の溶剤や毒性のある有機化合物が含まれるケースもあります。BOD管理において留意すべきベストプラクティスは:
- 有害物質の事前除去・無害化: 生物処理を適用する前に、生物に毒性のある成分を減らすことが重要です。例えば重金属や殺菌成分、極端なpHの排水は、そのままでは微生物が働けません。中和によるpH調整や、キレート剤・沈殿剤での重金属除去、揮発性有機溶剤のストリッピング除去など、前処理段階で生物に優しい状態に持っていきます。
- 段階的な微生物順応(アクラメーション): 難分解性の有機物でも、時間をかけて微生物を順応(アクラメーション)させれば徐々に分解できるようになる場合があります。そこで、いきなり本格処理槽に流すのではなく、培養槽で処理水や汚泥を使って試験分解し、分解可能な菌を増やしてから本処理に臨むことがあります。これによりショックなく処理を開始でき、安定したBOD除去が期待できます。
- 高度処理の併用: 化学工場ではCODとBODの差(すなわち難分解性有機物の存在)が大きいケースがあります。生物処理では下がりきらない残留CODに対して、オゾン酸化や活性炭吸着を併用することがベストプラクティスとなる場合があります。特に着色や微量有害成分の除去は、生物処理後にこれら高度処理を入れることで放流水質をクリアできます。
- インラインモニタリング: 化学系排水は原材料の切り替えやスケール掃除等で水質変動が起きやすいため、オンラインで水質を監視する仕組みが有効です。TOC計やCOD計などを用いて、リアルタイムに汚れ濃度を監視し、異常時にはタンクに一時隔離するといった制御をすることで、負荷ショックを緩和します。生産計画と連動して排水の負荷を予測し、あらかじめ処理設備の運転を調整するのも高度な取り組みです。
その他の業種
上記以外にも様々な業種でBOD管理は必要です。例えば製紙業では木材由来の有機物(リグニンなど)やパルプの繊維が排水に含まれるため、沈殿による繊維回収と、生物処理+凝集処理の組み合わせがとられています。**繊維工場(染色工程)**では色素やデンプン糊料などが混じり、生物処理では色が抜けないことからオゾン処理で色度を下げつつBODも補助的に減らすといった対策が行われます。電子部品工場などでは有機物汚染は少ないですが、万一有機洗浄剤などが流出すると下水処理場に負荷を与えるので、活性炭塔で吸着するなどの予防策をとっている場合があります。
このように業界ごとの排水特性に応じて適切な処理法を採用することがベストプラクティスの基本です。また、どの業種でも共通するのは「汚染の発生抑制」「適切な前処理」「安定した主処理」「定期的な監視とメンテナンス」というサイクルをきちんと回すことです。BOD管理は一度設備を入れれば終わりではなく、日々の運転・管理によって初めて効果が維持されます。各業界の成功事例を参考に、自社の排水特性にマッチした対策を講じることが重要です。
BOD処理のコスト最適化戦略
排水のBOD処理にはコストが伴いますが、設備投資費・運転費用・薬品費・人件費など多方面にわたります。コスト最適化とは、必要な水質基準を満たしつつ、これらの費用を可能な限り抑えるための戦略です。以下に、BOD処理でコストを最適化するためのポイントをいくつか紹介します。
1. 汚濁負荷そのものの削減: 最も基本的かつ効果的なコスト削減策は、「処理しなければならない汚れ(有機物)を減らす」ことです。これは製造プロセスの改善や原材料ロスの削減、設備からの漏洩防止などによって達成できます。例えば製品ロスを1日あたり100 kg減らせれば、その分BOD負荷(例えばBOD換算で数十kg)は発生しなくなるので、処理に使うエネルギーや薬品も減ります。また、可能な場合は汚濁の濃い部分を濃縮回収して再利用する手もあります。糖分を含む排水を蒸発濃縮して飼料化する、おからや生乳廃液を別ラインで集めて豚の飼料に転用する、などは排水負荷と処理費の両方を減らす取り組みです。
2. エネルギーコストの低減: 排水処理では、好気性処理の曝気やポンプ送水などで電力を多く消費します。そこで、省エネルギー型の設備や運用に切り替えることでコスト削減が可能です。具体的には、高効率ブロワーやインバーター制御の導入、溶存酸素センサー連動の曝気量制御によって過剰なエア供給を防ぐ、といった方法があります。近年は処理槽内の酸素濃度や有機物負荷をリアルタイムに監視して、必要最小限の曝気で済むよう自動制御するシステムも実用化されています。また、前段で触れた嫌気性処理を取り入れ、発生するメタンガスで発電・熱利用することで、処理設備全体のエネルギー自給率を高める試みもあります。例えばUASBリアクターを導入して、生成バイオガスでブロワー電力の一部を賄えば、エネルギーコストとCO2排出の両方を削減できます。
3. 薬品コストの最適化: 凝集剤や中和剤、消泡剤など排水処理には様々な薬品が使われます。これらの薬品費も積み重なると無視できません。コスト最適化のためには、薬品の適切な選定と投加量の最適制御が重要です。一例として、凝集剤については最適処理条件(pHや濁度)をキープすることで必要量を減らすことができます。pHが高すぎる場合は中和してから凝集剤を入れる、廃液温度を上げると反応効率が上がる場合は熱交換で温度調整する、といった工夫で薬品の働きを最大化し、投入量を低減します。また、近年では多機能型の凝集剤が開発されており、一種類でpH調整・凝集・脱色など複数の効果を発揮するものもあります。株式会社アクトの開発した無機系凝集剤『水夢(Suimu)』は、従来薬剤よりトータルコストを50~70%削減できた例もあります。単に安価な薬剤を選ぶのではなく、処理後のスラッジ量削減や作業効率まで含めた総合的なコスト評価で最適な薬剤を選択することが大切です。
4. スケールメリットと設備共有: 排水処理のコストは規模に依存する部分もあります。小規模事業所であっても、近隣の事業所と協力して共同の排水処理施設を利用することで、一社あたりの負担を減らせる場合があります。また、工場内でも異なる生産ラインの排水を一本化して処理場でまとめて処理すれば、設備を二重に設ける必要がなくなります。ただし、混合によって処理が難しくなるケース(例えば無機系排水と有機系排水の混合など)もあるため、事前の調査と合意形成が必要です。自治体によっては地域の中小事業者向けに共同排水処理場を整備している場合もあるので、利用可能なら検討すると良いでしょう。
5. メンテナンスと予防保全: 処理設備を計画通りに稼働させ続けるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。機器の故障や配管詰まり、微生物の機能低下などは早期に対処すれば大事に至りませんが、放置すると処理不良による基準超過や修理費の発生といったコスト増に直結します。予防保全の考え方で、ブロワーやポンプの点検整備、膜や活性炭の交換スケジュール管理、活性汚泥の状態チェック(顕微鏡観察や沈降率測定)などを継続的に実施しましょう。トラブルを未然に防ぎ、常に最適な運転状態を維持することが、結果的に余分な薬品投入ややり直し処理を減らし、コストの無駄を省きます。
6. 補助金や制度の活用: 環境改善や省エネに資する設備導入には、行政の補助金・助成金制度が使える場合があります。排水処理分野でも、高効率機器の導入や汚泥の減量化設備、バイオガス化設備の導入などに対して補助が出ることがあります。最新の公的支援策を調べ、条件に合うものがあれば活用することで初期投資の負担を軽減できます。また、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)を利用して、排水由来のバイオガス発電で収益を上げ、その収入で処理コストを相殺する試みもなされています。
以上、BOD処理のコスト最適化に関する代表的な戦略を述べました。ポイントは、「汚れを減らし・エネルギーを節約し・薬品を減らし・トラブルを未然に防ぐ」という一連のアプローチです。これらを総合的に実施することで、法規制を確実に守りつつ経済的な運転が可能となります。自社の排水特性や規模に応じて、最適な組み合わせを検討すると良いでしょう。
アクトのBOD改善実績と効果事例
水処理専門企業の株式会社アクトは、様々な業界の排水課題に対して独自の技術と製品でソリューションを提供してきました。BODの改善においても数多くの実績があり、高い技術力が評価されています。ここではアクトのBOD改善事例と、その特徴的な技術についてご紹介します。
1. 高難度排水への挑戦と成功例: 活性汚泥法では処理が難しい高濃度の乳汚水に対し、アクトの凝集剤「水夢(SUIMU)」は凝集処理を可能にしました。さらに、凝集処理によって発生する処理後の水は石鹸へのリサイクルが可能で、不要な排水を作らずBODの低減を実現させました。
2. 凝集剤『水夢(Suimu)』によるBOD改善: アクトの主力製品である無機系凝集剤『水夢(Suimu)』シリーズは、従来の凝集剤では処理が難しい重金属含有廃水や水性塗料廃液、放射性汚染水に至るまで幅広く対応できる点が特長です。水夢は単なる薬剤提供に留まらず、顧客の排水に合ったカスタマイズ調合も可能なため、それぞれの現場で最適な性能を発揮します。例えばある金属加工工場の研磨廃液において、水夢の品番「CO-5022MG」を用いたところ、活性炭成分が含まれていることも功を奏し色素の低減とBOD/CODの大幅削減を同時に達成しました。別の事例では、生活雑排水や家畜糞尿が混じる難処理水に対し「NSP-2035」という品番を投入し、汚濁成分を見事に凝集分離してBODを下げています(この製品は福島の放射能汚染ため池の浄化にも採用され、効果を挙げました)。水夢シリーズの導入効果として、処理コストをトータルで50~70%削減したケースも報告されています。これは単に薬剤価格が安いというだけでなく、処理後の汚泥発生量が減って廃棄費用が削減されたり、処理時間が短縮して人件費が抑えられたりした総合的な効果です。加えて、水夢は環境省や農水省の認定実績を持ち、2011年の福島第一原発事故後には汚染水処理にも貢献した経緯があり、公的機関からの信頼も高い製品です。BOD削減のみならず環境リスク対応まで視野に入れたソリューションとして、アクトの凝集技術は他社と一線を画しています。
3. コンパクトな処理装置『ACT-200』の提供: アクトは薬剤だけでなく凝集処理に必要なろ過資材や機械も販売しており、小型凝集分離ろ過装置『ACT-200』という製品も展開しています。「ACT-200」では凝集剤とセットで用いることで1バッチあたり200L程度の排水処理を手軽に実施できます。中小規模の工場や実験施設など、大掛かりな処理場を持たない現場でも、ACT-200を導入すれば少量の高BOD排水をその場で浄化し放流できるようになります。例えば研究所から出る試作段階の排水や、イベント会場など一時的に発生する排水の処理に威力を発揮しています。
4. 現場密着のコンサルティングとカスタマイズ: アクトのもう一つの特徴は、現場主義のコンサルティングです。「既存の凝集剤では効果が不十分」「活性汚泥処理で処理水のBODが下げ止まって困っている」といった相談に対し、原因を突き止めて薬剤の組成を微調整したり、新たな工程を追加提案したりして問題を解決に導きます。実際、「従来の凝集剤では処理が難しくなってきた」という企業に対し、その排水特性に合わせた試作薬剤を迅速に作り上げ、当初の半分の投薬量で所定の処理を可能にした例もあります。このように顧客ごとにカスタマイズしたアプローチをとることで、結果としてBOD処理のコスト削減や安定運転に繋げているのです。「困っているお客様に対し解決手段と成果をもたらす」という熱意がアクト社内に根付いており、それが技術開発の原動力にもなっています。
効果事例のまとめ
アクトの手掛けたBOD改善の効果事例を総括すると、「通常では難しい排水を処理可能にし、法規制クリアはもちろんコスト低減や付加価値創出まで実現した」点が際立ちます。例えば、ある事例ではグリストラップに特殊処理を施すことで、BODを約69 mg/Lから12 mg/Lまで低減し、油分についても検出限界以下にまで削減する成果を上げました。これは飲食店の雑排水処理での一例ですが、従来は高止まりしていたBOD値が劇的に改善され、無事に排水基準をクリアしたとのことです。
アクトはお客様の排水処理それぞれに親身に向き合い、単なる凝集剤メーカーの枠を超え、水処理分野の課題解決パートナーとして高い評価を得ています。BODの問題でお困りの事業者にとって、アクトの豊富な実績と高度なソリューションは強い味方と言えるでしょう。
まとめ:BOD(生物化学的酸素要求量)は水中の有機汚濁を表す重要な指標であり、工場・事業所の排水管理では基準遵守と環境保全のために的確な対策が求められます。本記事ではBODの基本から測定方法、法規制、原因・影響、低減技術、業界別対策、コスト最適化、そしてアクトの事例まで包括的に解説しました。適切なBOD管理によって排水トラブルを防ぎ、法令順守とコスト削減の両立を図ることが可能です。水処理のプロである株式会社アクトの知見も参考に、ぜひ貴社の排水管理にお役立てください。
併せて、BODと並ぶ指標であるCODや窒素・リンの管理も忘れずに行い、総合的な水質管理に取り組みましょう。環境に優しく経済的な排水処理は、これからの持続可能な事業運営に欠かせない要素です。今回の内容がその一助となれば幸いです。

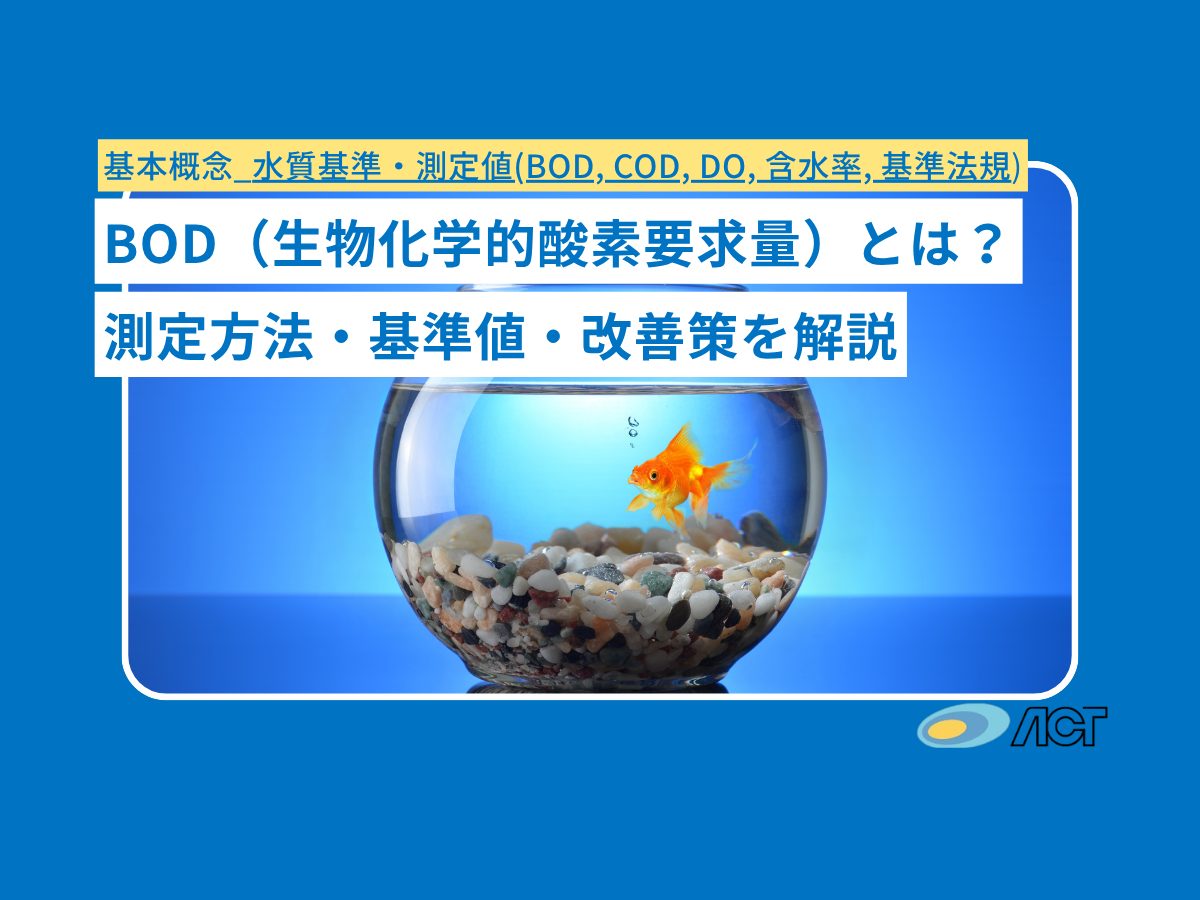





_安定稼働-300x225.jpg)
_四角-300x225.jpg)
_カーボン-300x225.jpg)
_BCP-300x225.jpg)
_DX-300x225.jpg)
_PFAS-300x225.jpg)