工場や事業所から排出される産業排水では、酸性・アルカリ性への中和処理が欠かせません。排水のpH(酸性度・アルカリ度)を適切に調整せず強酸性・強アルカリ性のまま流せば、環境への悪影響や法規制違反につながります。日本では公共用水域へ排水を放流する際、通常pH5.8~8.6(海域では5.0~9.0)の範囲に保つことが求められており、この基準を逸脱する排水はそのまま捨ててはいけません。また多くの水生生物にとってもpH6~9程度が生息に望ましい範囲であり、極端な酸性・アルカリ性水は生態系へ深刻な影響を及ぼします。そのため、排水を中和処理して適切なpHに整えることは環境保全と法令遵守の両面で不可欠なプロセスです。
さらにpH調整(中和処理)は排水処理プロセス全体の効果を左右する重要工程でもあります。たとえば凝集沈殿処理では水のpHによって凝集剤の働きが変わりますし、有害金属を除去する場合もpHをある特定の値に調整することで水酸化物の形で沈殿させやすくなります。実際、クロムなど重金属を含むメッキ排水の処理では、まず硫酸などでpH2~3の強酸性に下げて六価クロムを三価に還元し、その後苛性ソーダでpH7.5~10程度のアルカリ性に上げて水酸化クロムを沈殿させるといった二段階のpH制御が行われています。このように排水基準のクリアだけでなく後続処理の効率化のためにも、適切な中和処理によるpH制御が重要となります。
中和処理の基本原理|酸・アルカリ反応とpH制御の仕組み
中和処理の基本は、酸とアルカリの化学反応によって水と塩(えん)を生成するというシンプルな原理です。酸性に偏った水溶液にはアルカリ剤を、アルカリ性に偏った水溶液には酸剤を加えることで、それぞれの過剰な性質を打ち消しあい、溶液のpHを中性付近(pH7前後)に近づけます。この反応過程で溶液の酸性・アルカリ性が互いに打ち消され、pHが中性へと近づくのが中和反応です。
実際の排水では純粋な水溶液だけでなく様々な成分を含むため、理想通りに中性ジャストへ仕上げるのは容易ではありません。酸やアルカリを入れすぎると「行き過ぎ」て反対側に振れてしまう(過剰中和)ことがしばしば起こります。例えば酸性排水に苛性ソーダを加えすぎてpHが8を超えアルカリ性に振り切れてしまう、といったケースです。この場合また酸を足して下げねばならず手間も薬品も二重にかかってしまいます。中和処理ではこのようなオーバーシュートを防ぐために少しずつ段階的に薬品を加えて様子を見ながら調整することが鉄則です。後述する自動pH制御装置の活用も有効でしょう。さらに、排水中に重金属イオンが含まれる場合は中和に伴い金属水酸化物の沈殿物が生じます。これは重金属除去には有利ですが、一方で生成する汚泥(スラッジ)の処理・処分コストがかかる要因にもなります。こうした中和に伴う副産物にも留意しつつ、適切な方法でpHをコントロールすることが求められます。
中和剤の種類と選定|苛性ソーダ・消石灰・炭酸ナトリウムの特徴比較
排水のpH調整に用いる中和剤(pH調整剤)には、大きく分けて酸性薬剤とアルカリ性薬剤があります。それぞれ、中和したい対象(排水)がアルカリ性か酸性かによって使い分けます。アルカリ性の排水(pHが高い場合)には酸性の中和剤を、酸性の排水(pHが低い場合)にはアルカリ性の中和剤を加えて、中性域に近づけるのが基本です。本節では、代表的な酸剤およびアルカリ剤の種類と特徴について、メリット・デメリットを比較しながら解説します。
酸性中和剤(アルカリ性排水を処理する薬剤)
アルカリ性の排水を中和するための酸としては、硫酸(H₂SO₄)や塩酸(HCl)といった鉱酸が最も一般的です。硫酸は工業的に安価で入手しやすく、中和反応も速やかに進行するため大量のアルカリ廃水に対して経済的に処理できる利点があります。また揮発しにくいため酸ミストの発生も比較的小さいなど、取り扱いやすい酸でもあります。一方で強酸ゆえに腐食性・危険性が高く、劇物指定された薬品(毒物及び劇物取締法の規制対象)であるため取り扱いには資格が必要です。もう一つ硫酸使用上の注意点は、排水中に高濃度のカルシウムが含まれる場合です。硫酸をカルシウム分を多く含む水に加えると難溶性の硫酸カルシウム(石膏)が析出しやすく、スラリー状の沈殿が発生したり設備内に付着・スケール化する恐れがあります。石膏スケールは中和槽や配管の詰まり・容量低下を招き、ポンプ故障の原因にもなるため硬度成分が高い排水には硫酸を避けるか塩酸など別の酸を検討することが推奨されます。
塩酸(HCl)は強酸ですが、中和剤として使われる頻度は硫酸ほど高くありません。その理由の一つは価格が比較的高いこと、さらに濃塩酸は発煙性があって揮発しやすく刺激臭の塩化水素ガスが発生しやすいことです。取り扱いや保管の際も腐食性の塩化水素ガス対策が必要になるため、硫酸に比べ手間がかかります。しかし塩酸には硫酸と異なり石膏(硫酸カルシウム)析出を起こさない利点があります。水中にカルシウム等の硬度成分が多い場合でもスケール障害を避けられるため、高硬度の排水では硫酸の代わりに塩酸を選ぶケースもあります(ただし塩酸を加えると塩化物イオンが排水中に増える点には留意が必要です)。
このほか状況に応じて酢酸(CH₃COOH)やクエン酸といった有機酸が選ばれる場合もあります。有機酸は鉱酸ほど酸性が強くないため、中和時のpH変化が緩やかで過剰投入による急激なpH低下を起こしにくい特徴があります。また酢酸やクエン酸は低濃度であれば劇物に指定されないため、保管や扱いの法規制面でメリットがあります(※高濃度では腐食性が強いため注意)。食品関連など塩類を排水中に残したくない現場で、有機酸が中和剤に使われるケースもあります。もっとも酢酸類は価格が高めで刺激臭もあるため、大量中和にはあまり向かず必要最小限の微調整用途が中心です。
なお、近年ではアルカリ排水に対し二酸化炭素ガス(CO₂)による中和を行う方法も広く実績があります。CO₂は水中で炭酸(H₂CO₃)を生じる弱酸で、強酸に比べてpHを急激に下げにくく、適量を投入すれば目標pHで自動的に平衡に達するため過剰注入しづらく制御が容易です。またガス体なので薬品の運搬・保管の安全性が高く、反応生成物も炭酸塩となり環境負荷が低い利点があります。一方で、専用のガス注入設備やボンベ管理が必要になること、強酸に比べ中和速度が遅い(処理水量やpH変動幅によっては大型設備が必要)点には注意が必要です。もっとも近年はpH計によるフィードバック制御と組み合わせて精密にガス注入量を調節し、効率よくCO₂中和するシステムも実用化されています
アルカリ性中和剤(酸性排水を処理する薬剤)
酸性の排水を中和するアルカリ剤としては、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)、水酸化カルシウム(消石灰)、炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)の3つが代表的です。それぞれ特性が異なり、排水の種類や処理規模に応じて適材適所で使い分けられます。以下に主要なアルカリ剤のメリット・デメリットを比較してまとめます。
- 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ, NaOH):最も一般的かつ強力なアルカリ性中和剤です。工業用途では50%濃度ほどの液体苛性ソーダが広く流通しており扱いやすく、反応も瞬時で確実にpHを上昇させられるため、小規模施設から大規模処理場まで幅広く採用されています。ただしその反応の激しさゆえに投入量を誤ると一気にpHが上がり過ぎる(オーバーシュート)リスクがあり、手動で加薬する際は慎重な調整が必要です。また苛性ソーダ自体の単価は他のアルカリ剤より高価で、強腐食性の劇物指定物質でもあるため取り扱いには保護具と有資格者が必要です。固体(フレーク状・ビーズ状)の苛性ソーダも市販されていますが、その場合は事前に水に溶かす手間がかかります。総合的には即効性と制御のしやすさから多くの現場で使われる定番中和剤ですが、扱いやすさと安全性のバランスを考慮し投入・管理することが重要です。
- 水酸化カルシウム(消石灰, Ca(OH)₂):消石灰は石灰石を焼成・消化して得られる白色粉末で、単位コストが非常に低い安価なアルカリ剤です。苛性ソーダほど強力・瞬時にpHを上げる力はなく反応は穏やかでゆっくりですが、その分薬剤コストを抑えつつ大量の酸性排水を処理したい場合に適しています。通常、消石灰は水への溶解度が低いため水に懸濁させたスラリー状にして排水に投入します。未溶解の粒子が残るのでポンプや配管に固形物が詰まらないよう十分な撹拌や太めの配管径を確保するなど設備設計上の配慮が必要です。また中和反応の生成物として炭酸カルシウム(CaCO₃)などの沈殿を生じやすく、多量に使用すると処理後に石灰スラッジ(汚泥)が大量発生します。これは脱水・処分のコスト増要因となりますが、一方で石灰は重金属の水酸化物を生成・共沈させる効果が高いため、メッキ廃水など金属含有酸性排水の処理で古くから多用されてきました(生成した金属水酸化物が石灰の微粒子に付着して沈みやすくなる共沈作用も期待できます)。総じて、消石灰は反応後の汚泥処理負担こそ大きいものの薬剤費が安価で重金属同時除去に有利な点から、多量の酸性排水を扱う業界で広く使われています。
- 炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ, Na₂CO₃):重曹に近い性質を持つ弱アルカリ剤です。苛性ソーダのような強塩基ではないため、水溶液のpHは最大でもおおよそ11程度に留まり、酸性排水に対してゆるやかにpHを引き上げる用途に適します。強アルカリ剤ほど過激に中和が進まないため、過剰投入しても極端な高pHになりにくい安全側の特徴があります。粉末固体のまま袋詰めで保存・投入できる扱いやすさもあり、工場排水では実験系廃液の微調整や、苛性ソーダのような劇物を使いたくない現場で代替採用されるケースがあります。ただし炭酸ナトリウムは中和反応後に水中で炭酸イオンCO₃^2-や重炭酸イオンHCO₃-を生じ、酸を中和するときに炭酸ガスの発生や炭酸塩の析出につながることがあります。生成する炭酸塩(CaCO₃など)は石灰使用時と同様スケーリングや汚泥の原因となるので、量が多い場合の使用には注意が必要です。炭酸ナトリウム自体の価格は比較的安価ですが、中和力が弱いため大量の強酸を処理するには不向きで、あくまで弱酸性排水や微調整向けの中和剤と言えるでしょう。
上記以外にも、水酸化カリウム(苛性カリ)や炭酸水素ナトリウム(重曹)、アンモニア水などが状況により中和剤として使われることがあります。例えば一部の化学工場では酸性廃液に対し、副産物のアンモニア水を中和剤として再利用する例もあります(その場合排水中に窒素分が残留するため窒素排出規制への配慮が必要です)。このように各中和剤の特徴を正しく理解し、処理したい排水の性質(酸・アルカリの種類・濃度、含有物質、処理後の要求水質など)に合った薬剤を選定することが大切です。コスト最優先なら安価な薬剤に軍配が上がりますが、排水の組成によってはそれではトラブルが出る場合もあるため、安全面・環境面も考慮して総合的に判断しましょう。
業界別中和処理システム|金属表面処理・化学・電子工業での最適化事例
一口に中和処理と言っても、排水の性質や処理目標は業界ごと・現場ごとに異なります。ここでは業種別によくある中和処理システムの工夫や最適化事例を紹介します。自社の排水条件に近いケースがあれば、ぜひ参考にしてください。
金属表面処理(メッキ・表面仕上げ)業界: メッキ工場など表面処理業では、酸性のメッキ液や酸洗液を使用する工程が多く、排出される廃液は強酸性かつ重金属イオンを含む場合があります。これらを処理するには、上述の消石灰や苛性ソーダによる中和+重金属の水酸化物沈殿処理が古くから用いられてきました。石灰は安価で重金属を効果的に沈殿・共沈させられるため、大量の酸性排水を扱うメッキ工場で伝統的によく使われています。例えば、あるメッキ工場ではクロム酸を含む酸性排水をまず石灰乳でpH9程度まで中和し、クロムや他の金属を水酸化物スラッジとして沈殿・ろ過除去するプロセスを採用しています。石灰を選ぶ理由は薬剤コストの安さと重金属除去効率の高さですが、一方で汚泥処理量が多くなる欠点があります。近年では、生成するスラッジ量削減のため凝集剤を併用して必要最低限の石灰投与量に抑えたり、逆に硫酸イオンが多く石膏スケールが懸念される場合は石灰の代わりに苛性ソーダを使うなど、排水特性に応じた工夫がなされています。金属表面処理業ではこのように薬剤コストと処理後の副産物量のバランスを見極め、中和プロセスを最適化しているのが特徴です。
化学工業: 化学工場では排水の性質が施設ごとに千差万別ですが、酸性廃液とアルカリ性廃液が両方発生するケースが少なくありません。そのため工場内で酸性とアルカリ性の排水を分けて処理せず適切に混合してお互いを中和させ、追加の薬品使用量を減らす工夫も見られます。例えば工程内でアルカリ洗浄液が出る現場では、それを他の酸性排水と内部中和させて酸・アルカリ両方の薬剤投入を削減するといった方法です(ただし完全に中和されない成分の除去には別途凝集剤添加などが必要で、排水全体を見据えたバランス設計が不可欠です)。また、化学工場ではボイラーや炉の燃焼排ガスからCO₂が出る場合、それを回収再利用してアルカリ排水の中和剤に使うといった先進事例もあります。実際、ボイラー排水などアルカリ度が高いが量は限られるケースで排ガス中のCO₂を導入して薬品を一切使わずに中和処理し、年間数百万円の薬剤費を削減した事例も報告されています。化学工業ではこのように自社プロセスから出る副産物を有効活用したり、大型設備で高度な中和制御を行うことで、コスト削減と安定処理の両立を図っています。
電子・半導体関連工業: 電子部品や半導体製造の現場では、フォトエッチングや洗浄工程で酸・アルカリ薬品を大量に使う一方、高純度水のリサイクルや処理時間の短縮など独自の要求があります。たとえば処理タクト短縮のニーズが高いケースでは、従来の手法にとらわれず高速処理装置の導入が効果を上げています。電子関連では生産プロセスとシンクロした排水処理が重要であり、自動化システムや高速リアクターの活用でpH調整工程のボトルネックを解消する取り組みが進んでいます。また電子産業では排水中に塩分などを極力残したくない場合もあり、前述の有機酸による中和(例:酢酸やクエン酸を用いて中和し、副生成する塩類を低減)が採用されるケースもあります。総じて電子工業では高精度かつ効率的な中和処理が求められるため、先端技術を取り入れた制御装置や薬剤の選択によって処理最適化が図られているのが特徴です。
pH制御の自動化|センサー・制御システム・薬剤注入の最適化
近年、多くの排水処理施設でpH制御の自動化が進んでいます。自動pH制御システムでは、まず排水のpHをリアルタイムで監視するpHセンサー(電極)を中和槽や配管内に設置し、その計測信号をもとに制御装置(調節計やPLC)が中和剤の注入量を自動調節します。具体的には、設定した目標pHになるよう酸またはアルカリ薬剤の薬注ポンプや調節弁を制御し、薬剤を連続的・断続的に添加します。例えばある連続式中和装置では、pH計と連動して原水に対し自動的に硫酸を滴下することで所定のpHに中和を行っています。このようにセンサー計測値に基づくフィードバック制御によって、中和操作を人手に頼らず正確に行えるのが利点です。人がバルブを開閉して調整する場合と比べ、自動制御ならわずかなズレを常時微調整できるため、過剰中和による薬品の無駄遣いや基準逸脱を防ぐ効果も期待できます。
自動pH制御システムを安定稼働させるポイントとしては、まず信頼性の高いpH測定が前提となります。pH電極が汚れていたり校正不良だと正しい値を示さず、実際はpHが9を超えているのに表示計は7のまま、といった恐ろしい事態にもなりかねません。その結果、知らずに規制値を超えた排水を流出させてしまい行政から是正指導を受けるケースも報告されています。したがってセンサーについては定期的な洗浄・点検とキャリブレーション(校正)を欠かさず行い、少しでも測定値にズレを感じたら電極交換を検討するぐらいの慎重さが必要です。最近ではpH電極の自動洗浄機構や異常診断機能を備えた計測システムも登場し、メンテナンス負荷を減らせるようになってきました。
制御面では、対象とする排水の性質に応じて最適な制御方式を選ぶことが重要です。処理量が少ない場合はシンプルな中和槽方式で問題ありませんが、大流量を迅速に処理したい場合は配管内で中和を完結させるインライン方式が有利なケースもあります(インライン方式は中和槽や撹拌機が不要で装置をコンパクトにでき、短時間で処理可能といったメリットがあります)。また制御アルゴリズムも、単純なオンオフ制御から比例・積分・微分を組み合わせたPID制御まで様々です。pHは中和点近傍で急激に変化しやすい非線形特性があるため、外乱が少なく安定した制御を行うには熟練が必要ですが、適切に調整されたPID制御装置であれば目標pHを中心に安定した加薬が可能です。さらに最近ではIoTやAI技術の活用も進んでおり、薬品タンクの残量を遠隔モニタリングしたり、過去の処理データからAIが薬注量を最適化する試みも行われています。一時的なシステム投資は必要ですが、中長期的に見れば薬剤消費削減や人件費削減によって十分回収可能な場合も多いでしょう。
自動化により便利になったとはいえ、システム任せに油断するのは禁物です。定期的な保守点検で性能を維持し、常に無駄のない薬剤投入が行われるようにしましょう。実際、ある現場ではメンテナンス不足で中和装置が不調なまま運転を続けた結果、二酸化炭素が必要以上に消費されコスト増となった例も報告されています。自動装置こそ定期点検とデータ確認が重要であり、「任せきり」にせず人による監視とフォローを組み合わせることで、最も安定したpH制御と薬剤コスト最適化が実現できます。
中和処理のトラブル対策|pH変動・沈殿物生成・腐食対策
中和処理の現場では、思わぬトラブルに見舞われることがあります。ここでは典型的なトラブル例と、その対応策・予防策について解説します。
- pHオーバーシュート(過剰中和): 前述のとおり、酸・アルカリを加えすぎて目標pHを行き過ぎてしまう現象です。手動中和ではヒューマンエラーにより起こりがちで、行き過ぎた場合は逆の薬剤を少量ずつ加えて戻すしかありません。しかし根本的には予防が肝心です。予防策として、先述のように段階的な少量加薬で慎重に調整すること、そして自動pH制御装置の導入が挙げられます。自動制御なら設定値付近で微調整してくれるため、行き過ぎを大幅に減らせます。手動で行う場合でも、強アルカリの代わりに炭酸ソーダのような弱めの薬剤を使うと過剰中和になりにくく安全です。現場の状況に応じて、これらの対策でオーバーシュートを防止しましょう。
- 沈殿物・スケールの発生: 中和反応に伴って水に溶けない生成物が析出し、槽内や配管に付着・詰まりを起こすトラブルもよく見られます。代表例は石灰中和で生じるカルシウムの析出物(炭酸カルシウムや石膏)で、これが槽内に堆積すると有効容量の減少や撹拌不良を招きます。配管内にスケール付着すると流量低下やセンサー誤作動の原因にもなります。対応策として、定期的な設備洗浄や堆積物の除去が欠かせません。また予防策としてキレート剤やリン酸塩などのスケール抑制剤を少量添加して析出を抑える方法もありますが、これは排水処理目的によっては添加物を入れられない場合もあります。根本的な対策は薬品選択の見直しです。例えば石灰中和で石膏スケールが問題なら、塩酸に切り替えて石膏生成を避ける、あるいはCO₂中和にして固形生成物を残さないようにする、といったアプローチが有効ですこのように排水成分に応じて最適な薬剤に変更することで、副産物トラブルを減らせます。
- 設備の腐食・劣化: 強酸や強アルカリを扱う中和設備では、タンクや配管、ポンプなどが腐食によって損傷・劣化するリスクがあります。硫酸・塩酸などはステンレスすら腐食させる場合があるため、酸剤タンクはFRPや塩ビ、ポリプロピレンといった耐食性材料で作られるのが一般的です。またアルカリ剤の苛性ソーダもアルミニウムなど一部金属を侵すため、ポンプや配管材質の選定には注意が必要です。腐食対策としては、材質面の工夫に加え定期点検での早期発見が重要です。タンクや配管の異常な薄肉化・錆の発生を見つけたら早めに補修・交換し、大量漏えいなどの重大事故を防ぎます。さらに、塩酸使用時に発生する塩化水素ガスは周囲の金属機器も腐食させるため、中和設備の設置場所は換気や排ガス処理(スクラバー等)を適切に行いましょう。
- 処理水の基準逸脱: 中和処理後の排水が規制pH範囲から外れて放流されてしまうトラブルも重大です。これは上述の過剰中和の結果だったり、薬品不足で十分中和できなかった場合などに起こります。特に自動運転に任せきりでセンサーや装置の不調を見落とすと、本当はpHが基準外なのに気付かず流出…ということにもなりかねません。繰り返しになりますが、計器の定期点検と校正を確実に行い、運転データを日誌などに記録・チェックして異常を早期に発見することが肝要です。万が一基準逸脱が発覚した際は、原因を調査するとともに装置メーカーや専門業者に相談して再発防止策を講じましょう。
以上のようなトラブル対応策を踏まえ、日頃から「最悪のケース」を想定したリスク管理が大切です。人の誤操作に対して自動制御でカバーする、人の目が届かない部分はセンサー異常時のアラームや自動停止機能を付ける、といった多重の安全策を講じ、万全の体制で中和処理システムを運用してください。
アクトの中和処理最適化実績|安定制御と薬剤コスト削減の成功事例
株式会社アクトは環境分野の専門企業として、数多くの中和処理プロセスの最適化に取り組んできました。その中から、pH安定制御の改善と薬剤コスト削減に成功した事例をいくつかご紹介します。
ケース1: 最適薬剤の導入によるコストと安全性の両立(建設現場のセメント廃水処理) – 建設工事現場で大量に発生するセメント系アルカリ排水の中和処理では、従来は希硫酸などの鉱酸を用いるのが一般的でした。しかしある現場では、劇物の酸を大量に保管・取扱いすることに作業上のリスクとコスト増(有資格者の配置や安全設備の必要など)を抱えていました。そこでアクトは、自社開発のアルカリ中和剤「融夢」(ゆうむ)の活用を提案。融夢はクエン酸など食品添加物由来の強酸性液体で、肌や衣服を溶かすほどの危険がなく取り扱いに資格も不要な安全設計の中和剤です。実際に融夢を導入したところ、pH12前後の強アルカリ排水が数分で中和完了し、添加量も硫酸使用時より少量で済んだため薬剤コストも削減できました。何より劇物を扱わずに済む安心感から作業者の負担が軽減し、現場で高い評価を得ました。融夢はpH1程度の強酸性を維持しつつ毒物劇物に非該当の成分で構成されており、強酸の機能性と安全性を両立した中和剤と言えます。腐食性も塩酸や硫酸より低いため、設備材質へのダメージを抑えられる点もメリットです。
ケース2: 新技術の導入で薬剤費ゼロへ(塗料廃液処理プラント) – 別の塗装工場では、排水中の有機溶剤や塗料成分を処理する際に大量の石灰と凝集剤を使っており、pH調整と汚泥処理に多額のコストがかかっていました。アクトはこの工場に対し、従来の酸・アルカリ投入をやめ自社の無機系凝集剤「水夢」(すいむ)で処理するプロセスへの転換を提案しました。水夢は特殊な無機ポリマー薬剤で、適用できる排水であれば事前のpH調整なしで廃液処理を完結できる画期的な製品です。実際、水夢を導入した結果、この工場では中和操作そのものを省略できたため薬品費用がゼロに近づき、年間の総処理コストを大幅に低減することに成功しました。同時に石灰由来のスラッジ発生量も激減し、脱水・廃棄にかかるコストや手間も削減されました。この事例は、中和剤そのものを必要としない新プロセスの導入で従来比○%ものコストダウンを達成した好例です。常に最新の薬剤や技術動向にアンテナを張り、自社の排水にフィットする革新的ソリューションを取り入れることで、飛躍的な効率化が可能になることを示しています。
以上のように、アクトでは中和処理システムの課題解決を支援しています。お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
最後に、本記事で取り上げた中和処理の基本原理、薬剤の選び方、業界別事例、自動化技術、トラブル対策、そして当社の事例が、読者である工場・事業所の排水管理担当者の皆様にとって有益なガイドとなれば幸いです。環境規制の遵守とコスト最適化を両立する中和処理システムの設計・運用に向けて、ぜひ今日から実践できるポイントを取り入れてみてください。お困りの際は株式会社アクトまでぜひご相談ください。我々の技術と経験で、貴社の排水中和プロセスを安全かつ効率的に最適化するお手伝いをいたします。

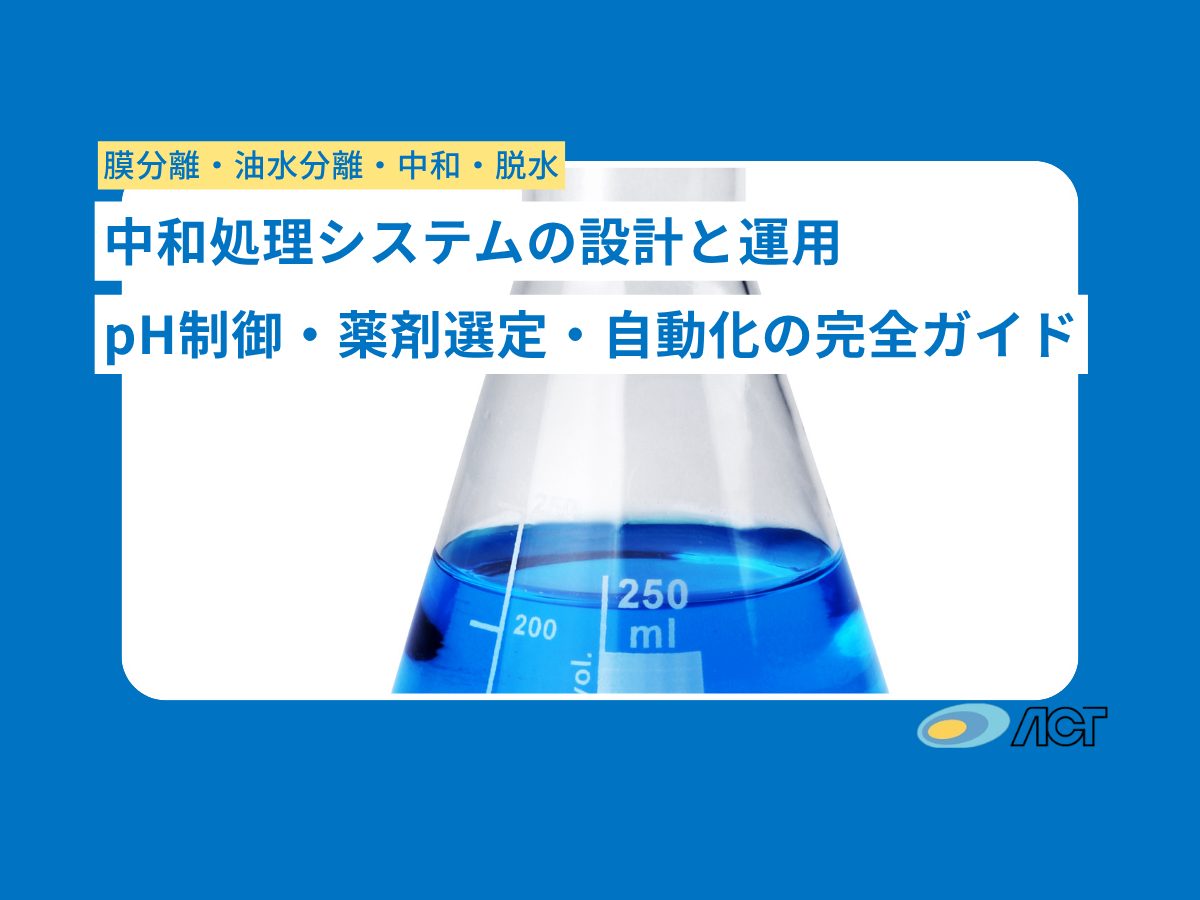
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)