工場や事業所の排水中のCOD値でお困りではありませんか?COD(Chemical Oxygen Demand、化学的酸素要求量)とは、水中の有機物汚染の程度を示す重要な指標です。適切に管理しなければ、排水基準を超過して行政指導の対象となったり、周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。本記事ではCODとは何かという基本定義から、測定方法、排水基準の詳細、COD値が高くなる原因と環境への影響、効果的な低減技術や処理システム、さらに業界別の管理ポイントや処理コスト削減のアプローチまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。最後に、株式会社アクトが手掛けたCOD改善ソリューションの実績もご紹介します。排水COD値の適切な管理によって、排水基準のクリアと処理コストの削減を実現しましょう。
↑ 廃水処理に最適な凝集剤・アルカリ中和中和剤はこちら ↑
※モノタロウで購入するよりアクトから直接購入する方がお買い得。アクトから直接購入するにはinfo@act-yume.comに「購入希望」とメール
CODの基本定義とBODとの違い
COD(化学的酸素要求量)とは、水中に含まれる有機物など酸化されやすい物質を強力な酸化剤で化学的に分解したときに消費される酸素の量(mg/L)を表す数値です。数値が高いほど水中に有機汚染物質が多いことを意味し、水質汚濁の度合いを示す重要な指標となります。
一方、BOD(生物化学的酸素要求量)は、水中の有機物が微生物によって分解される際に消費される酸素の量です。CODとBODの違いをまとめると次のとおりです:
- 測定方法の違い: BODは培養した微生物で有機物を5日間かけて分解させて測定するのに対し、CODは化学薬品(酸化剤)で有機物を短時間で酸化させて測定します。そのため、BOD測定には時間がかかりますが、CODは30分~数時間程度で結果が得られる迅速な指標です。
- 対象とする有機物の違い: BODは生物が分解できる(生分解性)の有機物量を主に反映します。一方、CODは生物では分解しにくい難分解性の有機物も含めて酸化できるため、より広範囲の有機物汚染をカバーします。その結果、同じ水試料でもCOD値の方がBOD値より高く出ることが一般的です(BODで測れない成分も酸化するため)。
- 用途の違い: BODは主に河川など生活排水主体の水域の水質評価に使われることが多い指標です。一方、CODは湖沼や海域のように微生物による分解が進みにくい水域での汚濁指標として用いられたり、工場排水の水質検査など幅広く利用されます。
要するに、CODとは水中の汚れ(有機物)の総量を短時間で測定できる指標であり、BODとは測定方法や対象範囲が異なるものの、どちらも排水中の有機汚染度を評価する重要な数値です。水質管理では両方の指標を補完的に活用し、迅速な管理(COD)と生物処理の効率確認(BOD)を行うことが望まれます。
COD測定方法(過マンガン酸カリウム法・重クロム酸カリウム法)
CODの測定には酸化剤で有機物を分解し、その消費量から酸素要求量を算出するという原理が用いられます。主に使われる酸化剤として、過マンガン酸カリウム(弱い酸化剤)と二クロム酸カリウム(強力な酸化剤)の2種類があり、それぞれCOD Mn(マンガン法)およびCOD Cr(クロム法)と呼ばれます。また、海水のように塩分が多い試料では塩化物イオンの影響を避けるアルカリ性での過マンガン酸法(アルカリ法)も用いられます。
過マンガン酸カリウム法(COD<sub>Mn</sub>)は、試料に過マンガン酸カリウムと硫酸を加えて100℃程度で一定時間(例えば30分)加熱し、有機物を酸化する方法です。酸化に要した過マンガン酸カリウムの量を酸素量に換算してCOD値を求めます。短時間で測定可能な利点がありますが、酸化力がやや弱くアルコールや有機酸など一部の有機物は酸化しきれないため、この方法で測定されるCOD値は一種の「過マンガン酸で酸化できる汚れの量」を示すものになります。
重クロム酸カリウム法(COD<sub>Cr</sub>)は、二クロム酸カリウム(重クロム酸カリ)と硫酸、触媒として硫酸銀を加えて試料を加熱し、より強力に有機物を酸化する方法です。酸化力が非常に強いため大部分の有機物を酸化でき、より総有機汚濁量に近い値が得られます。しかし、二クロム酸法では分析に有害な六価クロムや副試薬の水銀を使用するため、日本では環境保全の観点から公式のCOD測定法として認められていません(試薬廃液の処理問題があります)。欧米や中国では主にCOD Crが用いられており、日本や韓国ではCOD Mnが採用されています。両者で測定した値は単純に比較できず、一般にCOD Crの値はCOD Mnの約1.7倍程度とされていますが、試料中の有機物の種類によって比率は異なります。例えば、アルコールや低分子有機酸などはマンガン法では酸化されにくくCODに反映されづらいため、そうした成分を多く含む排水ではCOD MnとCOD Crの差が大きくなります。
実務上は、日本の環境規制に従い通常**「COD」と言えば過マンガン酸法による値を指します。ただし、取引先や海外ではクロム法の値を要求される場合もありますので、必要に応じて使い分けが重要です。測定は分析機関に依頼できますが、工場の日常管理には簡易的なパックテスト**(試薬パックによる簡易測定キット)も活用されています。例えばHACH社や共立理化学のCODパックテストを使えば、その場で概ねのCOD値を把握でき、緊急時の迅速な状況把握や日常の排水モニタリングに役立ちます。
COD基準値と排水規制の詳細
工場や事業場からの排水に含まれる汚染物質には法律で排出基準が定められており、CODも水質汚濁防止法の「生活環境項目」の一つとして排水基準が設けられています。一般排水の一律基準ではCODは日最大160 mg/L(1日平均120 mg/L)以下と定められています。つまり、事業場の排水を1日単位で測定した場合、その日の最大値が160を超えてはならず、日平均値は120を超えてはなりません。ただし、この数値は全てのケースに一律に適用されるわけではなく、排水の流出先となる水域の種類(海域・湖沼・河川など)や、事業場の種類(特定施設の種別)によって詳細な基準値が個別に設定されています。例えば、河川に放流する場合はBOD規制が適用され、COD規制は主に湖沼や海湾に放流する場合に適用されます。事業者は自社排水に適用される基準を正確に把握し、遵守しなければなりません。
さらに、国の基準に加えて地方自治体が条例で独自の排水基準(上乗せ基準)を定めている場合があります。地域の環境特性や水質目標に応じて、国より厳しいCOD規制が課されることも珍しくありません。例えば横浜市では、新設の工場等に対しCODの許容限度を25〜40 mg/Lと、国基準より大幅に厳しく定めています。このような自治体独自の規制(上乗せ条例)がある地域では、より高度な排水処理が求められます。また、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海などの閉鎖性水域では総量規制(地域全体でのCOD総排出量を規制)が敷かれており、各事業所に排出負荷量の削減が求められています。
一方で、水環境そのものの目標値として環境基準も定められています。環境省の定める公共用水域の水質環境基準では、湖沼の水質についてCOD値○mg/L以下といった目標が設定されています。例えば人の利用目的が高いA類型の湖沼ではCOD 3 mg/L以下が望ましい水質基準とされています。一般にCOD値が低いほど水質が良好と判断され、例えばCODが1 mg/L未満なら「きれいな水」、5〜10 mg/Lで「汚れている水」、10 mg/L以上では「非常に汚染が進んだ水」と評価されます。事業者の排水がこれら公共水域に与える影響を考えると、排水の段階でできる限りCODを低減し、環境基準の達成に貢献することが求められます。
近年は排水規制がさらに厳格化する動きも見られます。中央環境審議会では、一律排水基準のCOD値を現行の日最大160→120 mg/Lへ引き下げる議論が進められており、今後法令改正されれば全国的に一層厳しい管理が必要になります。またESGやSDGsの観点からも、水質負荷低減が企業評価のポイントとなっており、自主的にCOD削減目標を掲げる企業も増えています。
このように、CODの排水基準は国および自治体によって定められ、事業者はその両方を満たすよう排水管理を徹底しなければなりません。万一基準を超過すると操業停止など厳しい措置がとられる可能性もあります。自社の適用基準をよく理解し、適切な処理設備と運用で余裕をもって基準クリアすることが重要です。
COD値上昇の原因と環境への影響
「排水のCOD値がなかなか下がらない」「以前よりCOD濃度が上がってきた」という場合、まずはCOD値上昇の原因を探る必要があります。CODが高くなる主な要因として、排水中に分解されずに残留する有機物が多いことが挙げられます。具体的な原因には例えば以下のようなケースがあります。
- 原水の汚染負荷増加: 製造工程から出る有機物量が増えたり、洗浄工程で多量の薬剤・油分が流出した場合、排水中の有機汚濁負荷が高まりCOD値が上昇します。特に食品加工残渣や糖分・でんぷん質を多く含む排水は発酵しやすく、短時間でCODが急上昇しがちです。
- 難分解性物質の混入: 合成樹脂や高分子化合物、界面活性剤など微生物では分解しにくい物質が含まれると、生物処理では除去できずCODが残留します。化学工場や化粧品工場の排水ではこれら難分解性成分が原因でCOD値が高止まりすることがあります。
- 油脂の流出: 機械加工や金属部品製造工程で使用する潤滑油・切削油などの油分は、水面に油膜を張りわずかな量でもCOD値に強く影響します。油脂分は生物処理槽でも分解されにくく、残存するとCOD上昇の要因となります。
- 染料や顔料の残留: 繊維染色やインク製造排水では、色素成分が水中に残ると高い色度とともにCODも増加します。さらにこうした成分は膜処理では**膜ファウリング(膜の目詰まり)を引き起こしやすく、処理効率低下によるCOD悪化につながるケースもあります。
- 処理設備の不備や劣化: 排水処理フローの設計不良や老朽化・過負荷運転により、充分に有機物が処理されずCODが高く残る場合もあります。活性汚泥槽で溶存酸素量が不足したり、沈殿分離不良で汚泥が流出すると、処理水のCOD値が上昇する原因となります。
以上のような原因でCOD値が上昇した排水をそのまま環境中に放流すると、深刻な悪影響を及ぼす恐れがあります。COD値の高い水は水質汚染の進行を示すもので、環境や生態系に深刻なダメージを与える可能性があります。排水中に有機物が多い状態で放流されると、水域中の好気性微生物がそれら有機物を分解する際に水中の溶存酸素(DO)を大量に消費します。その結果、水中のDO濃度が急激に低下し、魚類など水生生物は呼吸困難に陥り、最悪の場合大規模な魚のへい死(酸欠死)を招いてしまいます。また有機物汚濁が進むと、水面に異常繁殖したプランクトンや微生物のマットが発生して日光が届かなくなり、水草などの光合成も阻害されます。
特に閉鎖性水域(湖沼や内湾)では、有機物による汚濁に加えて窒素・リンなどの富栄養化が進行しやすく、赤潮やアオコ(藻類の大発生)、深層の貧酸素水塊の発生といった深刻な環境問題が起こります。実際、日本の閉鎖性海域では外洋に比べCODや栄養塩濃度が高く、毎年のように赤潮や酸素欠乏が報告されています。CODはこうした水質汚濁による生態系被害を示すシグナルでもあるため、排水管理者はCOD値の上昇を軽視せず、原因に応じた適切な対策を講じる必要があります。
COD低減技術と処理システム
排水中のCODを効果的に下げるには、排水処理プロセス全体の最適化が重要です。CODを除去・低減する方法には、大きく分けて物理的処理、化学的処理、生物的処理の3つのアプローチがあります。実際の現場では単独ではなく複数の手法を組み合わせた多段処理によって、高い処理効率と安定運転が実現されています。ここでは代表的なCOD低減技術と処理システムを紹介します。
- 物理的処理: 排水中の固形物や油分を物理的に分離除去する工程です。具体的にはスクリーンによる粗ごみ除去、沈殿槽でのSS沈降分離、浮上分離槽(DAF)での油脂・微細SSの回収などがあります。物理処理単独ではCODを5~25%程度除去するのが一般的ですが、前段で粒子状汚濁を除去することで後工程の負荷を減らし、生物処理槽の過負荷防止や薬品コスト削減に繋がります。また油脂や大きな固形物を先に除去しておくことで、後段の膜ろ過のファウリング抑制や汚泥膨化のリスク低減といった効果も期待できます。物理処理は操作も比較的簡便で、薬品の投加量調整などの手間が少ないメリットがあります(ただし回収汚泥・ゴミの処分は必要です)。
- 化学的処理: 薬品を使って溶解・コロイド状の有機物を除去する工程です。代表例は凝集沈殿法で、凝集剤(無機系のPACや硫酸鉄など+高分子凝集剤)を投入して微細な有機物やSSを凝集し、沈殿分離させます。凝集処理を適切に行うと20~35%程度のCODを除去可能で、生物処理では分解しきれない着色成分や難分解性有機物も一部捕捉できます。また、強力な酸化剤を用いる方法も化学的処理に含まれます。例えば次亜塩素酸や二酸化塩素の注入による酸化分解は難分解性CODを一次的に分解し、生物分解性を高める効果があります(COD5~15%低減)。さらに近年ではオゾン処理やフェントン法、過酸化水素+紫外線による高度酸化処理(AOP)技術も普及しつつあります。これらは難分解性の有機物を化学的に分解してCODそのものを減らすことが可能で、生物処理の前後に組み込むことで排水の最終CODを大幅に下げるのに貢献します。高度酸化は設備・運転コストが高めですが、排水基準が厳しい場合や、処理水を再利用する場合には有効な選択肢です。
- 生物的処理: 微生物の働きを利用して有機物を分解し、CODを除去する工程です。典型的なのは活性汚泥法や生物膜法(接触曝気、生物ろ床など)で、好気性微生物が有機物を二酸化炭素と水に分解します。十分な空気(酸素)と栄養・適切な温度pH条件が整えば、生物処理はCODやBODを大幅に減容できる最も経済的な方法です。一般的な活性汚泥プロセスでも最終的な処理水のCODは60~90 mg/L程度まで下がります。さらに、高性能な膜分離活性汚泥法(MBR)を導入すれば、微生物で分解しきれなかった有機物や微細なSSも膜で截留できるため、放流水CODを20~50 mg/L以下と格段に良好な水質に仕上げることも可能です。MBRはランニングコストや設備費が従来法より高いものの、処理水の再利用(工程水や洗浄水へのリサイクル)を可能にし、用水使用量削減による経済効果も期待できます。生物処理全般では微生物の状態管理がポイントで、DOセンサーによる溶存酸素の最適制御やMLSS濃度の維持管理を行うことで、省エネ運転(曝気量15~30%削減)や汚泥発生抑制が可能です。
以上のような各種技術を組み合わせ、「前処理(物理・化学)+主処理(生物)+高度処理」といった多段階でアプローチするのが、CODを確実かつ効率的に下げる近道です。例えば、ある工場では既存の活性汚泥プロセスに凝集沈殿と膜処理を追加することで、従来はCOD 80 mg/Lだった放流水を40 mg/L以下に改善し、自治体の厳しい基準をクリアしたケースもあります。また、高負荷時のみ移動式の仮設処理ユニットを導入して既存設備を補完する手法も効果的です。繁忙期やトラブル時に一時的に前処理強化ユニットをレンタル活用することで、既存ラインを止めずにCOD負荷を減衰させることができます。
大切なのは、自社排水の特性(汚染負荷や汚濁成分の種類)に応じて最適な処理フローを設計することです。仮に排水中のBOD/COD比(生物難易度の指標)が低い場合(難分解性成分が多い)は、生物処理だけでなく凝集+浮上分離やオゾン酸化、活性炭吸着などを組み合わせて最終仕上げする設計が有効です。反対にBOD/COD比が高く大部分が生物分解可能な排水なら、生物処理を中心に据えて前後の処理は簡易な構成で済ませる方がコスト面で有利でしょう。このように、排水性状に合った処理技術の選定と、その運転条件の最適化によって、COD値の安定的な低減が達成できます。
業界別COD管理の実践方法
排水中のCOD起因物質や効率的な処理方法は、業種によってある程度傾向があります。ここでは業界別に見たCOD管理のポイントや実践方法を解説します。
- 食品・飲料業界: 食品加工廃水や飲料製造排水にはでんぷん、糖類、タンパク質など高濃度の有機物が含まれます。これらは比較的生物分解されやすいものの濃度が高いため、まずスクリーンで固形残渣をこしとり、必要に応じて嫌気性処理(メタン発酵槽)で高濃度有機物を減容した後、好気性生物処理で仕上げると効果的です。発酵性の糖分が多い場合はpHの急変に注意し、中和や段階希釈を行うこともあります。食品工場では悪臭防止の観点からも嫌気槽のガス捕集や適切な換気が重要です。
- 機械・金属加工業界: 機械部品製造やメッキ工場等の排水では油脂分や研磨剤由来の微細固形物がCOD上昇の原因となります。対策として、浮上油分離槽や凝集沈殿によって油分・SSをできるだけ前段で除去することが肝要です。油分は親油性の吸着剤マットやオイルフェンスで回収する方法も有効です。また、冷却水など大量の水を使う工場では排水の循環再利用(ろ過・殺菌して再び洗浄水に使う)がコスト低減に直結します。金属加工系排水はpH中和や重金属除去(沈殿法)が並行課題になる場合も多く、総合的な処理システム設計が必要です。
- 化学・医薬・化粧品業界: 製品中間体や原料が混ざるこれら業界の排水は、合成高分子や界面活性剤、溶剤など難分解性の有機化合物を含むことがあります。生物処理だけではCOD基準を満たせないことも多いため、オゾン分解や加圧湿式酸化などの高度処理技術や、粉末活性炭吸着の併用が効果を発揮します。また製薬系ではBOD/COD比が極端に低い排水もあるため、凝集沈殿+活性炭処理で難分解成分を可能な限り除去してから生物処理にかけるケースも見られます。化学工場では処理プロセスで副生成する廃液の分離(高濃度ストリームを分別して別途処理)もポイントです。
- 繊維・染色業界: 染料や顔料を扱う繊維工場の排水は色度とCODの両方が高く、生物処理だけでの対応は困難です。一般的には無機凝集剤(硫酸アルミニウムなど)で脱色凝集→沈殿し、上澄みを生物処理へ送るプロセスが用いられます。凝集剤も繊維染色専用の処方品(脱色凝集剤)を使うと色度除去率が高まります。凝集沈殿後の生物処理としては、接触曝気槽やMBRで有機物を削減し、仕上げに砂ろ過や活性炭ろ過で微細な色素成分まで捕捉すると、放流水の透視度が格段に向上します。染色排水では処理スラッジ中に染料が含まれるため、脱水ケーキの適正処理(産廃処理)も計画しておく必要があります。
- 電子・半導体業界: 超純水を大量に使う半導体製造では、有機物汚染よりむしろ微量金属やフッ素・アンモニアなどの除去が主眼ですが、一部工程では剥離液や現像液由来のCOD負荷が発生します。COD濃度自体は低~中程度でも、社内基準で極めて厳しい水質が要求されることが多いため、イオン交換処理や純水リサイクル装置で徹底的に浄化する場合があります。難分解性のフォトレジスト成分などはオゾン分解+活性炭で処理し、放流せず回収リサイクルすることも検討されます。
以上、業界ごとの排水特性とCOD管理のコツを述べましたが、共通して重要なのは**「自社排水の汚れの中身」を把握することです。排水を分析し、どの成分がCODを押し上げているかを知れば、有効な対策が見えてきます。例えば食品工場なら「糖分カットの洗浄方法に変更」「原料くずを設備排水に流さず回収」といった工程改善による汚れの発生抑制も有効でしょう。また、各業界で実績のある専門業者に相談し、自社の事例に近い成功事例(ベストプラクティス)**を参考にすると、短時間で改善策を講じることができます。
COD処理費用の削減アプローチ
CODを低減することは環境対応だけでなく、処理コストの削減にも直結します。高濃度の有機汚濁を含む排水は処理に手間と費用がかかるため、効率よくCODを下げるほど経済的メリットが得られます。ここでは、排水処理費用を抑えるいくつかのアプローチを紹介します。
- 源流対策と汚染負荷の低減: 最も効果的なコスト削減策は、汚れそのものを出さない・減らすことです。製造工程での原材料ロスを減らしたり、設備のドライ清掃を徹底して洗い流す汚れを減らすなど、排水へ流入する有機物量を抑制すれば、その分処理負荷が減りコスト削減につながりますigaden.com。例えば食品工場で製品くずを事前に回収するようにしたところ、排水処理薬品の使用量が大幅に減りコストダウンした例もあります。また、クローズドシステム化で工程内リサイクル率を上げ、排出する排水量自体を減らすことも有効な源流対策です。
- 適切な処理プロセス選択: 排水性状に対して過剰性能な処理をしていないか見直すことも大切です。例えば、生物処理だけで十分対応できる排水に高価な薬品処理を併用していれば無駄なコストですし、その逆に難分解性成分が多いのに生物処理一辺倒では放流水が基準を満たせず再処理コストが発生するかもしれません。自社排水にベストな処理方法の組み合わせを専門家に評価してもらい、シンプルで効果的なプロセスに最適化することで、余計な薬品やエネルギーの浪費を防げます。
- エネルギー効率の向上: 排水処理のランニングコストで大きな割合を占めるのが電力などのエネルギーです。特に活性汚泥プロセスでは曝気用ブロワーの電力が負担になります。近年はDOセンサーで溶存酸素をモニタリングし、インバーター制御で曝気量を自動調整することで無駄な過剰曝気を防ぎ、電気代を15~30%削減する事例もあります。またポンプの省エネ型への更新やタイマー運転の導入も効果的です。さらに、嫌気性処理を取り入れて発生するバイオガスをエネルギー回収(ボイラー燃料など)する工夫も、大規模プラントではランニングコスト低減に寄与します。
- 薬品費の削減: 凝集剤や消毒剤など薬品コストも積み重なると大きな負担です。薬品費削減には、まず最適な薬品選定と投加量の見直しが必要です。原水のpHやORPを最適化することで薬剤使用量が減らせる場合もあります。凝集剤については、一次無機剤(PAC等)と高分子を段階的に添加して効率良く凝集させれば、単一投与より薬剤量を減らし汚泥量も削減できます。薬品メーカーや水処理業者と連携してジャー試験を行い、必要最小限の薬剤で目標水質を達成できる条件を探ることが有用です。また、薬品単価の見直し(代替薬品の検討や一括購入によるコスト交渉)も行いましょう。
- 排水処理の内製化・外注化の比較: 排水を全量業者に委託処理(産廃扱い)している場合、処理量に応じて高額の費用が発生します。そのような場合、ある程度自社で前処理・減量化してから委託すれば量が減って費用削減になりますし、場合によってはオンサイトで全処理した方が中長期的に安くなるケースもあります。逆に、自社処理設備の維持管理コストが高すぎる場合は、思い切って排水を下水道へ放流して下水道料金を払う方が安くつく場合もあります(要・排水基準適合)。設備投資や人件費を含めたトータルコストで、内製と外注の損益分岐点を見極めることが重要です。
- 補助金や専門家活用: 排水処理設備の更新や高度化には費用がかかりますが、国や自治体の補助金制度を活用できる場合があります。中小企業向けの公害防止対策補助や、省エネ設備導入補助金など該当するものがないか調べ、上手に利用しましょう。また、水処理の専門コンサルタントに有償で診断してもらい、コスト削減のポイントを指摘してもらうのも一つの方法です。短期的な視点だけでなく、中長期の投資回収を含めてコスト最適化を図ることが、安定した排水管理と経営効率の両立に繋がります。
以上のようなアプローチを組み合わせ、排水処理コストの見える化と最適化を進めることで、COD対策に伴うコスト負担を大幅に軽減できます。実際に、後述するアクト社の事例でもCOD処理コストを60%以上削減し、投資回収1年未満を実現したケースがあります。環境対応と経済性の両立を目指し、自社に合ったコスト削減策を検討してみましょう。
アクトのCOD改善ソリューション実績
株式会社アクトは、様々な業種の排水課題を解決してきた実績があります。特にCOD低減に関しては、独自開発の無機系凝集剤「水夢(スイム)」シリーズと、コンパクトで高性能な**水処理装置「ACT-200」**を組み合わせたソリューションに強みがあります。ここでは、アクトが手掛けたCOD改善事例の一部を紹介します。
- 繊維染色工場O社の事例: タオル製品の染色加工を行うO社では、染色廃水の色度とCODの高さに長年悩まされていました。アクトはまず廃液の無償テストを実施し、染料に対し高い凝集効果を持つ専用凝集剤**「水夢SP-40014MB」を提案しました。導入後、**処理水の色度は肉眼で無色透明となり、COD値も排水基準を十分クリアできるレベルまで低減(COD低減率約85%)**しました。その結果、年間約900万円かかっていた処理コストが約360万円と60%削減され、薬品使用量も従来比半減しました。O社の工場長からは「地域環境への対応強化という経営課題が大きく前進した。季節変動に応じた調整など定期的なフォローも受けられ安心だ」と高い評価を頂いています。
- 外壁パネル製造T社の事例: 建材製造業のT社では、水性塗料の洗浄排水処理において、特殊顔料を含むため既存凝集剤では処理困難で全量産廃処理していたという課題がありました。月20トンの廃液処理に年720万円ものコストがかかり、保管・搬出の手間も大きな負担となっていました。アクトは廃液サンプルテストで最適凝集剤を選定し、水性塗料洗浄廃液の処理に適した凝集剤**「水夢SP-4004V」と1回200L処理可能な小型装置「ACT-200」を組み合わせたソリューションを導入しました。その結果、処理水質は全項目で排水基準をクリアし、排水処理コストは年間約720万円→約250万円と約65%削減**、廃液量も月20トン→1トンと大幅減容(95%削減)できました。加えて、1日3時間かけていた作業が30分に短縮され(約85%削減)、廃液保管スペースも80%削減と、経済面・環境面・運用面で大きな効果が得られました。
このほかにも、半導体工場の超純水系排水への対応や、食品工場の高濃度有機廃水処理など、アクトは各業種に合わせたCOD低減ソリューションを提供しています。
このように株式会社アクトは、高度な水処理薬剤開発力と細かなお客様サポートを強みに、各企業のCOD問題を解決してきました。排水のCOD値でお困りの事業者様は、ぜひアクトにご相談ください。適切なCOD管理によって排水基準をクリアし、環境リスクとコストの両面でメリットを得られるはずです。

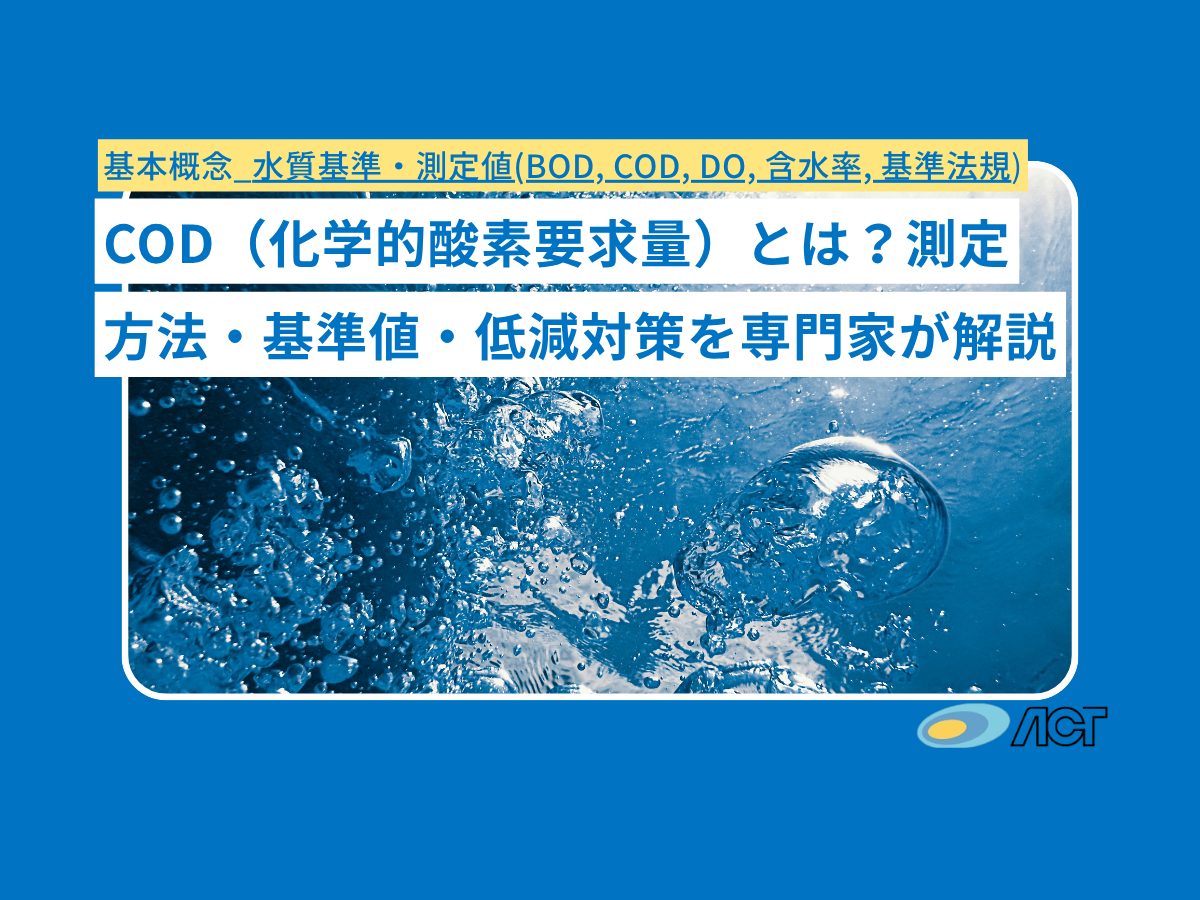





_安定稼働-300x225.jpg)
_四角-300x225.jpg)
_カーボン-300x225.jpg)
_BCP-300x225.jpg)
_DX-300x225.jpg)
_PFAS-300x225.jpg)