工場や下水処理場で発生する汚泥の脱水処理は、水分をできるだけ取り除いて体積を減らし、処理や処分を容易にする重要な工程です。汚泥はその大半(約99%以上)が水分であるため、脱水せずに焼却や埋立てを行うのは困難です。脱水処理によって水分を絞り出し、汚泥をケーキ状の固形物にすれば、運搬コストや最終処分量の削減、悪臭対策、さらには後続の焼却効率向上など多くのメリットがあります。本記事では、汚泥脱水の基本原理から主要な脱水装置の種類と特徴、業界別の脱水システム事例、脱水効率を高める薬剤選定や条件最適化のポイント、自動化技術の動向、そして株式会社アクトの技術力を活かした脱水処理改善の成功事例まで、包括的に解説します。一般の工場排水担当者の方にも分かりやすいよう、専門用語も補足しながら進めますので、ぜひ最後までお読みください。
脱水処理の基本原理|機械的脱水と薬剤による脱水促進メカニズム
汚泥の脱水処理には、大きく分けて機械的な脱水と薬剤添加による脱水促進の二つの要素があります。まず機械的脱水では、脱水機に汚泥をかけて圧力や遠心力で水分を物理的に分離します。例えば、フィルタープレス(加圧ろ過)では高圧で汚泥をろ布に押し付けて水を絞り出し、遠心脱水機では高速回転による遠心力で水分を分離します。これら機械的手段により汚泥の含水率(全体に占める水分の割合)は大幅に低下し、通常は含水率85%以下(固形分15%以上)のケーキ状にまで濃縮されます。含水率85%以下であれば、陸上での安定した埋立処分が可能になり、また焼却時の燃料消費も削減できます。
一方、汚泥には微細な固形粒子(コロイド)が多数含まれ、それらは通常マイナスに帯電して互いに反発しあっているため、そのままでは沈降・脱水しにくい性質があります。ここで活躍するのが凝集剤(フロック形成剤)などの薬剤です。正電荷を持つ無機凝集剤(例えばポリ塩化アルミニウムPACや硫酸アルミニウム)を添加すると、微粒子の表面電荷が中和されて一次凝集が起こり、小さなフロック(粒子の塊)が形成されます。さらに高分子凝集剤(ポリマー薬剤)を併用すると、長い高分子鎖が複数のフロックを橋渡しして結合し、大きくて強固な二次フロックを作ります。この架橋効果によってフロック径が大きくなると沈降やろ過が飛躍的に促進され、水と固形物の分離が容易になります。要するに、薬剤による凝集処理は汚泥中の微細粒子を素早く大きな塊にまとめる「潤滑油」の役割を果たし、機械的脱水を助けて効率と脱水率を高めるのです。
汚泥脱水では通常、機械的手段と薬剤の併用が行われます。まず汚泥に高分子凝集剤などを混ぜてフロック化(調質)し、その後にフィルタープレスや遠心脱水機などで固液分離を行うのが典型です。近年では、凝集剤の性能向上により少量添加で高い効果が得られるようになり、特に下水汚泥の脱水ではカチオン(陽イオン)系高分子凝集剤が主流となっています。カチオン系ポリマーは鉄塩や石灰などの無機薬剤に比べ、汚泥粒子の電荷中和と架橋作用に優れており、少ない添加量で高い脱水効果を発揮できる点が利点です。薬剤コストと処理効果のバランスを考慮しながら最適な凝集剤を選定・添加することで、機械的脱水だけでは達成できない高い脱水効率を実現できるのです。
脱水装置の種類と特徴|ベルトプレス・遠心脱水機・フィルタープレス・スクリュープレスの比較
汚泥脱水に用いられる代表的な脱水装置には、ベルトプレス脱水機、遠心脱水機、フィルタープレス(加圧脱水機)、スクリュープレス脱水機などがあります。それぞれ脱水の方式や構造が異なり、得意とする汚泥の種類や運用面の特徴も異なります。以下に主要な4種類の装置の仕組みとメリット・デメリットを比較してみましょう。
- ベルトプレス脱水機 – ろ布ベルトで圧搾脱水する方式です。2本のエンドレスベルト(ろ布)の間に凝集処理済みの汚泥を挟み、まず重力で水を滴下させた後、複数のローラー間でベルトを圧縮して水分を絞り出します。連続処理が可能で処理量あたりのコストが低く、含水率の低い脱水ケーキを比較的高速に得ることができます。一方で定期的なベルト洗浄やローラー部の目詰まり対策が必要で、メンテナンスに手間がかかる点がデメリットです。近年はベルト内に凝集反応槽を組み込んで効率化した機種や、圧縮ゾーンを改良してより低含水率を実現した機種も登場しています。
- 遠心脱水機 – 高速回転による遠心力で固液分離する方式です。デカンタ型(スクリューデカンタとも呼ぶ)では、シリンダ形状のドラムを高速回転させて汚泥を投入すると、密度の大きい固形分は外側に押し付けられ、内部のスクリューによって固形物は排出されます。遠心脱水機は処理速度が速く、1時間に数トン規模の汚泥処理も可能なため、大量の汚泥が出る大規模プラントで広く採用されています。さまざまな種類の汚泥に対応しやすい汎用性もメリットです。ただし構造が複雑で高速回転のため消費電力が大きく、また運転時の騒音・振動も大きいので、防音対策や定期整備が重要になります。
- フィルタープレス(加圧ろ過式脱水機) – フィルタープレスは多数のろ布(フィルター)を張った板と枠で構成された装置で、高圧ポンプで汚泥をろ室に圧入し、ろ布越しに水分をろ過排出するバッチ式の脱水機です。プレートを並べてろ過→圧搾→洗浄→排出のサイクルを繰り返すため処理は間欠的ですが、その分圧力を長時間かけられるため、非常に含水率の低いケーキを得ることができます。実際、フィルタープレスは他の方式に比べ乾燥度の高いケーキ(含水率60~70%程度以下も可能)を生成でき、焼却や資源化(堆肥化等)の前処理として有利です。欠点は装置が大型かつ停止時間があるため処理量あたりの効率が低い点と、ろ布の交換や洗浄といった維持管理に手間がかかる点です。ただ近年では、自動でろ布を洗浄する機構や連続的にプレートを動かす工夫により、処理効率と省力化も向上しています。
- スクリュープレス脱水機 – 低速回転のスクリューで汚泥を徐々に圧縮し、絞り出す方式です。円筒形のスクリーン(フィルター)内部にスクリューコンベアがあり、先端の背圧板との間で汚泥を圧縮することで水分を押し出します。回転数が遅くエネルギー消費が小さい一方、連続的に処理できる利点があります。特に多重板式(多重円板)スクリュープレスは可動リングと固定リングを交互に重ねた構造で、自己洗浄効果があり目詰まりしにくい点が特徴です。また油分を含む汚泥や高含油スラッジでも滑りやすいステンレス製のリングによって対応しやすく、従来大量の洗浄水が必要だったベルトプレスに比べ洗浄水を大幅に削減できます。スクリュープレスは構造がシンプルで日常の操作や保守が容易な反面、単位時間あたりの処理量は遠心機等より小さめで、大量処理には複数台の並列設置が必要になることもあります。しかし近年はスクリュープレスの改良が進み、背圧制御や多段圧縮により低含水率のケーキを得られる機種も登場しつつあります。脱水汚泥の含水率を70%以下(固形分30%以上)に維持できるよう、出口に水分センサーを設置してスクリューの圧力や回転数を自動調整する最新機も実用化されています。
以上が主な脱水機の種類と特徴です。いずれの方式にも一長一短がありますので、汚泥の種類・量や処理目的に応じて適切な機種を選定することが重要です。例えば下水汚泥のように大量で連続処理が必要なケースでは遠心脱水機やベルトプレスが適し、高粘度で難脱水な汚泥には真空脱水機(真空ろ過)やフィルタープレスの方が適する、といった使い分けが推奨されています。メーカー各社からは、多様な汚泥に対応できるよう各種脱水機がラインナップされていますので、自社の汚泥性状や処理目標に合った装置を選びましょう。
業界別脱水システム|下水処理・食品・化学工場での汚泥脱水最適化事例
汚泥の性状はその発生源によって大きく異なり、業界や用途ごとに最適な脱水システムも変わってきます。この章では、下水処理分野、食品工場、化学工場といった代表的な例について、それぞれの汚泥脱水の課題と最適化のポイント、実際の改善事例を紹介します。
下水処理場の汚泥脱水: 下水処理では、生物処理によって生じる余剰汚泥などが大量に発生します。典型的な都市下水処理場では遠心脱水機やベルトプレス脱水機が多く採用されてきました。余剰汚泥自体は含水率99%以上の液状ですが、凝集剤(通常はカチオン系ポリマー)を添加し脱水機にかけることで、含水率80~85%程度のケーキにまで濃縮されます。含水率85%以下であれば埋立処分が可能となり、多くの処理場でこの水準が目標とされました。1980年代以降、下水汚泥の脱水には高性能ポリマーの普及に伴って遠心脱水機の採用が増えましたが、1990年代以降は資源循環やエネルギー回収の観点から、含水率をさらに下げて汚泥を焼却炉の補助燃料に利用する動きも出てきました。そのため、スクリュープレス脱水機や電気浸透脱水など、より低含水率(70%以下)のケーキを得られる技術が注目されています。例えば東京都下水道局では、高度な自動制御によりポリマー注入量を最適化し、常に含水率が低く安定した脱水ケーキを得るシステムの実証を行い、従来より焼却燃料の削減と薬品コスト低減に成功しています。このように、大量の汚泥を扱う下水分野では、高性能薬剤+大型脱水機+自動制御による効率化がポイントです。
食品工場の汚泥脱水: 食品・飲料製造工場では、製造排水の処理過程で生じる有機性汚泥や食品残渣スラッジの脱水処理が課題となります。これらの汚泥は含油分や繊維質を多く含み、悪臭も発生しやすいため、迅速に脱水・減量化してしまうことが求められます。食品系汚泥は下水汚泥に比べて粘度が高かったり、微生物由来の粘質物を含んでろ布がつまりやすい傾向があり、脱水効率が出にくいケースもあります。そのため、食品工場ではスクリュープレス脱水機など目詰まりに強い機種や、高分子凝集剤の適正投与によるフロック形成改善がカギになります。
実際、ある食品加工工場では、脱水ケーキの含水率が約80%と高く汚泥重量が多いことが問題でしたが、凝集プロセスを見直すことで大きな改善が得られています。株式会社アクトが提案したソリューションでは、従来ポリマー剤だけだったところに少量の無機凝集剤「水夢(すいむ)」を前段添加し、その後に新しい高分子ポリマーを投入する二段凝集処理へ変更しました。その結果、脱水機から排出されるケーキの含水率は約75%まで低下し、汚泥重量にして約25%の減量を達成できました。処理コストも年間で数百万円規模の削減が見込まれ、実際の運用でも処理費用を約30%削減できています。さらにフロックが大きくなったことで脱水機の処理スループットも向上(毎時処理量20%増加)し、設備稼働時間の短縮による電力削減効果も得られました。この事例は、有機質の多い食品系汚泥でも凝集剤の選定・組み合わせ次第で脱水効率を飛躍的に高め、コストと環境負荷を同時に低減できる好例と言えます。
化学工場の汚泥脱水: 化学工場や塗料・インキ工場からは、製造プロセスで出る無機スラッジや塗料残渣、反応副生成物の汚泥など、処理の難しい廃液・汚泥が発生します。これらは重金属や高濃度の薬品成分を含む場合もあり、法規制の基準を満たすための前処理と効率的な脱水が必要となります。たとえば従来は有機溶剤系が主流だった塗料製造廃液も、水性塗料の普及に伴い水性塗料スラッジの処理が課題となっています。その解決策として開発されたのがゼオライト系無機凝集剤「水夢(SUIMU)」です。水夢シリーズは汚濁水に投入・攪拌するだけで顔料や樹脂分をみるみる凝集沈殿させ、上澄みは透き通った水になるため、処理後の水は下水道放流基準をクリアするほど清澄化します。従来は廃塗料の泥水全体を産業廃棄物として処理していたものが、水と固形物に分離されることで廃棄物量を大幅に削減できました。ある工場では水夢処理への切り替えによって年間の産廃処理量が劇的に減少し、処理コストも大幅ダウンしたとの報告があります。
さらに水夢で生成されるフロック(沈殿物)は粒子が大きく含水率が低いため、脱水機での処理もスムーズに行えます。一般的な高分子凝集剤だけで処理した汚泥はゼリー状で水分を多く含み脱水に時間がかかりますが、水夢で得られるフロックは水分含有が少ないためフィルタープレスで圧搾しやすく、実際に脱水ケーキの含水率が下がり運搬すべき汚泥重量が減った例もあります。このように化学系スラッジの処理では、汚染物質をしっかり凝集・中和しつつ、水分を抱え込まない固形フロックにすることがポイントです。必要に応じて無機凝集剤と高分子凝集剤の二段併用や、凝集助剤・吸着剤(後述)を組み合わせることで、難処理の化学汚泥でも効率的に脱水・減量化できる可能性があります。
脱水効率の向上|高分子凝集剤・脱水助剤の選定と条件最適化
脱水効率をさらに向上させるには、使用する薬剤の選定と投入条件の最適化が重要です。汚泥脱水で主に使われる薬剤は、前述の高分子凝集剤(ポリマー)と、必要に応じて用いる凝集助剤(脱水助剤)です。それぞれの適切な選び方と使い方のポイントを押さえておきましょう。
まず高分子凝集剤については、汚泥の種類に応じてカチオン系・アニオン系・ノニオン系など帯電特性の異なるタイプを使い分けます。一般に下水汚泥や有機汚泥にはカチオン(陽イオン)系ポリマーが用いられることが多いです。理由は、カチオンポリマーが汚泥粒子の表面電荷を効率よく中和し、大きなフロックを形成する架橋・吸着作用にも優れていて、少量で高い凝集効果と脱水促進効果を発揮できるためです。実際、カチオン系高分子凝集剤の普及によって遠心脱水機での余剰汚泥処理が大幅に効率化した経緯があります。一方、処理水中に溶け込んだ懸濁物質や有機物を凝集させる目的ではアニオン系が適する場合もあり、汚泥性状によって適材適所で選定することが肝心です。凝集剤メーカー各社からは分子量や荷電度の異なる多彩なポリマー製剤が出ていますので、現場の汚泥にマッチするものを試験で見極める必要があります。
高分子凝集剤を使用する際に特に留意すべきは、その最適添加量の見極めです。ポリマーは「入れれば入れるほど水が固まる」というものではなく、ある適正量でフロック形成と脱水性能が最大化し、それを超えると逆に効果が低下する場合があります。実験によれば、ポリマーの過剰投入・不足投入はいずれも脱水ケーキの含水率を上昇させてしまい、最適量で投入した場合に最も低含水率となることが確認されています。ポリマー過剰では未反応の余剰高分子が残ってケーキ中の水分を保持したり、過少ではフロックが不十分で水が絞り切れなかったりするためです。したがって、ジャーテスト(ビーカー試験)等で凝集状態やろ過性を確認しつつ、含水率が最小になるポリマー注入率を探ることが大切です。近年では汚泥の性状(固形分濃度や表面電荷)をオンラインで測定し、リアルタイムにポリマー添加量を自動制御するシステムも開発されています。例えば脱水機の分離液中の電荷量を常時計測し、「負の電荷が残っていればポリマー不足、正に傾けば過剰」と判断して適量に調整する技術が報告されており、実運転で薬品費の削減と含水率安定化に成功しています。
次に凝集助剤(脱水助剤)です。これは文字通り主薬たる凝集剤を補助する薬剤で、フロック形成の安定化や脱水効率の改善に効果があります。凝集剤だけでは沈降しにくい微細粒子を抱えてしまう場合や、汚泥中に油分が多くてフロックが崩れやすい場合などに助剤を併用すると、フロックが大きく強固になり沈降・脱水性が向上します。凝集助剤には大きく無機系と有機系があり、それぞれ作用メカニズムと適用場面が異なります。
無機系助剤はアルミニウムや鉄、石灰などを主成分とするもので、代表的なものにPAC(ポリ塩化アルミニウム)やフェリック系(鉄塩)、あるいは天然鉱物系(酸化カルシウムCaOやマグネシウムMgOを含むもの)などがあります。無機助剤は比較的安価で取り扱いも容易なものが多く、凝集力を補強したりpH調整を兼ねたりする目的で使われます。例えば難凝集性のコロイド粒子にPACを少量加えると、ポリマー単独では作れなかったフロックの核ができて凝集が安定するケースがあります。また天然鉱物系助剤は汚泥中の重金属や油分を吸着する効果に優れ、環境負荷を抑えながら処理を向上させることが可能です。
一方、有機系助剤は高分子補助剤とも呼ばれ、ポリアクリルアミドなどのノニオン性ポリマーを用いることが多いです。主剤(例えばPACやカチオンポリマー)の架橋をさらに補助し、フロックを一段と大きく成長させ安定化させる役割を果たします。有機系助剤を併用すると、より水切れの良い大粒径フロックを形成しやすくなるため、最終的な脱水ケーキ含水率の低減に非常に効果的です。実際、ある難脱水性汚泥の処理ではカチオン凝集剤+ノニオン助剤の組み合わせで含水率が大きく改善した例もあります。また助剤には、特定の用途向けに開発された凝集促進剤もあり、低温下や高濃度有機廃水など通常の凝集処理ではうまくいかない場面でフロック形成をアシストする製品も存在します。
凝集助剤の利用にあたっても、現場での試験(ジャーテスト等)が重要です。汚泥の種類や水質によって最適な助剤や添加順序が異なるため、主剤との相性を確認しながら導入する必要があります。例えば先に無機助剤を添加してから高分子凝集剤を加える場合と、その逆の順序とで結果が変わることもあります。また過剰な助剤投入はコスト増になるだけでなく場合によっては処理水を再汚濁させかねないため、効果が頭打ちになる適量を見極めて使うことが肝心です。
以上のように、薬剤面では「適切な凝集剤を、適切な量だけ、適切な方法で使う」ことが脱水効率向上のポイントです。凝集剤メーカーや水処理専門企業の知見を取り入れ、最新の高性能薬剤や助剤の活用、さらには自動制御技術を組み合わせることで、今までより格段にドライな(乾いた)脱水ケーキを得る余地は十分にあります。薬剤条件の最適化は処理コスト削減にも直結しますので、現状「汚泥ケーキの含水率が高い」「脱水処理後のコスト負担が大きい」などの課題があれば、一度専門家に相談してみる価値があるでしょう。
脱水処理の自動化|含水率監視・薬剤注入制御システム
近年、IoT技術やAIの進展により、汚泥脱水プロセスの自動化・高度制御が実用化されつつあります。脱水処理の自動化とは、センサーでリアルタイムに汚泥や装置の状態を計測し、それに基づいて装置の運転条件や薬剤注入量をコンピュータが自動的に最適調整する仕組みです。これにより、人手による勘と経験に頼った操作から解放され、常に安定した脱水性能を維持できるようになります。
含水率センサーによる自動制御: 脱水ケーキの含水率を下げ安定させるため、直接ケーキの水分をモニターして機械を制御するシステムがあります。例えばスクリュープレス脱水機の出口に連続測定式の水分センサーを設置し、排出されるケーキの含水率を常時計測します。センサー値に応じて背圧板(出口絞り)の圧力やスクリューの回転数を自動調節し、含水率が所定値(例えば70%以下)になるようリアルタイムでフィードバック制御を行います。含水率が高めに傾くと圧縮時間を延ばしたり回転を遅くしたりして絞りを強化し、逆に低くなりすぎると処理量優先でスループットを上げる、といった調整が人手を介さず行われます。これにより、季節変動や汚泥性状の変化があっても常に安定した乾燥度のケーキを得ることができ、焼却炉での安定燃焼や製品化する場合の品質確保に寄与します。
薬剤注入の自動制御: 前節で触れたポリマー注入量の最適化も、自動化技術が活用されています。下水処理場などでは、汚泥中の固形物濃度(%固形分)や脱水機からの分離水の水質指標(濁度や電気的特性)をオンラインで測定し、ポリマーの添加率をリアルタイムで調整するシステムが導入されています。具体的には、分離液中に残る微粒子の電荷量を測定し、それがマイナス方向なら「凝集剤不足」と判断して注入量を増やし、プラス方向なら「凝集剤過剰」とみなして減らす、といった制御が行われます。東京都の下水汚泥処理プラントで試験導入されたシステムでは、長期間の自動運転で常に適正注入が維持され、含水率の安定化とポリマー薬品コストの削減に成功したと報告されています。また最新の研究では、画像センサーで凝集状態をモニタリングしながらAIが最適薬注率を判断する技術も開発されています。これらの自動制御は、オペレーターの経験に頼る調整をデジタル技術で置き換えるもので、作業負担の軽減(人手不足対策)や運転データの蓄積による更なる最適化にもつながっています。
AIによる脱水機運転の最適化: 産業用遠心分離機メーカー等からは、AIを活用した高度な運転最適化システムも提供されています。例えば巴工業株式会社の「CentNIO(セントニオ)」は、遠心脱水機に搭載したカメラ映像や各種センサーの数値をAIが解析し、スクリューの差動速度や供給量などの設定を自動でチューニングするシステムです。熟練技術者が24時間付き添って細やかに操作しているのと同等の運転制御を目指したもので、2021年に販売開始されました。AIが含水率の低減や処理量の最大化などユーザーが設定した優先目標に従って遠心分離機を制御し、常に最大の性能を発揮できるようにします。その結果、遠心機の電力消費削減(負荷に応じた最適回転)、薬品添加の最適化、処理量アップによる生産性向上など、トータルのコストダウンと処理効率向上が実現できます。さらに遠隔監視や予兆保全(異常検知によるメンテナンス通知)機能も備えており、人手不足対策や安定稼働にも寄与する最新技術です。
このように、脱水処理の自動化・高度制御は着実に進歩しており、大規模プラントから中小規模施設まで普及が期待されています。導入にはコストもかかりますが、含水率低減による廃棄物量削減や薬品・エネルギー節減、人件費の圧縮など長期的メリットは大きいため、将来的には標準となっていくでしょう。現時点でも、脱水機メーカーや水処理エンジニアリング各社に相談すれば現場に適した自動化ソリューションを提案してもらえるはずです。
アクトの脱水処理改善実績|脱水効率向上と処理コスト削減の成功事例
最後に、株式会社アクトの技術を活かした脱水処理改善の事例を紹介します。アクトの無機系凝集剤「水夢(すいむ)」シリーズは非常に多彩なラインナップを有し、処理対象の汚水・廃液の種類や性質に合わせて最適なタイプを選べる点が大きな強みです。同業他社では数種類程度しか製品を持たないことも多い中、アクトの水夢シリーズは用途別・汚泥性状別に数十種類ものバリエーションが揃っており、水性塗料やインキ用、食品工場排水用、セメント排水用など細かなニーズに対応可能です。これは長年にわたり顧客の要望に応じて配合を微調整し、多種多様な廃液処理に対応してきた結果であり、「他社製品では処理が難しかった排水が水夢でクリアになった」という成功例が多数報告されています。アクトでは顧客の排水サンプルを預かって無償の処理テストを行い、水夢シリーズの中から最適な品番を選定して提案するサービスを提供しています。必要に応じて水夢の組成配合をカスタマイズする柔軟な対応も可能であり、こうしたきめ細かな技術サポートが脱水・浄化処理の最適化に大きく寄与しています。
すでに前述した事例以外にも、アクトの手掛けた脱水効率向上の成功例が数多く存在します。例えば食品工場の汚泥脱水改善では、水夢と高分子凝集剤の二段併用によって含水率80%→75%へ低減、汚泥重量25%削減、処理コスト30%減という成果が得られました(本記事「食品工場の汚泥脱水」節で詳述)。また塗料製造廃液の処理では、水夢投入によって顔料スラッジがしっかり凝集・沈殿し、上澄みが下水放流可能な透明水となるレベルまで浄化。その結果、廃棄物量が激減しコスト大幅ダウンを実現するとともに、生成したフロックは水分含有が少なく脱水ケーキの乾燥度が向上するため、その後のフィルタープレス処理も効率化されました。このように、水夢を適切に活用することで「汚泥を減らしつつ水も綺麗にする」という一挙両得のソリューションが可能となっています。
さらにアクトでは、薬剤だけでなく装置面での提案も行っています。同社開発の小型凝集分離ろ過装置「ACT-200」は、1台で凝集→沈降分離→ろ過までの全工程を手軽に行えるコンパクトな装置です。幅750mm×奥行1,250mm×高さ1,800mmという省スペース設計ながら、一度に最大200リットルの廃液を処理可能で、専門知識がなくても簡単に使える手軽さが特徴です。水夢シリーズとの併用で、水性塗料廃液、水溶性切削液、洗浄排水、食品工場排水など様々な水溶性廃液に対応し、液体産業廃棄物を固形化して産廃量を削減します。実績として、ACT-200と水夢を導入した事例では処理コストを最大70%削減できたとの報告もあり、中小規模事業所の排水処理改善に威力を発揮しています。
薬剤分野では、水夢シリーズに加えてアルカリ中和剤「融夢(ゆうむ)」という製品も提供しています。融夢はコンクリートやモルタルなどの強アルカリ性排水(pH12前後)を安全かつ迅速に中和するための薬剤で、食品添加物由来の成分を用いることで劇物に該当しない安全性を実現しながらpH1相当の強酸性機能を持たせたものです。通常、高アルカリ排水の中和には硫酸や塩酸が使われますが、それらは劇物指定で取り扱いが難しく危険でした。融夢は作業者が手に触れても安全(ただし強酸なので注意は必要)な設計で、しかもpH12の排水1リットルをわずか2mlで中和できるほど少量で効果を発揮します。反応も速く、数分の攪拌で中和処理が完了するため、現場作業の負担軽減にもなります。実際の使用例では、まず汚水に水夢を添加して浮遊物を凝集除去し、その後に融夢を適量加えてpHを中和調整、最後に固形物を分離して放流するという手順で行えば、安全かつ確実に排水基準を満たす処理水が得られます。融夢は建設現場の生コン排水処理などで活躍しており、アルカリ排水処理の効率化と安全性向上に寄与しています。
以上、アクトの技術力を活用した脱水処理の改善事例を見てきました。共通して言えるのは、「現場ごとの課題を的確に分析し、最適な薬剤とプロセスを組み合わせることで、脱水効率の飛躍的向上とコスト削減が実現できる」ということです。汚泥処理の悩みは千差万別ですが、「汚泥が減らない」「含水率が高くて困る」「処理コストがかさむ」といった課題に対して、適切な凝集剤や装置の導入で解決できる余地は大いにあります。株式会社アクトはそうした課題解決のために無料テストや技術提案を通じて最適なソリューションを提供しています。脱水処理の効率化やコスト低減でお困りの際は、ぜひ専門企業のノウハウも活用しながら、自社にベストな脱水技術を選定・導入してみてください。汚泥の減量と水環境保全、そして経済性の向上を同時に達成する道がきっと開けるはずです。

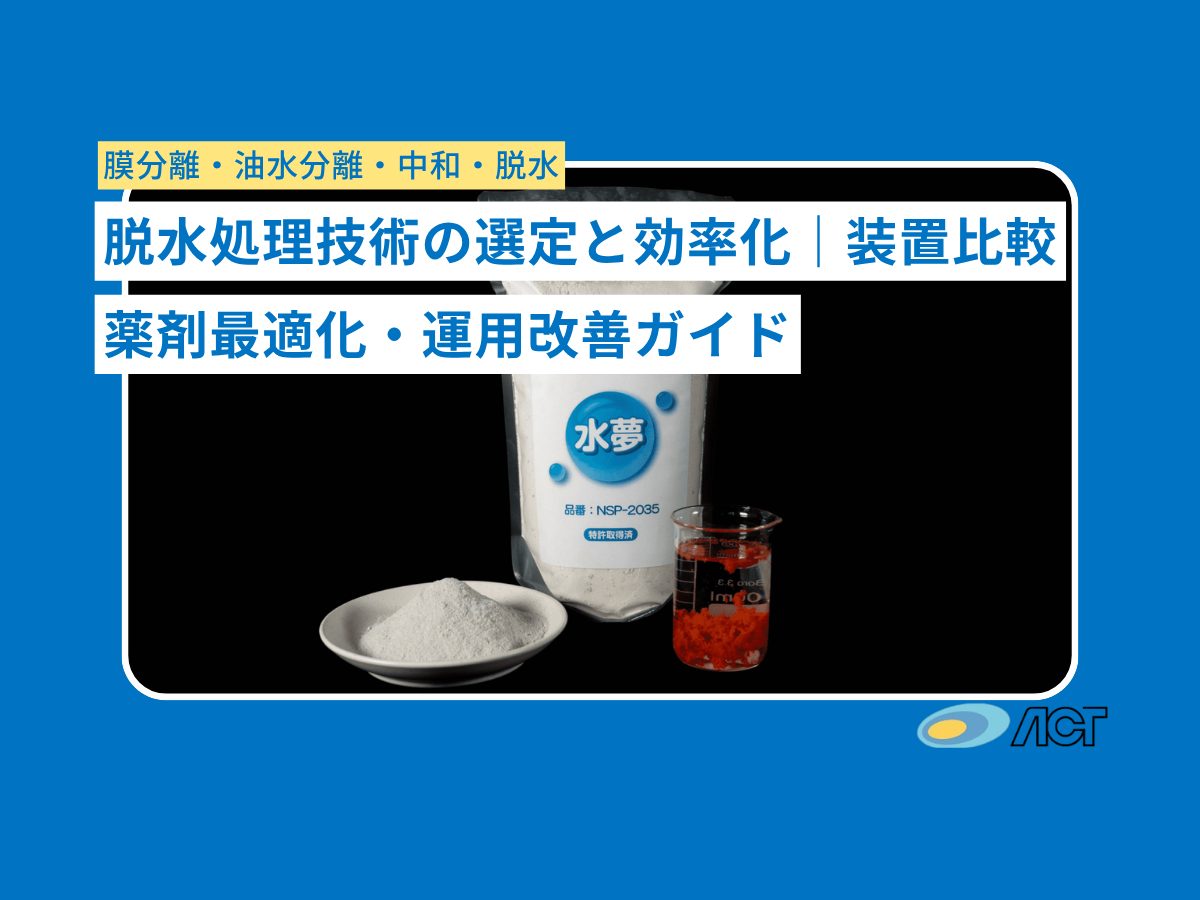
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)