工場や研究施設で不可欠な純水とは、自然の水や水道水から不純物を取り除いた水のことです。明確な定義はありませんが、水質の指標として電気抵抗率(電気の通りにくさ)が用いられ、0.1~1.5MΩ・cm程度の抵抗率が純水の目安とされています。純水は不純物が極めて少ないため「腐食性」が強く、金属を溶かしやすい特性もあります。このガイドでは、純水の基本概念から製造技術、システム設計、品質管理、メンテナンスまでをわかりやすく解説します。純水の製造や設備導入を検討する工場・事業所の担当者の方はぜひ参考にしてください。
純水の基本概念|水質基準・用途別要求品質・製造プロセスの理解
純水とは不純物を極力取り除いた水で、その純度は主に電気伝導率(抵抗率)で評価されます。不純物(イオン)が少ないほど電気が流れにくくなるため、抵抗率が高いほど水が純粋である目安になります。例えば、一般的な水道水の抵抗率が数千Ω・cm程度であるのに対し、純水は数百万Ω・cm(数MΩ・cm)にも達します。また、半導体製造などで使われる超純水では25℃で18.2MΩ・cm(理論純水に近い限界値)という非常に高い抵抗率が要求されます。
用途に応じた要求水質も異なります。純水は幅広い産業・研究分野で利用されており、代表的な用途として以下が挙げられます:
- 電子・精密分野(半導体洗浄など):半導体ウェハー洗浄や実験器具の洗浄には極めて純度の高い水が必要です。微量の不純物でも製品不良や実験結果の誤差につながるため、超純水レベルの水質が要求されます。
- ボイラー給水・加湿用途:ボイラー内の腐食や加湿器内の堆積物(スケール)を防ぐため、イオン分を除去した純水が用いられます。硬度成分を含まない水により、配管や機器の寿命延長・メンテ低減につながります。
- 食品・飲料製造:製品の風味や品質を安定させるため、製造用水として純水が使用されます。不純物や微生物を含まない水により、雑味のない安定した品質の食品・飲料生産が可能です。
- 実験・医療用途:分析試験や製薬プロセスでは、試料を汚染しない精製水(純水)が不可欠です。不純物を取り除いた水を用いることで、実験結果の信頼性・再現性を確保できます。
こうした用途別の要求品質を満たすため、純水製造プロセスでは通常、多段階の処理を組み合わせます。一般に「前処理 → 主処理 → 後処理」という段階構成で設計され、原水中の様々な不純物を段階的に除去していきます。前処理で大まかな不純物負荷を下げ、主処理で目的の純度まで精製し、後処理と配管設計で品質維持と供給の安定化を図るのが基本思想です。次章では、純水を得るための代表的な技術とそれぞれの特徴について比較解説します。
純水製造技術の種類|RO膜・イオン交換・EDI・蒸留の比較と選定
純水を製造する方法にはさまざまな技術があります。代表的なものに逆浸透膜(RO)法、イオン交換法、電気再生式イオン脱塩(EDI)法、蒸留法があり、それぞれ原理や長所・短所が異なります。目的とする水質や運用条件に応じて最適な方式を選定することが重要です。以下に各技術の特徴を比較します。
- RO膜法(逆浸透膜法):半透膜に高圧をかけ、水分子のみを透過させて他の不純物をほぼすべて除去する方法です。溶解したイオン類の90%以上、有機物や微粒子・微生物も94~99%除去できる高性能なろ過技術です。前処理で塩素や懸濁物質を除去すれば膜の長寿命化が図れます。メリットは、大量の水を比較的低ランニングコストで処理でき、メンテナンスが膜の定期交換程度と容易な点です。デメリットは、原水の一部が高濃度の濃縮排水となり廃棄されること、高圧ポンプの動力が必要なこと、膜ファウリング(汚染)により処理水量や水質が低下し得ることです。
- イオン交換法:陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を用い、水中のイオンをそれぞれH⁺(水素イオン)やOH⁻(水酸化物イオン)と交換除去する方法です。生成されたH⁺とOH⁻は水(H₂O)になるため、新たな不純物を残さず高純度の水が得られます。メリットは、装置構造が比較的シンプルで水を流すだけで純水を得られる扱いやすさ、そして電気などのエネルギー投入が不要な省エネ性です。一方デメリットとして、樹脂の交換基が飽和すると徐々にイオン除去性能が低下するため定期的な再生処理(強酸・強アルカリ薬品による樹脂再生)が必要になります。再生作業の手間や薬品管理コスト、再生排水の処理が課題です。また樹脂では有機物や微生物は除去できず、逆に樹脂が微生物の温床となり精製水が汚染されるリスクもあります。
- EDI法(連続電気脱イオン):上記イオン交換を電気の力で連続的に行う先進的な方法です。RO膜で予めイオンを大幅に減らした水をEDIモジュールに通し、内部のイオン交換樹脂で残留イオンを捕捉しつつ電圧をかけて樹脂を同時再生します。この電気透析的プロセスにより、薬品を使わず自動で樹脂が再生されるため、常に安定した脱塩性能が維持できます。メリットは、薬品再生が不要で運転コストや手間を大幅削減できること、高純度の純水を連続的に得られることです。実際、RO+EDIを組み合わせた装置では生成水の抵抗率が15MΩ・cm程度に達し、従来法より不純物を少なくできる報告があります。デメリットとして、EDIは前段のROできちんとイオンを減らし硬度や二酸化炭素を除去しておかないとスケーリングや性能低下を起こすため前処理水質管理が重要です。また初期設備コストが高めであり、小規模用途には不向きな場合もあります。
- 蒸留法:水を加熱して水蒸気にし、冷却して純水だけを凝縮・回収する伝統的な精製法です。不揮発性の不純物(無機塩や高沸点有機物など)は沸騰残渣に残り、蒸発しないため分離されます。蒸留によりイオン分はもちろん、有機物や微粒子、微生物まで除去可能で、高純度の水が得られます。この方法のメリットは、原理がシンプルで安定した水質を得やすく、加熱により殺菌効果も期待できる点です。デメリットは、大量の熱エネルギーと時間を要するため処理効率が低く、大量の純水を必要とする用途には不経済なことです。また水と沸点が近い物質(例えば一部の有機溶剤など)は完全には除去できない場合があります。蒸留法単独では抵抗率0.5~0.8MΩ程度の純水しか得られませんが、蒸留後にイオン交換を組み合わせることで1~10MΩ・cmまで水質を向上できる例もあります。したがって蒸留は主に実験室や医療用の限られた水量需要に適し、大規模プラントでは補助的手段か過去の技術となりつつあります。
以上のように各方式で除去できる不純物の種類やコスト・メンテ性が異なります。装置選定のポイントは、求める純水水質(イオン濃度レベル、有機物・菌の管理レベル)と必要水量、運用コスト・管理体制を総合的に考慮することです。たとえば「毎時数トン規模で純水を供給したいが超純水レベルまでは不要」という工場なら、RO膜で大部分のイオンを除去し、後段に混床イオン交換やEDIで仕上げる方式が効率的です。一方「研究室で少量でも最高純度の水が必要」という場合は、市販のRO+EDI内蔵の純水装置や蒸留+カートリッジ式精製水装置が適するでしょう。用途に応じて各技術の適材適所で最適な純水システムを設計することが大切です。
純水システムの設計|前処理・主処理・後処理・配管設計の最適化
高品質な純水を安定供給するには、システム全体の設計最適化が重要です。ここでは純水製造プラントを構成する前処理・主処理・後処理各工程の役割と、品質維持の要である配管設計のポイントを解説します。
- 前処理(プリートリートメント):原水中の粗ゴミや塩素、硬度成分など主処理装置に負荷をかける要因を事前に取り除く工程です。例えば井戸水や工業用水には砂や鉄サビなどの懸濁物が含まれるため、多層ろ過砂フィルターやマイクロフィルターで除去します。また、水道水には殺菌用の残留塩素が含まれRO膜やイオン交換樹脂を劣化させるため、活性炭フィルターで脱塩素します。硬度(カルシウム・マグネシウム)はRO膜のスケーリング原因となるため、イオン交換式の軟水器で軟化したり、薬剤添加(スケール防止剤)で沈殿を抑制します。前処理を適切に行うことで、後段の主処理が効率良く働き、装置の寿命やメンテナンス間隔も延びます。
- 主処理(メインプロセス):純水化の中核工程で、前処理水から目的の純度の水を作ります。主処理には前章で述べたようなRO膜ユニットやイオン交換装置、EDIユニットなどが用いられます。一般的な純水プラントでは、まずRO膜装置で一段階大きな不純物除去を行い(塩類90%以上除去)、その後にイオン交換樹脂塔やEDIモジュールで微量イオンまで除去して所要の抵抗率まで高める二段構成が多く採用されています。必要に応じてROを二段直列(二段RO)にして脱塩率をさらに向上させたり、RO後に二つの樹脂塔(陽イオン床+陰イオン床)を連続配置して完全除塵する方式もあります。蒸留法を併用するシステムでは、蒸留器で精製した後に混床イオン交換樹脂やRO膜で仕上げ純水を作るケースもあります。主処理工程の設計では、原水水質と目標純度から逆算して工程組み合わせを決定し、各ユニットの処理能力に余裕を持たせてピーク需要時でも安定供給できるようにします。
- 後処理(ポリッシング&貯留):主処理を経て得られた純水を保存・供給する段階です。必要に応じてさらなる精製や品質保持対策を行います。例えば半導体や医薬用途向けには、純水タンクに紫外線殺菌装置(UV)を設置して残留有機物をUV酸化分解(TOC削減)するとともに、細菌繁殖を抑制します。さらに供給直前には精密フィルター(0.2μm以下の孔径)やUF膜を通し、配管内で発生した微粒子や菌類を捕捉して供給します。純水をタンクに貯留する場合、タンク内の水質劣化を防ぐため撹拌循環や窒素封入、ベントフィルターによる清浄空気管理を行います。超純水システムではタンクレスで連続製造・循環供給する方式も採用されますが、需要変動に応じた安定供給には一定容量のタンク設置が一般的です。
- 配管設計の最適化:純水は製造後の配管輸送中に不純物を溶出・混入しやすいため、配管材料・方式の選定や設置施工にも細心の注意が必要です。配管材にはステンレススチール(SUS316Lなど)や高純度樹脂配管(硬質塩ビのクリーンPVC、PFA樹脂など)が用いられます。特に近年は施工性とコストに優れたクリーンPVCが多く採用されており、通常の塩ビ管に比べイオンや有機炭素の溶出が極めて少ない専用品です。接合も接着剤を使わず溶着接合することで有機物混入を防いでいます。また配管内の滞留防止も品質維持の重要ポイントです。末端の使用ポイントまでリング状に配管を巡らせて常に循環させるループ配管方式を採用し、どの分岐でも最低流速を確保して停滞を防ぎます。さらに、配管施工時にはパージ洗浄やクリーン施工を徹底し、油分や塵埃の持ち込みを排除します。配管設計の工夫により、「製造した時が一番水質が良く、配っているうちに徐々に汚染される」という事態を避け、ユーザーポイントにおいても高純度を維持できる純水供給を実現します。
純水品質の管理|導電率・TOC・微生物・粒子数の監視と制御
純水システムを安定運用するには、水質モニタリングと適切な制御が欠かせません。純水・超純水の品質指標として代表的なものに電気伝導率(抵抗率)、TOC、微生物数、粒子数があります。それぞれの意味と管理方法を解説します。
- 導電率(抵抗率):水中のイオン量を反映する指標で、純水の純度を表す基本指標です。導電率が低い(抵抗率が高い)ほどイオン性不純物が少ないことを示します。一般的な純水装置ではオンラインの導電率計(または抵抗率計)でリアルタイム監視し、目標値以下に維持します。例えば電子産業向け超純水では18MΩ・cm以上(25℃換算)の抵抗率が求められ、わずかppbレベルの金属イオン混入でも17MΩ程度に低下してしまうほど管理基準が厳格です。抵抗率の低下が見られた場合、イオン交換樹脂の劣化・飽和や膜の損傷を疑い、早期に対処します。
- TOC(全有機炭素):水中に溶解する有機物汚染の総量を表す指標です。イオンにはならない有機化合物(微生物由来の有機物、腐食防止剤や樹脂からの溶出成分など)は導電率には現れないため、超純水ではTOC測定が重要です。超純水ではTOC数ppb以下が要求され、オンラインTOC計(紫外線酸化-NDIR検出法等)で連続監視します。TOC値が上昇した場合、前処理活性炭の消耗やUVランプの故障、有機汚染の混入を疑って対策を行います。特に製薬用水ではTOC管理が法規制されており、各国薬局方の基準内(例えば日本薬局方では注射用水TOC < 500 ppb等)に維持する必要があります。
- 微生物(生菌数):純水中の細菌・真菌など微生物の数を指します。一般工業用途では極端に厳しい基準は設けられていないこともありますが、医薬品や半導体では1mLあたり1個未満といった厳格な管理値が設定されています。微生物は配管内でバイオフィルムを形成すると急激に増殖するため、日常的な殺菌対策が必要です。定期的な水質検査(培地培養による生菌数測定)に加え、UV殺菌装置の活用、定期的な配管の熱水殺菌・薬品殺菌(オゾン水や過酸化水素の循環など)を行います。生菌数の増加が確認された場合、配管デッドレッグの解消やタンクの清掃・殺菌を実施し、再発防止策を講じます。
- 粒子数(パーティクルカウント):水中に浮遊する微粒子(不溶性微粒子)の個数濃度です。半導体の洗浄工程などでは、粒子が製品歩留まりに直結するため、0.1μmサイズで1リットル中数個以下という厳しい管理が行われています。粒子カウンター(光学式粒子計測器)で連続監視し、粒子数増加時にはフィルターの交換や洗浄度の点検を行います。純水システムでは、配管やタンクから微粒子が剥離・混入しないよう素材選定・表面仕上げが重要であり、前述のクリーン配管や循環設計も粒子対策の一環です。粒子数管理は超純水領域では必須ですが、一般的なボイラー用純水などではここまで厳密に測定しないケースもあります。用途に合わせて適切な頻度・基準で粒子モニタを設置します。
以上のような主要指標に加え、シリカ濃度(SiO₂)や溶存酸素量、エンドトキシン(内毒素)など特殊な項目を管理する場合もあります。純水品質を総合的に監視し、異常の早期検知と是正措置を行うことが安定運用のカギです。水質管理を徹底することで、不良発生の防止や製造プロセスの信頼性向上に大きく貢献します。
純水システムのメンテナンス|膜交換・樹脂再生・清浄化・予防保全
純水製造システムを長期にわたり安定稼働させるには、計画的なメンテナンスと予防保全が不可欠です。主なメンテナンス項目とポイントを解説します。
- RO膜の点検・交換・洗浄:RO膜は経年劣化やファウリング(汚れ蓄積)によって性能が低下します。膜が劣化すると透過水のイオン除去率が急激に低下し、水質悪化や処理量減少を招きます。そこで定期的に膜差圧や透過流量を監視し、ファウリング兆候があればCIP(定置洗浄)を実施します。スケーリングには酸洗浄、有機汚れにはアルカリ洗浄や酵素洗浄など汚染物質に応じた洗浄剤を循環させ膜をクリーンアップします。十分な回復が見込めない膜は数年おきに新品交換し、常に高い脱塩性能を維持します。また、前処理の活性炭やカートリッジフィルターも定期交換し、RO膜に負荷をかけないよう管理します。
- イオン交換樹脂の再生・交換:イオン交換装置では、樹脂の交換基が飽和したら再生処理が必要です。定期的(例えば数日に一度など)に塩酸や苛性ソーダを逆流通させ、吸着したイオンを洗い流して樹脂をH⁺/OH⁻型に復元します。再生条件(薬品濃度や接触時間)を最適化することで再生効率を高め、薬品使用量やランニングコストの低減を図ります。しかし樹脂自体も経年で劣化し、架橋構造の崩壊や有機汚染による性能低下が起こるため、数年毎に樹脂そのものの交換も考慮します。なお再生型ではなく、使い捨てカートリッジ型の小型純水器の場合は、カートリッジをメーカー推奨のサイクルで取り替えます。交換時期を過ぎて水質が悪化してからではなく、予防的な交換が安定稼働のコツです。
- 定期清浄化・殺菌:純水システム内のタンクや配管、EDIモジュールなどは、長期間運転していると微生物のバイオフィルムや汚れが付着します。そこで定期清浄化として、年に数回は系内に殺菌剤(次亜塩素酸やオゾン、過酸化水素など)を満たして一定時間循環させるCIP殺菌を行います。RO膜は塩素に弱いので、前段のみ殺菌し後段は別途ホットウォーターサニタイズ(温水殺菌)を行うケースもあります。タンクは内部を洗浄・消毒し、エアフィルターも交換します。これら清浄化作業により微生物汚染をリセットし、水質の長期安定化を図ります。
- 予防保全と点検:機器故障や水質トラブルを未然に防ぐため、日常点検と定期点検を組み合わせて行います。日常点検では水質計測値(抵抗率・TOC等)や圧力計・流量計の値を確認し、異常な傾向がないか監視します。定期点検ではポンプやバルブの動作、計装センサーの校正、配管の漏れチェックなどを実施します。最近ではIoT監視により遠隔からリアルタイムで稼働状況を分析し、例えば膜の汚れ進行を傾向監視して最適な洗浄タイミングを予知保全することも可能です。計画的な予防保全により、突発的なダウンタイムを防ぎ、常に安定稼働・安定供給を維持します。
以上のように、純水設備は「作って終わり」ではなく「維持して育てる」視点が重要です。

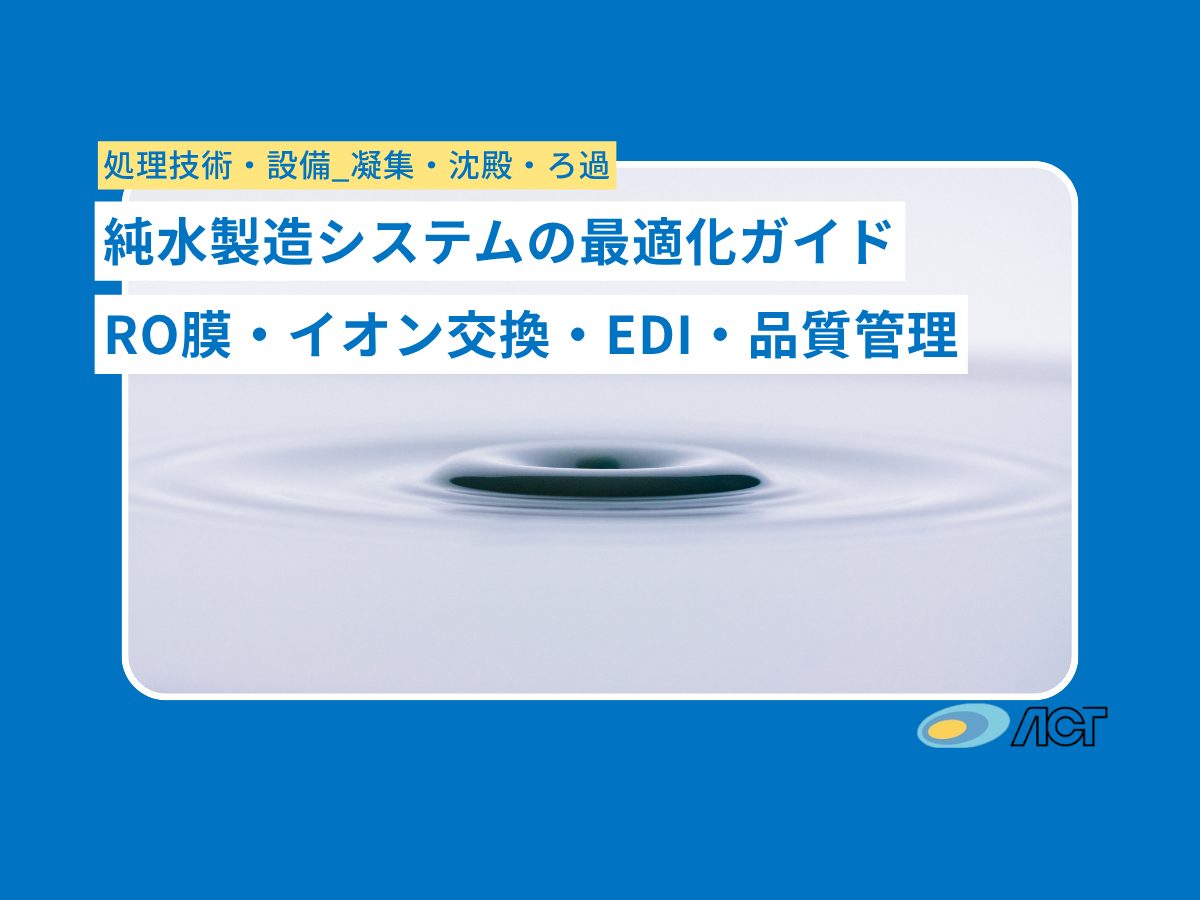
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)