工場や施設で発生する排水を効率的に処理し、高品質な再利用水を得る方法として膜分離技術が注目されています。膜分離は、水を特殊な半透膜(非常に細かいフィルター)に通して不純物を除去する技術です。膜の孔径(細孔の大きさ)によって除去できる物質の大きさが異なり、精密ろ過膜(MF)、限外ろ過膜(UF)、ナノろ過膜(NF)、逆浸透膜(RO)といった種類があります。本記事では、膜分離の基本原理から各膜種の特徴、業界別の活用事例、そしてファウリング(膜汚染)対策や省エネルギー運転のポイントまで、排水管理担当者の方にも分かりやすく解説します。また、株式会社アクトの技術力や導入事例を交え、最適な膜分離システム選定と運用のヒントをご提供します。
膜分離の基本原理|分子サイズによる分離メカニズムと膜の種類
膜分離の基本原理は「サイズによるふるい分け」です。半透膜には微細な孔(あな)が多数開いており、水など溶媒の分子は通しますが、大きな分子や粒子は通しません。膜の孔径サイズはマイクロメートル(μm)からナノメートル(nm)オーダーに及び、水中の不純物を分子サイズで選択的に分離します。例えば、直径1μm(1ミクロン)は1mmの1,000分の1ですが、膜分離技術ではさらにその1/100~1/1,000程度のナノスケールの孔も利用します。孔径によって捕捉できる物質のサイズが決まるため、「膜種の選定=除去対象のサイズに合わせた膜の選択」と言えます。
膜の種類は一般に大きな孔から順にMF膜(Microfiltration:精密ろ過膜)、UF膜(Ultrafiltration:限外ろ過膜)、NF膜(Nanofiltration:ナノろ過膜)、RO膜(Reverse Osmosis:逆浸透膜)の4種に大別されます。MFやUFは比較的孔径が大きく主に物理的な濾過(フィルター効果)で分離します。一方、NFやROは極めて小さい孔(RO膜は実質的に孔がないとも言われます)で溶解した塩類イオンまでも分離可能ですが、そのメカニズムは“逆浸透”と呼ばれ、水分子だけを選択透過させる現象を利用しています。RO膜では高い圧力を加えて水に溶けた塩類を押し戻し、水だけを通すことで脱塩を行います。このように膜分離は分子サイズの違いを利用した高度な濾過技術であり、目的に応じて適切な膜種を選定することが重要です。
膜の素材には主に高分子(ポリマー)製の有機膜と、セラミックなどの無機膜があります。有機膜は比較的安価で広く使われ、無機膜は耐熱性・耐薬品性に優れ洗浄しやすい利点があります。また膜モジュールの形状も様々で、中空糸膜(ストロー状の繊維を束ねたもの)や平膜(シート状の膜を積層したもの)、スパイラル型(シートを巻き付けたもの)などがあります。膜分離システムでは、これら膜モジュールをいくつも組み合わせて必要な処理能力を確保します。
ポイントまとめ – 膜分離の基礎
- 半透膜による分子サイズ分離: ナノ~マイクロメートルの微細孔が、不純物をサイズでより分ける。孔径が小さいほど微細な物質まで除去可能。
- 膜の代表的種類: MF(精密ろ過)、UF(限外ろ過)、NF(ナノろ過)、RO(逆浸透)の4種類。孔径の大きいMF→小さいROの順で除去対象が微細化する。
- 各膜の原理: MF/UFは物理的フィルター効果、NF/ROは一部イオンも除去でき逆浸透現象を利用。ROは事実上あらゆる溶解成分を99%以上除去可能。
- 留意点: 膜は高品質な処理水を得られる一方、圧力駆動のためエネルギー消費が大きく、膜孔の目詰まり(ファウリング)対策が必要。これらメリット・デメリットを踏まえて膜種選定とプロセス設計を行うことが重要です。
膜の種類と特徴|MF・UF・NF・RO膜の分離性能と適用範囲
膜分離技術で使われる代表的な膜4種類について、その分離性能(除去できる物質)と適用範囲を詳しく見てみましょう。各膜種ごとに特徴を整理します。
- MF膜(精密ろ過膜): 一般に孔径が約0.1~数μmと最も大きく、細菌・微生物、懸濁物質(SS)、微粒子の除去に適します。ろ過のイメージとしては砂ろ過の延長のような物理的なこし取りです。MF膜は処理水量が多い用途に向いており、上水道の高度処理や下水・産業排水の再利用、飲料や食品のろ過工程などで広く使われます。例えばビールやワインの無菌ろ過(熱殺菌の代わりに酵母や雑菌を膜で取り除く)や、半導体工場の超純水製造工程で微粒子を除去する最終フィルターとして利用されています。MF膜単独ではウイルスなど極小の物質は除去困難ですが、その分運転に必要な圧力が低くエネルギー消費が小さいメリットがあります。
- UF膜(限外ろ過膜): MF膜より細かい孔(おおむね2~100nm程度)を持ち、ウイルスやコロイド状物質、タンパク質など高分子の分離が可能です。身近な例では人工透析に使われるフィルターや、食品工業での乳清中のタンパク質濃縮などにUF膜が活躍しています。また水処理分野では、MFではすり抜けてしまう微小な濁質や有機物を除去する目的で用いられます。例えば紙・パルプ工場の排水から微細な繊維や有機コロイドを除去したり、上水処理の高度濾過で濁度を下げる用途です。UF膜は単独で使われることは少なく、RO膜の前処理やMF膜後の精密濾過など他の工程と組み合わせて使われるケースが多いです。MFと比べ圧力がやや高く必要になりますが、それでもROより低圧で運転でき、比較的広範な用途に利用されています。
- NF膜(ナノろ過膜): 孔径がさらに小さい2nm未満の膜で、性質的には「ゆるいRO膜」とも言われます。二価の無機イオン(例: Ca^2+やMg^2+など硬度成分)や一部の有機分子を除去できるのが特徴です。例えば地下水や工業用水の硬度(カルシウムやマグネシウム)を下げる軟化処理や、RO海水淡水化の前処理でスケーリング原因の硫酸イオンを減らす用途に使われています。農薬や有機汚染物質の一部除去にも効果があり、飲料水中の微量有機物対策や製薬業界での純水製造などにも利用されます。NF膜はROほど完全には塩を除かないため通過水にわずかにイオンを残しますが、その分ROより低い圧力で運転できる場合もあり、省エネ的な利点もあります。
- RO膜(逆浸透膜): 膜分離技術で最も精密な膜です。実質的に水分子以外は通さないとされ、水中の溶解性塩類・イオンまで除去できます。代表例は海水の淡水化で、RO膜を使えば海水から真水だけを取り出し飲料水を製造できます。その他、電子産業で必要な超純水の製造や、ボイラー給水の脱塩、飲料や食品製造での高純度水製造など幅広く活用されています。RO膜の除去率は非常に高く、適切に使えばあらゆる不純物の99%以上を除去可能です。ただし性能が高い分、運転には高い圧力(数MPaオーダー、海水の場合50~70気圧程度)が必要でエネルギーコストが大きくなります。また極小の孔ゆえに無機塩のスケーリングや微生物・有機物の付着によるファウリングが発生しやすく、定期的な洗浄や高度なメンテナンスが求められます。
以上のように各膜には得意分野と適用範囲があります。MF/UF膜は懸濁物や細菌・ウイルス除去、NF膜は特定イオンや低分子有機物の除去、RO膜は完全な脱塩と、それぞれ役割が異なります。重要なのは、処理したい水質や達成したい水の純度レベルに応じて、適切な膜を選ぶことです。また必要に応じて複数の膜を組み合わせることも行われます。例えば「MFで大きな粒子を除去 → ROで脱塩」といった二段構成にすると、RO膜の負荷を下げつつ高品質な処理水を得ることができます。逆に、要求水質がそれほど高くない場合は高価なROを使わずMFやUFで十分なケースもあります。経済性とのバランスを見ながら、必要十分な水質を確保できる最適な膜プロセスを設計することが肝心です。
業界別膜分離システム|電子・医薬品・食品工業での高純度水製造事例
膜分離技術は様々な業界で純水・高純度水の製造や排水の再生利用に活用されています。ここでは代表的な電子産業、医薬品業界、食品・飲料産業の3分野における膜分離システムの活用事例とポイントを紹介します。それぞれの業界で要求される水質や用途が異なるため、求められる膜性能やシステム構成にも違いがあります。
電子産業における膜分離と超純水製造
半導体や液晶パネルなど電子産業では、製造プロセスで大量の超純水を使用します。超純水とは不純物濃度を極限まで低く抑えた水で、導電性を持つイオンや微粒子・微生物がほとんど含まれません。この超純水製造に膜分離システムが不可欠です。典型的なプロセスは、まずRO膜で水道水中の溶解塩類を99%以上除去し、その後イオン交換樹脂や電気脱イオン(EDI)で残留イオンを完全に取り除きます。さらにUF膜を用いて微粒子や微生物・ウイルスを捕捉し、最後に0.1μm以下のカートリッジフィルターで仕上げることで、超純水が得られます。例えば半導体工場の超純水プラントでは、RO膜の段階で導電率を大幅に下げ、その後の処理負荷を軽減しています。近年ではRO膜の性能向上により、以前は難しかったレベルの高純度化が可能となり、終端のRO膜を採用するケースも増えています。電子産業ではこのように複数の膜技術を組み合わせて超純水を製造し、結果として高い洗浄効果と製品歩留まり向上につなげています。
また、製造工程で使用した純水を回収して再生する取り組みも行われています。例えば洗浄後の排水をROで再度処理し、純水に戻して再利用することで水使用量を削減する事例があります。排水中の有機物分解には生物処理やオゾン処理を組み合わせ、最後にRO膜処理で高品質化する循環システムです。電子産業では水資源の有効活用と排水削減も重要課題であり、膜分離はそのソリューションとして大きな役割を果たしています。
医薬品業界における膜分離の活用
医薬品・製薬工場でも高品質な水が求められます。特に注射剤などの無菌製剤に使う注射用水(WFI)や、製造設備の洗浄用水は極めて厳しい水質基準があります。かつては注射用水の製造に多段蒸留が用いられてきましたが、近年ではRO膜とUV殺菌、UF膜などを組み合わせた膜法による精製水システムが採用されるケースが増えています。膜法は連続運転が可能でエネルギー効率も高く、一定の要件を満たせば公定書上も認められるようになりました。
製薬工場ではまずRO膜でイオンや有機物を大幅に除去し、後段のEDI装置や混床イオン交換樹脂で純水レベルまで精製します。その上で、UF膜(限外ろ過膜)を通水してエンドトキシンや微生物を除去し無菌性を確保する設計が一般的です。UF膜はウイルスサイズの物質もカットオフできるため、最終段でのウイルス・エンドトキシン除去フィルターとして有効です。このような多段階の膜処理により、医薬品製造用の水は高純度かつ無菌状態を維持します。
また、医薬品業界では環境規制への対応として排水処理にも膜が活用されています。例えば培養工程などから出る高BODの排水は活性汚泥法(生物処理)が用いられますが、膜分離活性汚泥法(MBR)にすることで処理水質を向上させ、従来の生物処理では残留する微生物や懸濁物も膜で截留できます。これにより放流水質をより安全なレベルに引き上げたり、場合によっては再利用水として設備洗浄などに回すことも可能です。医薬品工場では安定した処理水質と確実な除菌が重視されるため、膜分離技術が品質保証と環境対応の両面で貢献しています。
食品・飲料産業における膜分離の活用
食品や飲料の製造現場でも、膜技術の導入が進んでいます。まず製品そのものに使用する水の高度処理です。清涼飲料水やビールなどでは水道水を原料としますが、味や品質の均一化のためにRO膜ろ過でミネラル分を調整したり、不純物を除去することがあります。RO処理した水はほぼ純水になるため、そこに必要なミネラルを添加して製品に適した組成に調整することで、地域によらず安定した製品品質を確保できます。またお茶や炭酸飲料では原水由来のにおいや有機物を除去する目的で活性炭処理と膜ろ過を組み合わせる例もあります。
次に製造プロセスでの膜利用です。食品工場では加熱殺菌できない生産工程において、微生物除去のための膜ろ過(精密ろ過)が活用されています。例えばビールの瓶詰め時にMF膜で酵母や雑菌をろ過除去し、熱をかけずに生ビールの風味を保持したまま殺菌と同等の効果を得る「膜ろ過ビール」の製造があります。ワインや果汁でも風味を損なわないコールドろ過に膜が使われていますt。また乳製品分野ではUF膜で牛乳中のタンパク質を濃縮したり、NF/RO膜で乳清からラクトースやミネラルを分離回収するなど、成分の分離・濃縮にも膜技術が応用されています。
さらに、食品工業では大量の洗浄水や冷却水が必要ですが、水資源の制約やコスト増大への対策として排水の再利用にも膜が役立ちます。食品工場の排水は有機物や油分を含むことがありますが、凝集沈殿や生物処理で一次処理した後に膜ろ過で仕上げ処理することで、洗浄用途などに再利用できるレベルまで浄化する試みもあります。ある食品工場では、洗浄排水をMF膜で処理して濁度を下げ、殺菌後に工場内のトイレ用水やボイラー給水補助に回すことで、水道代を削減した例も報告されています。食品・飲料産業では製品品質への直接影響が大きいため、安全・安心を支える技術として膜分離が欠かせません。
ファウリング対策と膜寿命延長|前処理・洗浄・交換の最適化
膜分離システムの運用上最大の課題の一つがファウリング(膜の汚れ・目詰まり)です。原水中の懸濁物質、コロイド、スケール成分、微生物などが膜表面や孔内部に付着・蓄積すると、透過流量が低下し圧力損失が増大します。その結果、所定の水量を得るためにより高い圧力が必要になり、エネルギーコストが上昇したり、最終的には膜が使用不能になります。ファウリングをいかに抑制し、膜の寿命を延ばすかが運用最適化の鍵です。
主なファウリング対策として以下のポイントが挙げられます:
- 前処理の徹底: 原水中の懸濁物や有機物をあらかじめ取り除いておくことで、膜への負荷を低減できます。例えばスクリーンろ過や砂ろ過で大きな粒子を除去し、さらに凝集沈殿処理で微細な粒子やコロイドを取り除くことが効果的です。凝集処理では無機系凝集剤を加えて汚濁粒子をフロック(塊)にまとめて沈降・ろ過除去します。アクトが提供する無機凝集剤「水夢(すいむ)」シリーズは、排水ごとに適切な薬剤組成をカスタマイズでき、凝集しにくい特殊な汚染物質でも効率よく除去可能です。例えば水性塗料廃水中の特殊顔料に対し、市販凝集剤では処理困難だったものを水夢SP-4004Vでフロック化除去し、後段フィルターの目詰まりを防止したケースがあります。このように適切な前処理で膜汚染物質を減らすことがファウリング抑制の第一歩です。
- 運転条件の最適化: 膜ろ過の運転パラメータ(ろ過速度、圧力、クロスフロー流速など)を適切に設定することも重要です。例えばクロスフロー(膜面に沿って水を流す方式)で運転すれば膜表面に堆積する汚れを随時洗い流せるため、デッドエンド(一方向ろ過)よりファウリングが緩和されます。また回収率(供給水に対する産出水の割合)を欲張りすぎないことも大切です。回収率を高くしようと排水を減らすと、濃縮側の濃度が上がり膜表面でのスケーリングやバイオファウリングが進みやすくなります。その結果、浄水の質が低下したり、同じ造水量を得るのに必要圧力が上昇してエネルギーコストが増大する恐れがあります。一般にブライン(濃縮水)の濃度が一定以上高くならないよう適切な回収率に制御し、必要に応じ濃縮水の一部を再循環させる設計が有効です。以上より、「運転条件は高ければ高いほど良いわけではなく、膜システムの状況に応じた適切な設定が必要」と言われます。具体的には、膜メーカーや水処理エンジニアの知見を参考に、膜ごとの推奨範囲内で圧力・流量を調整しファウリングを抑える運転を心がけます。
- 定期洗浄(CIP)の実施: 膜の性能を維持するためには、定期的な洗浄によって付着汚れを除去することが欠かせません。MFやUF膜では一定時間運転ごとに逆洗(バックウォッシュ)を行い、膜に溜まった汚れを逆方向の水流で押し出します。さらに薬品洗浄として、アルカリ洗浄(有機物汚れの除去に有効)や酸洗浄(無機スケールの溶解除去に有効)、次亜塩素酸ソーダなどによる殺菌洗浄(バイオファウリング対策)を組み合わせますj。洗浄頻度の目安は、例えばUF膜であれば膜間差圧が所定値に達した時点、RO膜であれば透過流量が新品時の一定割合に低下した時点などがあります。定期洗浄を行うことで膜性能を回復させ、運転効率を維持できます。このように適切なメンテナンスサイクルを確立し、汚れが深刻化する前に対処することが膜寿命延長につながります。
- 膜交換の計画管理: 洗浄を繰り返しても性能が回復しなくなったら、膜モジュールを交換する必要があります。とくにRO/NF膜は化学洗浄による劣化が蓄積しやすく、MF/UF膜に比べ寿命が短い傾向があります。一般にはRO膜で3~5年、MF/UFで5~10年程度が更新目安と言われますが、これは水質や運用によって変動します。重要なのは性能モニタリングを行い、交換時期を見極めることです。例えば透過水量や透過水質(塩素イオン濃度など)のトレンドを監視し、劣化の兆候があれば計画的に交換します。新品膜と比較した劣化率を把握し、予備の膜を手配しておくなどの段取りも不可欠です。
以上のような対策を講じることで、膜分離システムの安定稼働期間を伸ばしトラブルを防ぐことができます。特に前処理(凝集剤の活用等)と運転条件の管理は初期ファウリングの抑制に大きく寄与し、結果的に洗浄頻度を下げ寿命延長につながります。膜技術は高度ですがデリケートな面もあるため、「汚さない工夫・早めの手当て」が肝心です。
膜分離システムの省エネルギー化|エネルギー回収・運転最適化
膜分離プロセス、とりわけROやNFは加圧によって水を透過させるため、運転には電力が必要です。大規模な海水淡水化プラントなどでは、エネルギーコストが運用全体の相当部分を占めることから、省エネルギー化が重要なテーマとなっています。ここでは膜システムの省エネに有効なエネルギー回収技術と運転の最適化について解説します。
エネルギー回収装置による省エネ
RO膜で海水を淡水化する場合、典型的な回収率は40~50%程度で、残りの高圧濃縮水(排水側)には依然として大量の圧力エネルギーが残っています。この排水側の余剰圧力を回収再利用するのがエネルギー回収装置(Energy Recovery Device: ERD)です。代表的なものに圧力交換器(Pressure Exchanger)があります。圧力交換器は高圧の濃縮水と低圧の原水を直接接触させ圧力エネルギーを移動させる仕組みで、最新の装置ではエネルギー回収効率90%以上にも達します。実際、世界中の海水淡水化プラントでこの技術が採用されており、年間39億ドル相当のエネルギーコスト削減に貢献しているとの報告もあります。ある大型設備では、圧力交換器の導入によって従来比最大60%ものエネルギー低減を実現した例もあり、今や業界標準の技術となっています。
他にもターボチャージャー式(ポンプとタービンを組み合わせたもの)やピストン式のエネルギー回収装置があり、いずれも高圧ポンプで加えたエネルギーをできるだけ無駄にしない工夫ですrix.co.jp。中小規模のシステムでは初期コストとの兼ね合いもありますが、エネルギー価格高騰やカーボンニュートラルの観点から、将来的にはさらに小型で安価な回収デバイスが普及していくでしょう。
運転の自動制御と最適化
省エネ化には、人為的なムダを省く賢い運転も欠かせません。例えば、ポンプにインバーター制御を導入し、必要な圧力・流量だけを供給するよう自動調整すれば、余分な電力を消費せずに済みます。実際に某メーカーのRO装置ではインバーター搭載ポンプで運転最適化を行い、無駄な加圧を抑制して省エネに貢献しています。また、運転モードの自動切替も有効です。需要が少ない時間帯には低流量モードに切り替えたり、必要に応じて複数ユニットを間欠運転することで、常にフル稼働させるよりエネルギーを節約できます。
膜システムのリアルタイム監視と制御も進んでいます。圧力や流量、透過水質などをセンサーで監視し、最適な範囲から外れそうになると自動で補正する制御ソフトが活用されています。例えば透過水の導電率が上昇した場合に自動フラッシング(膜面洗浄)を実施してファウリングを抑え、結果的にポンプ負荷増大を防ぐといった仕組みです。遠隔監視システムを導入すれば、異常があればすぐ検知して対応でき、トラブルによるエネルギーロスを最小化できます。
さらに、膜モジュールの最適配置も省エネにつながります。例えばRO膜を一段ではなく二段に配置し、途中で加圧を段階的に行うことで、一度にかける圧力を抑え全体の消費エネルギーを低減する設計もあります。その他、前述のように適切な回収率設定は不要な高圧化を避ける意味で重要です(回収率を抑えめにすることで結果として必要圧力が下がり省エネとなる場合があります)。このように装置設計と運転条件の工夫次第で、膜システムのエネルギー効率は大きく向上します。
総じて、膜分離システムの省エネルギー化にはハード面(エネルギー回収機器や高効率機器の導入)とソフト面(運転制御の最適化)の両輪で取り組むことが有効です。導入段階で多少コストがかかっても、長期的なランニングコスト削減や環境貢献を考えれば元が取れるケースも多いです。省エネはコスト削減だけでなくSDGsの観点からも企業価値に直結するため、膜分離技術でも今後ますます重視されるでしょう。
アクトのコスト最適化の成功事例
最後に、当社株式会社アクトの製品の導入実績と、他社にはない強みについてご紹介します。アクトは長年にわたり廃水処理・リサイクルのソリューションを提供しており、凝集剤「水夢」シリーズや中和剤「融夢(ゆうむ)」、小型処理装置「ACT-200」など、多彩な製品ラインナップと技術サポートでお客様の課題解決に取り組んできました。単に薬剤や装置を販売するだけでなく、事前のサンプルテストによる最適処理条件の提案、導入後のフォローまで一貫対応することで、導入効果とROI(投資対効果)を最大化することを信条としています。
導入事例1:塗装工場での膜分離+凝集処理によるコスト削減
外壁パネル製造T社では、水性塗料の洗浄排水を処理する際に、従来の凝集剤では特殊顔料を十分除去できず全量産廃処分せざるを得ないという課題がありました。毎月20トンもの廃液を業者委託で処理しており、年間約720万円のコストと保管スペース確保の負担に悩まれていました。アクトは排水サンプルで無償テストを行い、この顔料に適合する凝集剤として水夢SP-4004Vを適用。さらに効率的処理のため凝集沈殿–ろ過一体型の小型処理装置ACT-200を組み合わせたソリューションを提案しました。
結果、導入後は処理水は全項目で排水基準をクリアし再利用可能となり、廃液は月1トン程度まで激減(95%削減)しました。産廃処理コストも年間約720万円→約250万円と65%のコストカットを達成しています。特殊顔料も凝集除去できるようになり、悪臭や槽のヘドロもほぼ発生しなくなったため、作業環境も大きく改善しています。T社の担当者様からは「処理が簡便で驚いた。専門知識がなくても短時間で処理が完了する」と高い評価をいただきました。この事例は膜分離(フィルターろ過)と高度凝集剤の組み合わせにより、高品質な処理水確保とコスト最適化を両立した成功例です。
導入事例2:半導体工場での超純水洗浄排水処理の高度化
半導体製造R社では、製造工程から出る洗浄廃水に微量のレアメタルが含まれるため、自社基準で法規制の1/10という極めて厳しい排水水質基準を課していました。しかし従来の処理では安定的に基準を満たすことが難しく、しかも月30トンの廃液処理に年間1,800万円ものコストがかかっていたのです。処理工程も複雑で作業負荷が高いことから、安定運転と省力化が課題となっていました。
アクトはまず無償テストを実施し、様々な濃度変動にも対応できる汎用性の高い凝集剤水夢SP-3602GPを選定しました。この薬剤はR社の複数種にわたる廃液に対して有効でした。処理水質は全項目で自社基準(法規制の1/10)をクリアし、しかもその変動係数は1%以下という非常に高い安定性を実現しました。年1,800万円かかっていた処理コストも約630万円まで65%削減され、さらに副次効果として沈殿汚泥中から年間200万円相当の貴金属を回収・再資源化することにも成功しました。投資回収期間はわずか1.8年と試算され、経済的メリットは非常に大きなものとなっています。運R社の環境管理ご担当者からは「当社の厳しい要求に対し何度も調整を重ね、最適なソリューションを提供してもらえた。処理水質の安定性が飛躍的に向上し、資源有効活用も実現できた」とのお声を頂戴しています。
アクトの強み:カスタマイズ対応と技術サポート
上記の事例に共通するのは、アクトのお客様ごとのカスタマイズ対応力です。他社では汎用の薬剤・装置しか提供されず処理しきれなかった課題に対して、アクトは豊富な凝集剤ラインナップから最適な処方を選定・開発しできます。凝集剤「水夢」は数十種類以上のバリエーションがあり、無機系から高分子系まで用途別に取り揃えています。必要に応じ新規配合の開発も行い、お客様の排水にジャストフィットする薬剤を提供できる点は大きな強みです。
以上、膜分離技術の基礎から応用事例、運用のポイントまで概説しました。膜分離は高品質な水を得る上で非常に強力な手段ですが、その選定・運用には専門知識とノウハウが求められます。本記事で挙げたように、前処理の工夫やファウリング対策、省エネ技術の導入など、総合的に検討することで性能とコストの最適バランスを実現できます。株式会社アクトでは、豊富な実績をもとにお客様個々のニーズに合わせた凝集剤をご提案し、導入後もしっかり技術サポートいたします。排水処理や水リサイクルでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。限りある水資源を有効活用しつつ、コスト削減と環境対策を両立するベストソリューションを一緒に実現しましょう!

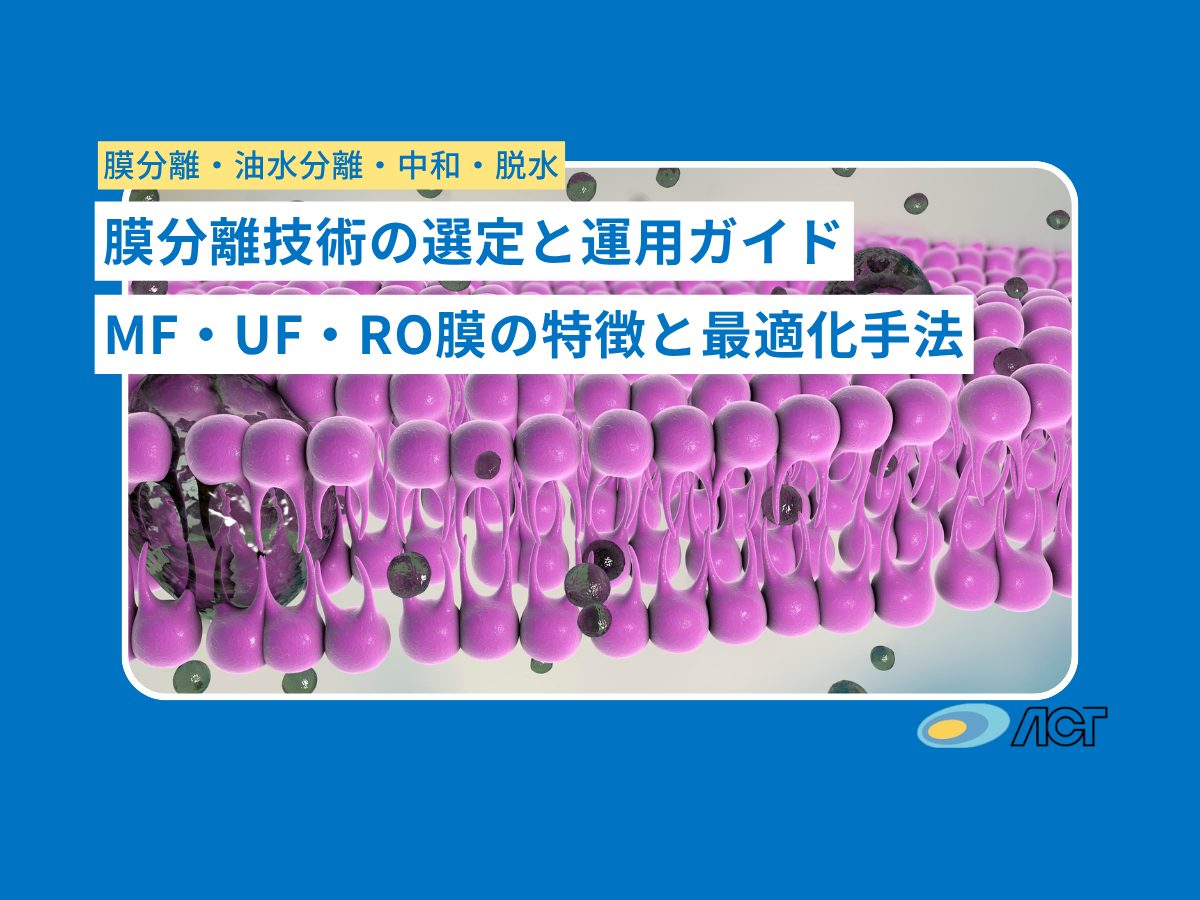
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)