日本では高度経済成長期に深刻化した工場排水による水質汚染は、その後の環境規制により大幅に改善されました。1970年制定の水質汚濁防止法によって全国一律の排水基準が設けられ、特に有害物質やBOD/CODなどの指標について排出が厳しく管理されています。その結果、現在では産業排水が原因の汚染は著しく減少し、多くの河川で水質環境基準の達成率は90%以上と高水準を維持しています。一方で、工場排水以外の新たな水質汚染要因が浮上しており、企業にはそれらへの対策も求められています。
日本の水質汚染の現状|河川・地下水・海洋汚染の実態
日本の公共用水域の水質は規制導入後に大幅に改善されました。例えば令和5年度(2023年)の全国水質調査では、有害重金属や農薬等の健康項目について99.0%の測定地点で環境基準を満たし、BOD・CODなど生活環境項目でも河川は93.8%の水域で基準達成しています。しかし、湖沼の水質は依然として改善途上で、COD環境基準達成率は約52.5%に留まっています。閉鎖性水域では栄養塩の蓄積による富栄養化(アオコや赤潮の発生)が問題となり、湖沼水質保全特別措置法による追加対策などが講じられています。
また、地下水汚染も一部地域で懸念されています。農地から浸透する硝酸性窒素や、工場跡地などからの重金属溶出による地下水汚染事例が報告されてきました。環境省の調査によれば、2023年度の地下水質常時監視において環境基準未達の井戸は全体の約5%で、特に硝酸性窒素・亜硝酸性窒素、砒素、ふっ素が基準超過の主な原因でした。このように、地上の対策強化に伴い地下水への影響に注意が移りつつあります。
一方、現在の日本の水質汚染の主要因として目立っているのが生活排水です。工場など産業排水は法規制で厳しく管理されたため、今では河川や海域の水質汚濁の多くが家庭からの生活排水に起因しています。東京都内の例では、川や海への排水による汚濁の70%以上が生活排水によるものと推計されており、洗剤や油脂、生ごみなどの排水が依然として水環境へ負荷を与えている状況です。実際、伊勢湾の汚染負荷を見ると生活排水由来が49.1%と産業排水の38.0%を上回り、家庭からの排水が水質汚染の半数近くを占めています。
このように、日本の水環境は一時期に比べれば大幅に改善されたものの、閉鎖性水域の富栄養化や地下水汚染、そして生活排水汚染など新たな課題が残っています。さらに近年は、従来のBODや重金属だけでなくPFASやマイクロプラスチック、医薬品成分といった新興汚染物質が水質に与える影響が注目され始めました。次章では、これら新興の水質汚染要因とその脅威について解説します。
新興汚染物質の脅威|PFAS・マイクロプラスチック・医薬品成分の影響
海岸に打ち上げられた大量のプラスチックごみ(漂着ごみ)は、マイクロプラスチック汚染の一因であり、生態系への影響が懸念されています。
近年、水環境中で存在感を増している新興汚染物質として、PFAS(ピーファス)類・マイクロプラスチック・医薬品成分が挙げられます。これらは従来の汚染物質とは異なり低濃度でも慢性的に蓄積したり、生態系や人への長期的影響が懸念されたりするものです。それぞれの特徴と影響を見てみましょう。
- PFAS(有機フッ素化合物) – PFOSやPFOAに代表されるPFAS類は**“永遠の化学物質”とも呼ばれ、炭素-フッ素結合の非常に強い構造により自然界で分解されにくく残留性が極めて高い物質です。撥水剤や消火剤などに長年使用されてきましたが、近年その有害性が明らかになりつつあります。環境中の残留PFASは世界各地で検出され、日本でも地下水や河川、水道水から相次いで検出報告がなされています。PFASは蓄積性があり、体内に取り込まれると排出に非常に長い時間がかかります(血中濃度半減期が3~5年とも)。健康への影響として、一部のPFASに発がん性の指摘や免疫機能低下、出生体重の低下などが報告されており、特に妊婦や乳幼児へのリスクが懸念されています。こうした背景から、日本政府も対策を強化中です。2023年2月にはPFOSとPFOAが水質汚濁防止法上の「指定物質」に追加され、有害物質同様に規制対象となりました。これにより万一これらが大量漏出した場合は直ちに応急措置と届出が必要となり、事業者は事故時の措置義務を負います。さらに環境省はPFOS/PFOAの暫定目標値(合計50ng/L)を正式な水質基準に格上げし、2026年4月から水道事業者に対し3ヶ月ごとのPFAS定期検査と基準遵守を義務化することを決定しました。PFAS汚染は今や全国的な水質問題となっており、発生源の特定や排出抑制策が急務です。
- マイクロプラスチック – マイクロプラスチックは5mm以下の微小なプラスチック片で、プラスチックごみが劣化・粉砕されて生じます。海洋や河川、湖沼などあらゆる水域で検出されており、その海洋汚染への影響は深刻です。海ではプランクトンから魚類、大型哺乳類まで生物がマイクロプラスチックを誤飲・摂取しており、食物連鎖を通じた生態系被害が懸念されています。またマイクロプラスチックは表面に有害化学物質(例:PCBやDDTなど)や環境ホルモンを吸着し運搬する性質があり、汚染の媒介となる点も問題です。実際、北極海や南極海の表層水からもマイクロプラスチックが検出されており、地球規模の汚染が進行中といえます。人間への影響については研究途上ですが、世界保健機関(WHO)は現時点の飲料水中濃度では直接的な健康リスクは確認されないとしながらも、更なる調査と汚染削減の必要性を指摘しています。日本でも水道水や市販の飲料水、さらには食品から微小プラスチックが検出されており、もはや日常的に摂取を避けられない状況にあるとの報告もあります。今後、人の体内での蓄積や長期的健康影響について解明が進めば、規制や対策が求められる可能性があります。
- 医薬品成分 – 医薬品やその代謝産物による水質汚染も新興汚染として注目されています。私たちが日々使用する処方薬や市販薬は、体内で代謝されたのち一部が尿や排泄物として下水に流れ込みます。その中には下水処理場で除去しきれない成分もあり、処理後の放流水に微量ながら残存して河川や湖沼へ放出されます。実際、2000年代に入ってから世界中で下水・河川水から各種医薬品(例:消炎鎮痛剤、抗生物質、抗うつ薬、避妊薬の合成ホルモンなど)が検出されたとの報告が急増しました。日本でも調査により、胃腸薬、糖尿病薬、高血圧薬、抗アレルギー薬などが環境中から検出されており、日常生活由来の化学物質が環境中に蓄積している実態が明らかになっています。こうした医薬品汚染はごく低濃度でも生態系に影響を及ぼす可能性が指摘されています。例えば、ある湖で避妊薬由来の合成エストロゲンが蓄積した結果、オスの魚に卵巣が形成され繁殖不能になる内分泌かく乱作用(環境ホルモン問題)が報告されました。また抗生物質の環境残留は薬剤耐性菌の出現リスクを高める懸念もあります。現状、こうした微量化学物質を完全に除去する技術はコストや技術面で課題がありますが、オゾン処理や活性炭吸着、膜分離など高度処理技術の開発が進められています。企業にとっても、製薬工場や病院など特定業種では排水中の医薬品成分管理が求められつつあり、一般の工場でも廃棄薬品の適正処理など新たな視点での対応が重要になっています。
以上のように、PFAS・マイクロプラスチック・医薬品成分といった新興汚染物質は従来の汚染とは異なる慢性的かつ複合的なリスクをもたらします。政府もこれらに対する環境中濃度のモニタリングや規制強化に乗り出しており、企業もアンテナを高くして情報収集と対策に努める必要があります。次章では、企業が遵守すべき水質汚染対応の法規制上の義務と、監視・報告・改善の体制について解説します。
企業の水質汚染対応義務|法規制・監視・報告・改善の要件
工場や事業場を運営する企業は、水質汚染防止のために様々な法的義務を負っています。代表的なものに水質汚濁防止法に基づく義務があり、これは企業の排水管理担当者にとって必ず遵守すべき基本事項です。以下、法規制上のポイントを整理します。
- 特定施設の届出義務: 工場・事業場で有害物質を含む水や多量の有機汚濁物質を排出し得る設備(政令で定める「特定施設」)を設置する場合、事前に都道府県知事等への届出が必要です。例えばメッキ槽、洗浄設備、化学反応槽、食品工場の加工設備など多岐にわたる業種設備が特定施設に指定されます。届出により排水経路や処理方法を明示し、行政の監督下で適切な排水管理を行うことが求められます。
- 排水基準の遵守と測定・記録義務: 特定施設から公共用水域に排出される汚水には、法令で濃度基準(排出基準)が定められています。全国一律基準としてpH、中味(BODまたはCOD)、SS(浮遊物質)、油分、重金属類など項目ごとに許容濃度が規定され、地域によってはこれより厳しい上乗せ基準や総量規制も適用されます。事業者は自社排水がこれら基準を常時満たすよう管理する責務があります。そのために定期的な水質測定と記録の義務が課せられており、排水口での水質を計画的に分析して保存しなければなりません。例えばpHやCODの測定値を所定年数保存し、行政から求められた際には報告できるようにしておく必要があります。これら届出・測定義務の不履行は法律違反となり、罰則の適用対象です。実際、基準超過を隠して記録せず放置したりすると、発覚時に企業名公表や罰金刑等の厳しい処分が科される可能性があります。コンプライアンス上、日々の排水測定と記録管理は企業責任の基本です。
- 異常時の通報・応急措置義務: 排水設備の故障や事故等により、有害物質や油が漏洩したり排水基準超過の恐れが生じたりした場合、事業者には直ちに応急措置を講じ汚染拡大を防止する義務があります。これは水質汚濁防止法第14条の2に規定された措置義務で、まず排出を停止し、漏れた汚水の拡散を防ぐ(例:排水設備の停止、オイルフェンスや土嚢での囲い込み、回収ポンプで汚水吸引など)対応が求められます。次に、関係機関への連絡として所轄の環境部署(都道府県や政令市)に速やかに電話連絡し、状況を報告します。さらに、一定時間内に事故届を提出し、事故の原因・状況・講じた措置を文書で報告する義務があります。例えば「有害物質を含む水が河川に流出し人の健康被害のおそれがある場合」などは法定事故として扱われ、迅速な届出が必須です。万一こうした初動措置や報告を怠り被害を拡大させた場合、事業者は懲役刑・罰金刑等の処罰や損害賠償責任を問われる可能性があります。企業は緊急時の対応フローをあらかじめ定め、従業員にも周知しておくことが重要です。
- 改善命令と罰則: 行政当局(知事等)は、事業者が排水基準に違反した場合や水質事故対応が不十分な場合、施設の改造や使用停止など改善命令を発する権限を持っています。従わない場合は懲役刑・罰金刑に加え、違反事実の公表措置が取られることもあります。加えて、故意の基準超過や虚偽報告等悪質な違反には刑事告発も行われ得ます。企業にとって法令遵守は経営の最低条件であり、水質事故一つで社会的信用を失墜しかねません。平時から環境法令リストを整備し、改正情報にも注意を払いながら、自主的な順守状況チェックと体制整備を怠らないことが肝要です。
このように、水質汚染防止に関する企業の義務は「届け出・測定の平常管理」と「異常時の迅速対応」に大別できます。これらを確実に履行しつつ、次章で述べるような汚染予防対策や日常的な管理システムを構築することが、企業の責務であると同時にリスク低減にもつながります。
水質汚染の予防対策|発生源対策・処理技術・管理システム
水質汚染を未然に防ぐには、企業が日頃から汚染物質の発生源対策と適切な処理技術の導入、そして継続的な管理システムを確立することが重要です。以下、それぞれのポイントについて解説します。
- 発生源対策(上流での汚染削減): 汚染を出さないことが最善の対策です。工場では原材料や工程を見直し、汚染負荷の低減を図ります。例えば製造プロセスで使用する薬品をできるだけ無害・低量に切り替える、原料の歩留まりを向上させ廃液発生量を減らす、といった取組みです。実際、化学工場では薬品使用量の削減(原単位改善)によって排出汚染を減らすことがコンプライアンス強化につながるとされています。また設備面でも、万一の漏洩に備えて二重囲いタンクや非常時用の遮断弁を設置するなど、事故リスクを下げる設計にします。さらには廃液の分別管理(有害な実験排水を一般系統と分離して専用処理する等)も有効です。汚染源対策の基本は「自社の排水の性状を正確に把握し、それに最適な処理法を選定すること」に尽きるとも言われます。そのために発生源ごとの水質分析データを蓄積し、どの工程がどんな汚染を出しているかを常に把握しておくことが重要です。
- 処理技術の導入(適切な排水処理): 発生した排水については、最新かつ適切な処理技術を用いて環境基準以下にまで汚染物質濃度を下げなければなりません。排水処理技術は排水の性質によって様々ですが、一般には多段的な処理フローを組み合わせて汚濁負荷を除去します。例えば有機物の多い排水には微生物を用いた生物処理(活性汚泥法など)でBODを削減し、重金属を含む排水には薬品沈殿やイオン交換で金属を除去します。高濃度のリン・窒素を含む場合は嫌気・好気の組み合わせによる脱窒・脱リン処理を施します。油分や浮遊ゴミはスクリーンやグリーストラップで物理的除去をします。さらに近年問題化している微量汚染物質(前述のPFASや医薬品等)には、活性炭吸着やオゾン酸化、逆浸透膜(RO)など高度処理を追加して対応するケースもあります。実際、PFAS除去には一般的な活性炭フィルターでは不十分な場合があるため、粒状活性炭やRO膜によるろ過が有効とされます。このように排水特性に合った技術を選定し、複数の処理法を最適組み合わせすることが大切です。また処理設備は導入して終わりではなく、日常の維持管理が性能維持のカギとなります。ポンプや攪拌機、計測機器の点検整備を計画的に実施し、故障や性能低下を早期発見するようにしましょう。処理プロセス各段階での水質サンプリングも有効で、例えば中和槽や沈殿槽の水を定期分析して基準超過の兆候がないか頻繁にチェックすることが推奨されています。さらに、新たな処理技術や薬剤も積極的に情報収集し、必要に応じて専門業者に相談するとよいでしょう。自社では難しい高度処理も、外部の水処理メーカーと連携することで解決策が見つかる場合があります。
- 管理システムの構築(人材・運用の仕組み): 技術的対策と並んで重要なのが、組織としての環境管理体制づくりです。まず「人と設備の両面からの管理体制」を整えることが必要とされています。人的な側面では、環境法令に精通した担当者を配置し、定期的な教育訓練を行って知識をアップデートします。社内規則やマニュアルも整備し、新入社員への周知や緊急時対応フローの訓練も欠かしません。設備面では前述のような適切な処理装置の導入と保守に加え、緊急時の応急措置手順の確立なども求められます。これは事故発生時に誰が何をするかを事前に決めておくことで、初動遅れを防ぐ狙いがあります。さらに、継続的改善の仕組みとして、品質管理などで知られるPDCAサイクルを環境管理にも適用することが推奨されています。Plan(計画)– Do(実行)– Check(点検)– Act(改善)の循環を回し、定期的に排水管理の目標設定・実施・結果評価・対策見直しを行います。例えば「年間を通じ全排水項目で基準値の50%以下を維持」という社内目標をPlanで定め、Doで設備運転と測定を実行し、Checkで測定データを解析して異常値や傾向を評価、不適合があれば原因分析します。そしてActで処理工程の改善や担当者再教育など対策を講じて次の計画に反映します。このPDCA管理サイクルを定着させることで法令遵守が着実なものとなり、さらに昨今求められる環境負荷低減の自主的取組み(例えば省エネ・排出削減によるSDGs貢献など)も進めやすくなります。実務的にはISO14001等の環境マネジメントシステムを導入するのも有効でしょう。重要なのは「決められたことを守る」消極的態度ではなく、「自ら環境改善に取り組む」積極的姿勢で管理レベルを向上させていくことです。
以上の発生源対策・処理技術・管理システムの三位一体の取組みにより、企業は水質汚染の予防と継続的なリスク低減を図ることができます。万全の予防策を講じていても、事故の可能性をゼロにすることは難しいため、次章では万一汚染事故が発生してしまった場合の緊急対応策について説明します。
水質汚染事故の緊急対応|初動対応・拡大防止・復旧計画
どれだけ注意していても、設備トラブルや人的ミス、天災などにより水質汚染事故が発生してしまう可能性はゼロではありません。例えば薬品タンクからの漏洩、配管破損による有害液の流出、豪雨時の排水処理能力オーバーによる未処理水の放流など、様々なケースが考えられます。ここでは、万一事故が起きた際に企業が取るべき緊急対応のポイントをまとめます。
- 初動対応:安全確保と汚染源の遮断
事故を発見したら一刻も早く汚染の拡大を防ぐことが最優先です。具体的には、ただちに関連設備を停止し、漏洩元のバルブを閉じるなどして汚染物質の流出を止めます。同時に、既に流出した汚染水が広がらないよう拡散防止措置を講じます。例えば、油や薬品が河川に流れ出た場合は直ちにオイルフェンスを展張して拡散を封じ込め、排水溝内であれば土嚢や止水板で塞ぎ込みます。漏洩物が土壌に染み込む恐れがあれば吸着マットや真空ポンプで可能な限り回収します。現場作業者は防護具を着用し、二次災害や負傷に注意しながら対応します。必要に応じて社内の緊急連絡網を使い人員を招集し、初動対応にあたる体制を敷きます。 - 関係機関への通報:行政・周辺への速やかな情報提供
初動措置を進めながら、速やかに関係機関へ連絡します。水質汚濁防止法では所轄自治体(都道府県または政令市)の環境部局等に事故発生を連絡することが義務付けられています。連絡時には「いつ・どこで・何が・どれだけ流出し・現在どう対応しているか」を簡潔に伝え、指示を仰ぎます。また場合によっては消防(危険物質の場合)や水道事業者(上流に取水口がある場合)等への連絡も必要です。周辺住民や利害関係者への周知も、被害拡大防止のために欠かせません。例えば飲用井戸や農業用水に影響が及ぶ恐れがあるなら、自治体を通じ近隣住民に対し井戸水の利用停止を呼びかけるなどの措置が取られます。企業としても自主的に周囲への説明・謝罪に努め、誠実に対応する姿勢が重要です。 - 拡大防止と汚染除去:現場封じ込めと環境復旧
初動で封じ込めた汚染物質を確実に除去し、環境への被害を最小限にとどめます。たとえば、漏洩した液体は強力なバキューム車(吸引車)等を使用して可能な限り回収し、タンクに移送します。油膜が水面に浮いている場合は吸着シートやオイルブームで回収・回収します。土壌に染み込んだ場合は汚染土を重機で掘削除去し、産業廃棄物として処分します。必要に応じて仮設の水処理装置を現場に設置し、汚染水を浄化することも有効です。例えば活性炭フィルターや簡易沈殿槽を組んだポータブル処理ユニットを用い、その場で浄化してから安全な水を放流する手段もあります。実際、近年は環境対策企業が緊急用の移動式処理設備を備えており、工事現場や災害対応で利用されています。自社で手に負えない場合は、専門業者に応援要請して処理作業を委ねる判断も必要です。自治体によっては水質事故時に協定を結んだ処理業者を派遣する体制が整えられています。拡大防止措置が完了したら、河川や地下水の水質モニタリングを実施し、汚染範囲を確認します。濃度が基準内に戻るまで継続的に監視し、周辺環境に安全が確保されるまで復旧作業を続けます。 - 事故報告と再発防止策:原因究明と対策の共有
事故対応が落ち着いた段階で、所定の事故報告書を作成して行政に提出します。報告書には発生日時・原因・流出物質と量・受けた被害・講じた措置・今後の対策などを詳しく記載します。同時に社内でも事故の原因究明を行い、再発防止策を検討します。設備起因なら設計変更や老朽部品交換、人為ミスなら手順書見直しや教育強化など、具体的な改善策を講じます。再発防止策は社内に展開し、同種リスクを抱える他拠点があれば横展開して共有します。場合によっては、安全管理規程や緊急時対応マニュアルを改訂し、訓練をやり直すことも必要でしょう。事故対応を経験した担当者のヒヤリハット情報を集め、次に活かす仕組みも有効です。重要なのは、「二度と同じ事故を起こさない」という強い決意で組織的な学習と改善を行うことです。
以上が水質汚染事故時の一連の緊急対応フローです。初動の速さ・適切さが被害の大小を左右するため、日頃から「最悪を想定した準備」を怠らないことが肝心です。具体的には、吸着材や土嚢などの資材を備蓄し、緊急連絡網や手順書を整えて定期訓練することで、いざという時に慌てず対応できます。また信頼できる専門業者(環境対策会社)との契約を結び、緊急出動支援を受けられるようにしておくのも有効でしょう。企業のリスクマネジメントとして、水質汚染事故への備えも環境経営の重要な要素なのです。
アクトの水質汚染対策実績|予防から緊急対応まで総合支援の成功事例
ここまで、日本国内の水質汚染の現状と企業に求められる対応策について解説しました。最後に、水処理の専門企業である株式会社アクト(Act)による水質汚染対策の実績とサービスについて紹介します。
◆ 総合力と技術力:340社以上の支援実績
アクトは自社開発した無機系凝集剤「水夢(すいむ)」、アルカリ排水中和剤「融夢(ゆうむ)」、小型凝集沈殿装置「ACT-200」などを駆使し、多種多様な業種の排水処理ソリューションを提供してきました。その導入実績は340社以上にのぼり、国土交通省や農林水産省から製品認定を受け公共事業に採用されたほか、福島第一原発事故後の放射能汚染水処理にも採用されるなど、高い信頼性で裏付けられています。これらの実績は、アクトの技術力が厳しい基準をクリアし得ることを示すものです。単に排水基準を満たすだけでなく、「処理コスト削減」と「環境負荷低減」の両立を実現できる点がアクトの強みであり、他社との差別化ポイントとなっています。
◆ オーダーメイド処理薬剤と装置による課題解決
アクトが提供するソリューションの特徴は、顧客それぞれの排水特性に合わせたオーダーメイドの対応です。例えば凝集剤「水夢」はゼオライトを主成分とした特許取得済みの無機凝集剤で、排水成分に応じて最適な調合が可能です。これにより、従来の有機高分子凝集剤では処理困難だった水性塗料廃水や重金属含有廃水にも対応でき、汚濁物質を効率よく固形化・除去します。小型処理装置「ACT-200」は1台で凝集→沈殿→ろ過の全工程を容易に行えるコンパクト装置で、専門知識がなくても運用可能です。この装置と水夢の組み合わせによって、排水中の有害物質や濁度成分を確実に低減しつつ、排出される廃棄物を液体から固体へ転換します。その結果、液体産業廃棄物を大幅に減容化でき、処理費用を最大で70%削減した実例もあります。実際に、ある建材製造工場では水性塗料の洗浄廃液を従来全量産廃処理して年間約720万円かかっていたものを、アクトの凝集剤「水夢SP-4004V」と装置「ACT-200」で処理するソリューションを導入した結果、年間コストを約720万円から約250万円へと65%削減し、廃液発生量も月20トンから1トンへと95%削減することに成功しました。しかも処理水は全項目で排水基準をクリアし、法令遵守と経済メリットを同時に達成しています。このように、アクトは各社の事情に合わせたカスタマイズ技術で「環境対応」と「経営改善」の両立を実現しているのです。
水質汚染対策は単に法律を守るだけでなく、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な経営にも直結する課題です。株式会社アクトでは実績に裏付けられたソリューションで水質汚染リスクの低減と企業価値向上を両立させるお手伝いをしてまいります。
※本記事で紹介したサービス内容は株式会社アクト公式サイトの情報および実績事例に基づいており、詳細や緊急対応の可否については直接企業にお問い合わせください。

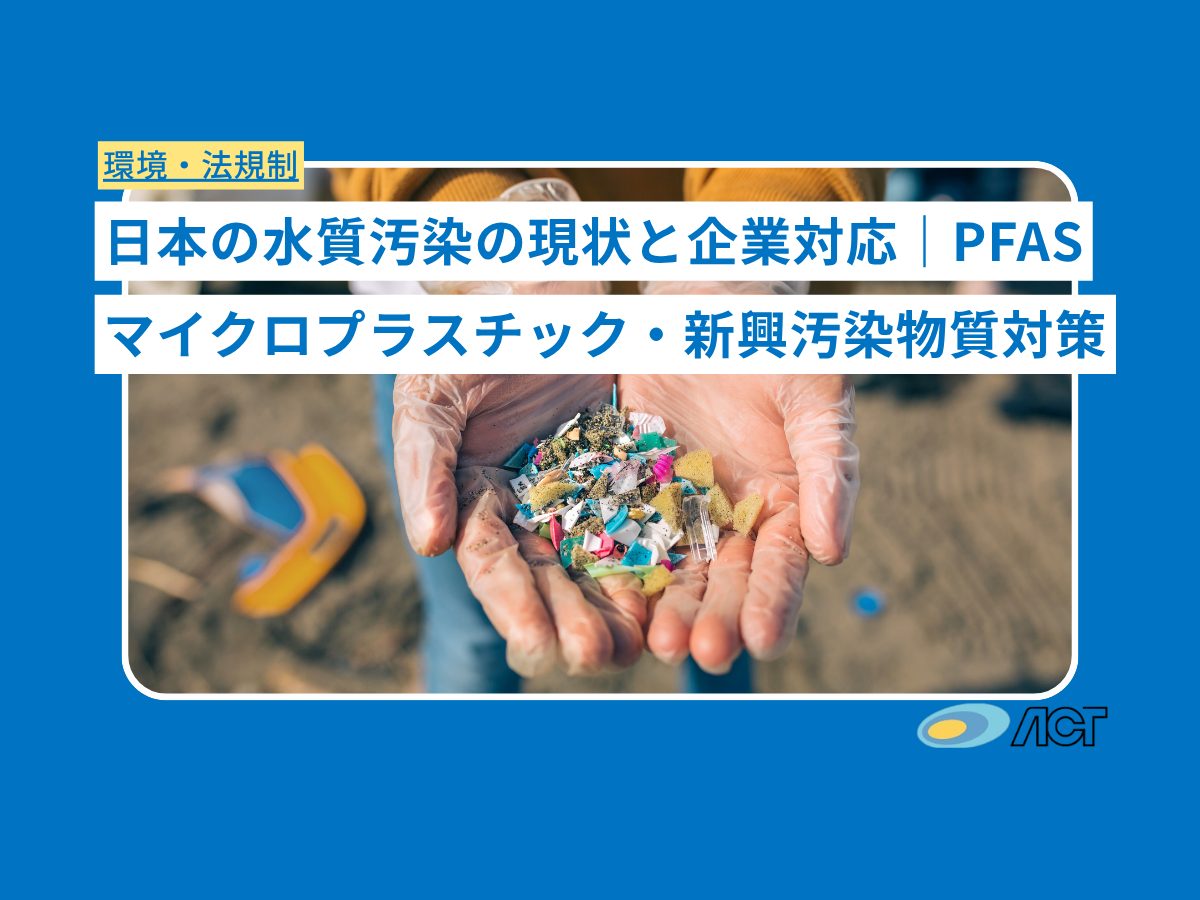
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)