工場や事業所で日々発生する排水を適切に処理するには、「ろ過」の技術が欠かせません。本記事では、ろ過処理の基本から最新技術、効率化のポイントまでを包括的に解説します。専門企業であるアクトの知見を交え、ろ過処理技術の種類や選定方法、効率化のポイントについて分かりやすく紹介します。排水管理担当者の方々が直面する課題解決に役立つ情報をまとめました。
ろ過処理の基本原理|物理ろ過・生物ろ過・化学ろ過の仕組み
まず、ろ過処理には大きく分けて物理ろ過・生物ろ過・化学ろ過の3つの方法があります。それぞれの基本原理と仕組みを見ていきましょう。
- 物理ろ過: フィルターや砂利などの物理的なフィルターを使って水中の不純物をこし取る方式です。サイズの大きなゴミや汚れを、目の細かい網や砂の層といったろ過材で捕捉し、水と分離します。例えば家庭用浄水器のフィルターやコーヒーフィルターも物理ろ過の一種です。物理ろ過は構造がシンプルで、比較的大きな粒子の除去に効果的ですが、目に見えないほど小さい汚染物質には効果が及びません。
- 化学ろ過: 活性炭などの吸着剤や薬剤を用いて、水中の微小な汚染物質を化学的に除去する方式です。代表的なのが活性炭フィルターで、水に溶け込んだ臭気物質や有機化合物、残留塩素などを多孔質の活性炭の表面に吸着させて除去します。活性炭は物理吸着と化学吸着の両面で作用し、油分・有機物・塩素・臭気など幅広い物質を効率よく除去できます。化学ろ過により、水に溶けた目に見えない不純物や着色成分を取り除けるため、飲料水の味や臭いの改善にも有効です。一方で、吸着剤は使用に伴い効果が飽和していくため、定期的な交換や再生が必要になります。
- 生物ろ過: 微生物の働きを利用して水中の汚染物質を分解・無害化する方式です。ろ過材に付着したバクテリア(ろ過バクテリア)が、水中の有機汚濁物質や有害なアンモニアなどを栄養源として分解し、最終的に二酸化炭素や硝酸などの安定した物質に変えます。水槽や池のろ過装置では、生物ろ過によってアンモニアが亜硝酸塩・硝酸塩へと変換され、水質が自然に浄化されます。生物ろ過は持続的かつ環境に優しい方法であり、一度バクテリア層が形成されれば連続的に汚濁物質を処理し続ける点が強みです。ただし、微生物が活動しやすい環境(水温や栄養など)の維持と、立ち上げに時間を要する点に留意が必要です。
以上のように、ろ過処理には物理的にこし取る方法、化学的に吸着・反応させる方法、生物学的に分解する方法があり、多くの場合これらを組み合わせて排水中の様々な汚染物質を除去しています。例えば工場排水では、比重差を利用した沈殿分離(物理)+活性炭処理(化学)+生物処理といった複合プロセスで汚濁物質を徹底的に減らすことが一般的です。目的とする処理レベルや汚染物質の種類に応じて、最適な方法を選定・組み合わせることが重要になります。
ろ過装置の種類と特徴|砂ろ過・膜ろ過・活性炭ろ過・精密ろ過の比較
次に、実際に水処理現場で使われるろ過装置の種類について、その特徴を比較します。代表的なものとして砂ろ過装置、膜ろ過装置、活性炭ろ過装置、精密ろ過フィルターが挙げられます。
- 砂ろ過装置: 砂の層をろ過材として利用する伝統的なろ過方式です。水を砂層に通過させ、砂粒の隙間で不純物を捕捉します。砂ろ過には主に2種類あり、ゆっくり水を通す「緩速ろ過」と高速で通水する「急速ろ過」に分類されます。
- 緩速ろ過: 厚い砂層の上を原水がゆっくり浸透していく方式です。砂の表面には運転開始後しばらくして生物膜(バイオフィルム)が形成され、これが天然の濾過層となります。生物膜が物理的フィルターの役割を果たしつつ、微生物の働きで溶解性の有機物やアンモニアも分解できるため、濁質除去と生物処理を同時に行える点が特徴です。処理速度は遅いものの、薬品を使わず安定した水質が得られるため、古くから上水道の浄水場などで利用されてきました。
- 急速ろ過: 文字通り水を高速で砂層に通す方式で、前段で凝集剤を添加して水中の微粒子や細菌をあらかじめ凝集沈殿させてから、上澄みを砂ろ過する方法です。原水の濁度が高い場合でも対応しやすく、大量の水を短時間で処理できるのが利点です。現在の浄水場では一般的に、凝集沈殿→急速砂ろ過→塩素消毒というプロセスが採用されています。ただ、砂ろ過だけでは除去しきれない微小物質(ウイルスや溶解性物質)が残る場合もあり、必要に応じて後段の処理と組み合わせます。
- 膜ろ過装置: 微細な孔(膜)をろ過材に用いる近年発展したろ過方式です。中空糸膜や平膜モジュールに原水を通し、膜の孔径より大きな粒子・微生物を物理的に遮断します。膜ろ過は砂ろ過など従来法と比べて極めて高いろ過精度を持ち、ナノメートル(nm)オーダーの微粒子まで除去可能です。膜の種類によって除去できる物質のサイズが異なり、大きな孔径のものは「マイクロフィルtration (MF膜、精密ろ過膜)」、続いて「ウルトラフィルtration (UF膜、限外ろ過膜)」「ナノフィルtration (NF膜)」「リバースオスメosis (RO膜、逆浸透膜)」に分類されます。MF膜は孔径0.1~数μm程度で濁りや細菌を除去し(ウイルスは通過し得る)、UF膜はさらに細かく一部のウイルスも除去可能、NF膜になると溶け込んだ有機物や農薬の分子レベルまで除去し、RO膜は最も孔が小さく塩類イオンまで除去できるため海水淡水化にも利用されます。膜ろ過装置は高度な水質が得られる反面、コストやエネルギー、膜の目詰まり対策も考慮が必要です。ただ近年は膜の低価格化が進み、多くの浄水施設で細菌や原虫対策としてMF膜・UF膜が導入されるケースも増えています。
- 活性炭ろ過装置: 粒状または粉末状の活性炭を詰めたカラムに水を通すことで、水中の不純物を吸着除去する装置です。活性炭は前述の通り多数の微細孔による大きな表面積と高い吸着力を持ち、有機物や異臭味物質、残留塩素、重金属の一部まで幅広く除去できます。飲料水の処理では主に臭気やトリハロメタン前駆物質の除去に用いられ、下水処理の高度処理工程や工業排水の処理でも、色度やCODの低減に活躍します。活性炭ろ過は物理・化学ろ過のハイブリッドとも言える方式ですが、活性炭が飽和すると吸着能力が低下するため、一定期間での交換再生活動が必須です。また、活性炭槽自体は細かな粒子の除去には向かないため、通常は前段に砂ろ過や精密ろ過フィルターを置き、懸濁物質を除いてから活性炭に通すのが一般的です。
- 精密ろ過フィルター: カートリッジフィルターやバッグフィルターなど、非常に細かい孔径のフィルターを使用するろ過装置です。膜ろ過の一種とも位置づけられますが、ここでは特に数μm~0.1μmオーダーの孔径を持つフィルターによる微粒子除去を指します。日本語では「精密ろ過」とも呼ばれ、英語ではマイクロフィルトレーション(MF)に相当します。精密ろ過フィルターは細菌や酵母、大腸菌サイズの粒子を物理的に捕捉できるため、清涼飲料の無菌ろ過や電子部品洗浄水のろ過などに利用されます。例えば精密ろ過膜(MF膜)は孔径0.1~10μm程度で、藻類や原生動物、細菌類を除去可能です。一方でウイルスや溶解したイオンなどは通過してしまうため、必要に応じて限外ろ過膜(UF膜)やRO膜と組み合わせます。また、精密ろ過フィルターは一定量の不純物を捕捉すると目詰まりするため、処理水量や濁度に応じてフィルターサイズや本数の設計、交換サイクルの管理が求められます。
以上のように、ろ過装置には砂ろ過(粗ろ過)から最新の膜ろ過、吸着式の活性炭ろ過、微細フィルターによる精密ろ過まで様々な種類が存在します。それぞれに得意分野と限界があるため、処理したい水の性質や求める水質に応じて、最適なろ過方式や組み合わせを選定することが重要です。例えば飲料水処理では「凝集沈殿+砂ろ過+活性炭」、超純水製造では「砂ろ過+活性炭+RO膜+精密フィルター」といった多段階のろ過システムが一般的です。目的に応じてろ過材の選択やろ過精度の調整を行い、効率的かつ経済的なろ過処理を実現しましょう。
業界別ろ過システム|食品・医薬品・電子工業での高精度ろ過事例
用途や業界によって、求められる水の純度や処理方法は異なります。ここでは食品業界、医薬品業界、電子工業の3つを例に、それぞれで活用されている高精度ろ過システムの事例を紹介します。
食品業界における高精度ろ過事例
食品・飲料産業では、水そのものを製品に使うケースや、製造プロセスで衛生的な水が必要なケースが多々あります。また、製品自体(飲料や酒類など)の品質維持のために微生物や不純物の除去が重要です。
代表的な例がビールや清涼飲料の「無菌ろ過」です。ビール醸造では完成後に熱殺菌を行わず、膜ろ過によって酵母や雑菌を除去することで風味を保ったまま製品化する手法が広く普及しています。精密ろ過膜(MF膜)を使えば、ビール中の酵母や乳酸菌など直径数μmの微生物は通さずに取り除けるため、生ビールでも雑菌繁殖を防げます。同様にワインや果汁飲料でも、加熱による風味劣化を避けるためにマイクロフィルトレーションによる除菌が行われています。例えば日本酒やワインの生酒では、0.2μm程度の中空糸フィルターで火入れせずに酵母を除去し、フレッシュな風味を保つ技術が用いられています。これらの膜ろ過技術により、食品業界では高品質かつ安全な製品を効率よく生産することが可能になっています。
さらに食品工場の用水や洗浄水にも高度なろ過処理が導入されています。飲料メーカーでは原水を一旦RO膜で脱塩・純水化し、必要なミネラルを調整してから製品に使用することがあります。乳製品工場では、超濾過膜(UF膜)を用いて乳清からタンパク質を濃縮・回収するなど、膜技術を利用した成分分離・濃縮も盛んです。また、食品工場排水の処理にも膜が活用されており、嫌気・好気処理+膜分離(MBR)によってBODやSSを基準値以下に浄化しつつ、処理水を再利用する取り組みも進んでいます。食品業界では製品品質と衛生管理の観点から、膜ろ過や精密ろ過フィルターが重要な役割を果たしています。
医薬品業界における高精度ろ過事例
医薬品製造においては、純水・超純水が欠かせません。特に注射剤や点滴液の製造には、ウォーター・フォー・インジェクション(WFI:注射用水)と呼ばれる極めて高純度の水が必要です。伝統的にWFIは多段蒸留によって製造されてきましたが、近年ではRO膜(逆浸透)+UF膜(限外ろ過)による膜法でWFIを生成することも認められ、設備の省エネ・省コスト化が図られています。RO膜でイオンや有機物を除去し、続いてUF膜でエンドトキシン(パイロジェン)や微生物をシャットアウトすることで、蒸留法に匹敵する水質の注射用水を得ることが可能です。
また、製薬用水の製造プロセスでは、原水の段階から多段階のろ過が取り入れられます。前処理段階で砂ろ過や活性炭ろ過により懸濁物と塩素を除去し、軟水化装置で硬度成分を取り除いた後、RO膜ユニットを複数段直列に配置して溶解性イオンを徹底的に除去します。さらに、EDI装置(電気再生式イオン交換)や混床イオン交換樹脂でイオンを追い込み除去し、最後に精密ろ過フィルター(0.2μmカートリッジ)で完全除菌するといった工程が一般的です。こうして製造された超純水は電気伝導率が極めて低く(18MΩ・cm近い抵抗率)、細菌やウイルスがゼロで、有機物も検出限界以下という水質基準を満たします。
医薬品工場内では、工程用水だけでなく空調系の加湿水や洗浄用水も高純度が要求され、必要に応じてRO水やUF処理水が使われます。また、製剤工程では薬液そのものを滅菌ろ過するケースも多いです。たとえばワクチンや点滴液は、充填直前に0.22μmの除菌フィルターでろ過し無菌保証するのが標準的手順です。医薬品業界では、このように膜ろ過と殺菌フィルターを駆使することで、製品中の微生物リスクを排除し高い品質を担保しています。わずかな不純物や菌も許されない領域だからこそ、最新のろ過技術が不可欠なのです。
電子工業における高精度ろ過事例
電子工業(半導体・液晶・電子部品製造など)では、超純水と呼ばれる究極に純度の高い水が必要になります。半導体工場ではシリコンウェハーの洗浄や製造プロセスの各所で大量の純水が使われますが、極微細パターンを扱うためにほぼ完全に不純物を排除した水が求められます。超純水とは、イオンや微粒子、有機物、微生物などあらゆる不純物が限界まで除去された水で、電気を通さないほどイオン成分が無く、粒径0.1μm以下の微粒子すら含まれていません。
超純水を製造するには、様々な水処理技術を組み合わせた多段精製システムが用いられます。一般的な例では、まず原水に対し前処理として砂ろ過・カートリッジフィルターで大きな粒子を除去し、活性炭で塩素や有機物を吸着除去します。続いてRO膜で大部分のイオンと有機物を除去し、場合によってはNF膜で特定の有機物を補足的に除去します。その後、イオン交換樹脂(陽イオン交換と陰イオン交換の両方)で残留イオンを極限まで取り除きます。さらに超濾過膜(UF膜)によってナノサイズのコロイドや微生物を除去し、最後に紫外線殺菌装置で微量の有機物を分解・殺菌する、といった工程を経て超純水が完成します。
この超純水は、半導体製造では製品歩留まりを左右する命綱と言っても過言ではありません。わずかな微粒子でも回路をショートさせ欠陥の原因となり、イオン不純物はエッチングなど化学プロセスを乱します。超純水を用いることで製造工程の不良を減らし、結果的に良品率(歩留まり)を向上させ生産コストを下げることができます。例えば、ある先端半導体工場では超純水中の微粒子濃度を1粒/ℓ以下(50nm以上の粒子)に維持し、不純物濃度もppt(兆分率)レベルに管理しています。これを実現するため、配管やタンクの材質にもこだわり、ポイントごとに精密フィルターを多重に配置して再汚染を防止します。
電子工業では排水処理にも高度なろ過技術が使われます。製造工程から出る排水には薬品成分や超微粒子が含まれるため、膜分離活性汚泥法(MBR)で有機汚濁を処理しつつ、MF/UF膜で微粒子を分離するシステムが導入されています。さらに必要に応じてRO膜を組み合わせ、超純水の洗浄排水をリサイクルして再利用する企業もあります。電子産業では水の高度なリサイクルが環境・経済両面で求められており、ろ過技術がその鍵を握っています。
以上、業界別に見てきたように、食品・医薬・電子それぞれの分野で求められる水質や処理技術は異なりますが、共通して膜ろ過や精密ろ過といった高度ろ過技術が重要な役割を果たしています。それぞれの業界特有のニーズに応じて最適なろ過システムを選定し、安全性・品質向上とコスト削減を両立することが大切です。
ろ過効率の最適化|目詰まり対策・逆洗システム・交換タイミング
ろ過装置を安定かつ効率的に運用するには、目詰まり(ファウリング)の防止と対策が避けて通れません。フィルターやろ材は使用を続けるうちに捕捉した汚れで徐々に目が塞がり、流量低下や処理水質の悪化を招きます。ここでは、ろ過効率を最適化するための目詰まり対策、逆洗システムの活用、ろ材交換のタイミングについて解説します。
- 目詰まりの予防策: 最初から目の細かいフィルター一段で処理しようとすると、すぐに目詰まりが発生し効率が低下します。そこで一般的なのは、多段階のろ過で負荷を分散する方法です。まず粗めのスクリーンやサイクロン分離器で大きなゴミ・重い汚れを除去し(一次ろ過)、次に砂ろ過やバッグフィルターで中程度の粒子を取り除き、最後に精密フィルターや膜ろ過で微粒子を捕捉する、といった流れです。例えばマルチサイクロン(遠心分離機)をろ過器の前につけると、比重の大きな汚泥やスラッジを先に分離できるため、後段のフィルターに蓄積する汚れが大幅に減り、清掃が容易になります。このように前処理を充実させることが、目詰まりしにくいろ過システム設計のポイントです。
- 逆洗(バックウォッシュ)の活用: 砂ろ過や一部の膜ろ過装置には、逆洗システムが備わっています。逆洗とは、通常とは逆方向に水や空気を流してろ材を洗浄する操作です。定期的に逆洗を行うことで、フィルター内部に溜まったゴミを押し出して除去し、圧力損失の回復や処理性能の維持が図れます。例えば急速砂ろ過では1日に1回程度バックウォッシュを行い、砂層表面に堆積した汚泥を洗い流します。中空糸膜モジュールでも運転を一定時間行った後、透過水を逆流させて膜表面を洗浄する自動逆洗運転が採用されています。逆洗頻度は原水の汚れ具合によりますが、こまめな逆洗こそが目詰まり防止の基本です。
- フィルターの洗浄と薬品洗浄: 逆洗では落としきれない汚れが付着した場合、フィルターを取り外して洗浄する必要があります。特に膜ろ過装置では、定期的に膜モジュールを水から取り出し、酸・アルカリなどの洗浄液で化学洗浄(CIP:定置洗浄)を行います。例えばUF膜ではタンパク質など有機汚れにはアルカリ洗浄、無機スケールには酸洗浄を実施し、膜透過性能を初期状態近くまで回復させます。これにより膜の寿命延長と安定稼働が可能です。自動運転で定期洗浄を組み込める装置も増えており、運転管理の省力化にもつながっています。
- ろ材・フィルター交換のタイミング: 物理的洗浄や薬品洗浄を行っても性能が戻らなくなったら、ろ材自体の交換時期です。一般に、ろ過器の差圧(入口と出口の圧力差)が設計上の限界を超えたり、処理水の水質が基準を下回ったりしたら交換の目安となります。砂ろ過の場合、一定期間運転すると砂に付着したバイオフィルムが厚くなりすぎるため、数年に一度は砂を入れ替える必要があります。カートリッジフィルターは使い捨てが前提なので、差圧上昇や所定の処理量に達したら新品と交換します。フィルターには寿命があることを念頭に置き、目詰まりが顕著になる前に早めの交換を心がけましょう。なお、フィルター交換時には、ろ材を通った後の配管内にも汚れや菌が繁殖している場合があるため、配管の洗浄・消毒も併せて実施すると効果的です。
- 運用条件の最適化: ろ過効率を維持するには、装置の運転条件も重要です。例えば膜ろ過では、クロスフローろ過(膜面に沿って水を流し一部だけ透過させる)を採用すると、膜表面の汚れ堆積を抑えられます。また、処理流速を上げすぎない、ろ過圧力を適正範囲に保つ、といった操作条件の最適化も目詰まり防止につながります。さらに、原水の季節変動に合わせて凝集剤注入量を調整し前処理効果を高めるなど、プロセス全体のチューニングが有効です。現場では日々の差圧や流量データを監視し、傾向変化を早期に察知して洗浄・交換計画に反映させることが求められます。
このように、適切な前処理・逆洗・洗浄と計画的な交換によって、ろ過装置は長期間にわたり安定した性能を発揮できます。逆に、メンテナンスを怠ると処理水の水質悪化や装置の容量低下を招き、最悪の場合ライン全体の停止につながりかねません。ぜひ定期メンテナンスを習慣づけ、ろ過効率の最適な維持管理に努めましょう。
膜ろ過技術の最新動向|MF・UF・RO膜の選定と運用
最後に、膜ろ過技術の最新動向について触れます。膜ろ過は近年ますます普及が進み、上水・排水処理からリサイクル水製造まで幅広い分野で採用されています。その背景には膜モジュールのコスト低下や技術革新があり、以前は高価だったROやUF膜が現在では経済的に導入可能になってきました。ここでは、MF・UF・ROといった膜の種類ごとの役割や選定ポイント、運用上の最新トレンドを概説します。
●膜の種類と選定ポイント: 前述のように、膜にはMF(精密ろ過)・UF(限外ろ過)・NF(ナノろ過)・RO(逆浸透)の種類があり、孔径サイズ順に除去できる物質が異なります。選定にあたっては、原水中に含まれる異物の種類と目標とする水質レベルを考慮します。例えば:
- MF膜(精密ろ過膜): 孔径がおおむね0.1~数μmと大きめで、濁質や細菌を除去するのに適します。処理水量あたりのコストが低く、水道の高度処理(クリプトスポリジウム対策)や下水処理水の再利用などで広く使われます。ただしウイルスや溶解成分までは除去できないため、それらが問題となる場合は後段にUFやROが必要です。
- UF膜(限外ろ過膜): 孔径が数nm~0.1μm程度で、ウイルスやコロイド粒子、高分子有機物まで除去できます。上水処理ではMFでは残存するウイルスの除去に、製薬分野ではエンドトキシン除去に利用されています。また、浄水場や工場排水の高度処理でMFとUFを連結し二段ろ過するケースもあります。UF膜単独で使うより前段にMFを置いた方が、膜ファウリングが抑制でき効果的です。
- NF膜(ナノろ過膜): 孔径が1nm程度と極めて小さく、二価イオンや一部有機化合物を選択的に除去します。硬度成分(Ca²⁺やMg²⁺)の除去や、有機汚染(農薬など)のさらなる低減に利用されます。NFは脱塩性能も持ちますがROほどではなく、一価イオンは一部透過します。そのため、軟水化や部分的な脱塩が目的の場合に適しています。例えば地下水から硬度を下げつつ有機物を除去したいときにNF膜が活躍します。
- RO膜(逆浸透膜): 孔径が0.0001μm以下という半透膜で、ほとんどあらゆる溶存イオン・分子を物理的に遮断できます。食塩すら除去できるため、海水淡水化装置の核心技術です。また超純水製造でもROが中心的役割を果たします。RO膜は最も高精度な反面、ポンプ圧力やエネルギー消費が大きく、他の膜に比べ目詰まりもしやすい傾向があります。そのため前段にMF/UFで大きな異物を除去し、複数段ROで段階的に脱塩するのが一般的です。ROの導入可否はコストと必要水質のバランスで判断されます。近年ではROとイオン交換樹脂を組み合わせ、運転コストを抑えつつ高純度水を得るハイブリッドシステムも増えています。
膜の選定においては以上のように「原水に何が含まれ、どのレベルまで除去すべきか」を軸に考えます。一つのプラントでMF→UF→ROを多段併用することもあれば、必要に応じて単一段の膜にとどめる場合もあります。例えば水道水の浄化ではUF膜で細菌・ウイルスを除去すれば十分なケースが多く、一方リサイクル水や超純水ではROまで経て高純度化します。膜技術は柔軟な組み合わせが可能な点も特徴と言えるでしょう。
●膜ろ過設備の運用と最新トレンド: 膜ろ過設備を安定運用するには、やはりファウリング対策とメンテナンスが鍵になります。前節で述べた目詰まり対策は膜システムでも同様で、原水に応じて前処理を強化し、定期的な逆洗・薬洗をスケジュールします。最近の膜装置はIoT技術により、リアルタイム監視で膜差圧や透水量の異常傾向を検知し、自動的に洗浄サイクルを調整する高機能なものも登場しています。これにより運転管理が簡便化し、膜寿命の延長やダウンタイム短縮につながっています。
また、膜そのものの技術革新も見逃せません。低ファウリング膜(親水化処理膜など)の開発や、セラミック膜の実用化により、従来は膜適用が難しかった高濁度・高温の液体処理にも膜が使われ始めています。セラミック膜は耐薬品・耐熱性が高く、食品工場の高温排水や油分含む排水でも性能を発揮します。価格は高めですが繰り返し洗浄再生して長期使用できるため、トータルコストで有利なケースもあります。
さらに、MBR(膜分離活性汚泥法)の普及も重要なトレンドです。これは生物処理と膜ろ過を一体化したシステムで、下水処理場や産業排水処理で省スペース・高効率を実現します。従来の沈殿槽を膜に置き換えることで処理槽を小型化でき、得られる処理水は高い清澄度を誇ります。近年はMBR処理水をさらにRO膜で処理して超純水レベルまで再生し、工場で再利用する「水リサイクルシステム」も各地で導入されています。水資源の有効活用と排水削減の観点から、膜技術はサステナビリティの担い手として期待されているのです。
膜市場の動向として、世界的に見ると今後も年率6~7%程度で成長が見込まれています。特に水需要が拡大するアジア地域で海水淡水化や上下水道整備に膜ろ過が採用され、技術と市場規模の両面でさらなる発展が予想されます。膜ろ過技術はまさに日進月歩であり、より低コストで高性能な膜モジュールや高度な運用制御システムが次々に生み出されています。排水処理に携わる私たちも、この流れにアンテナを張り、適切な膜技術をタイムリーに取り入れていくことが重要でしょう。
アクトのろ過処理改善実績|処理精度向上とランニングコスト削減の成功事例
株式会社アクトでは、これまで数多くの排水処理プロジェクトでろ過技術の改善提案と導入を行い、処理精度の向上とコスト削減を実現してきました。ここでは、その一部事例と同社技術の特徴をご紹介します。
アクトは、自社開発の無機系凝集剤「水夢(Suimu)」や中和剤「融夢(Yumu)」、そして小型凝集分離ろ過装置「ACT-200」などを組み合わせ、お客様ごとの排水に最適な処理ソリューションを提供しています。従来は処理困難とされた重金属含有排水や水性塗料排水でも対応可能で、単に薬剤単価を追求するのではなく排水処理のトータルコストを50~70%削減することを目指した提案が特徴です。実際、「水夢」を導入した企業では、沈殿汚泥量の大幅削減や廃棄物処理費の圧縮に成功したケースが多数あります。また、水夢シリーズは国土交通省・農林水産省からの認定実績を持ち、2011年の福島原発事故後には汚染水処理にも採用されるなど、その高い信頼性が評価されています。
例えばある金属加工工場の排水処理改善事例では、従来の凝集剤では処理が難しかった微細な研磨スラッジに対し、アクトが特注ブレンドした「水夢」凝集剤を用いることで汚濁物の分離が飛躍的に向上しました。凝集+ACT-200装置で処理した結果、処理前COD(Cr)15,600 mg/Lの排水が、凝集沈殿後には540 mg/L、さらに循環ろ過2時間で210 mg/Lまで低減し、環境基準を大きく下回る水質を達成しました。これは約98%の有機汚濁削減に相当し、排水の処理精度が格段に向上したことを意味します。また、発生した沈殿汚泥も、自然脱水後は200L中わずか8.5kg(50L相当の沈殿が減量)となり、廃棄物量95.7%削減という大幅な減容化を実現しました。これにより産廃処理コストが劇的に減少し、経済的メリットも得られています。
別の塗装工場の事例では、塗料洗浄廃液の処理において、水夢凝集剤によって塗料成分を効果的に分離除去し、活性炭フィルターで色素と臭気を吸着する方法を提案しました。結果、処理水の色度とCODが大幅に改善し、地元排水基準の余裕をもってクリア。さらに循環再利用することで年間数百トンの水使用量削減と排水負荷低減につながりました。従業員からは「これまで悩みの種だった悪臭が解消した」「薬剤投入量が減りランニングコストが下がった」と好評で、アクトの提案が付加価値を生んだ好例と言えます。
アクトの「水夢」シリーズは、「既存の凝集剤では効果が不十分…」という課題に応えるため、排水の性質に合わせたオーダーメイド品の開発にも取り組んでおり、多様な業界からの相談に応えています。また、小型凝集分離装置ACT-200は専門知識がなくても扱いやすいシステムで排水処理を強化でき、実際に「現場の手間が減り助かっている」「凝集+ろ過の組み合わせで安定運転が可能になった」といった声が寄せられています。
このようにアクトは、高度なろ過技術と凝集沈殿技術を組み合わせることで、処理水質の向上とコストダウンを両立するソリューションを実現しています。単に規制値をクリアするだけでなく、ESGの観点から環境負荷そのものを減らすことを目指し、各企業の排水課題に応じた最適解を提案しています。もし現在の排水処理にお困りであれば、ぜひアクトにご相談ください。培ってきた技術力と豊富な実績をもとに、一歩先を行く排水処理で皆様の事業をサポートいたします。

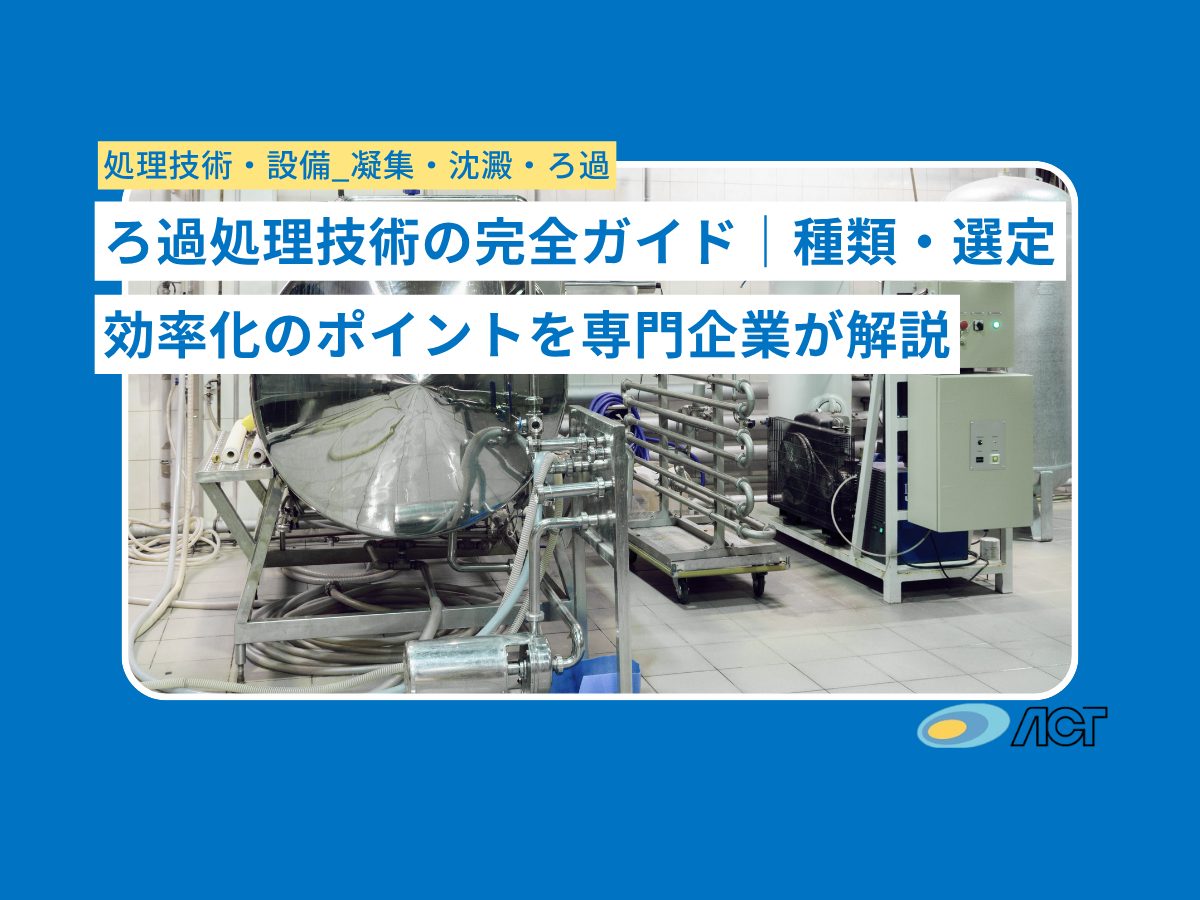
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)