工場や事業所から出る排水を環境に無害化するうえで、生物処理(微生物による汚濁物質の分解)は物理処理・化学処理と並ぶ重要な手法です。特に有機汚濁(BODやCOD)が高い排水では、生物処理によって効率的に汚染負荷を低減できます。一方で、生物処理を安定稼働させるには微生物の管理や設備設計に専門的なノウハウが必要です。また、水質汚濁防止法に基づき排水中のBODやpH、窒素・リン含有量など約30項目に厳しい基準値が定められており、これを確実にクリアする高度な処理システムの構築も求められます。
本記事では生物処理の基本原理(好気性・嫌気性微生物による有機物分解メカニズム)から生物処理法の種類と特徴(活性汚泥法・生物膜法・MBBR・SBRの比較)、業界別生物処理システムの最適化事例(食品・化学・製薬工場の排水特性と対策)、そして微生物管理と運転制御のポイント(MLSS・SVI・DO管理)や生物処理の高度化技術(窒素・リン除去や難分解性物質への対応)まで網羅的に解説します。最後に、アクトの豊富な実績に基づく生物処理最適化ソリューションをご紹介し、処理プロセスの安定化や省エネルギー化を実現した成功事例と同社の技術力についても触れます。工場・事業所の排水管理担当の方で、生物処理システムの基礎から応用、最新動向まで一通り把握したい方はぜひ参考にしてください。
生物処理の基本原理|好気性・嫌気性微生物による有機物分解メカニズム
生物処理とは、排水中の有機汚濁物質を微生物に“食べさせて”分解させる処理方法のことです。微生物が栄養源とするのは排水中のBOD成分(有機物)であり、それを代謝して最終的に二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)などに分解します。微生物には大きく分けて好気性と嫌気性の種類があり、それぞれ働く条件や生成物が異なります。
- 好気性微生物: 酸素を必要とする微生物で、活発な代謝には十分な溶存酸素(DO)が不可欠です。好気性菌は有機物を酸素で酸化し、水とCO₂に分解してエネルギーを得ます。この仕組みを利用した排水処理が好気性生物処理であり、代表例が後述する活性汚泥法です。好気性処理は比較的短時間で高い有機物除去率が得られ、下水処理場や産業排水処理で広く採用されています。
- 嫌気性微生物: 酸素を必要としない微生物で、酸素がない環境下でも生育・代謝できます。嫌気性菌の中には、硝酸塩中の酸素を利用して硝酸を窒素ガスに還元するもの(脱窒菌)もおり、これは窒素含有排水の脱窒プロセスに利用されています。また、酸素があると生存できない絶対嫌気性の微生物も存在し、その代表がメタン生成菌です。メタン生成菌は有機物分解の最終段階でメタンガス(バイオガス)を産生し、エネルギー資源としての回収が可能なため近年注目されています。嫌気性処理では有機物が最終的にメタンやCO₂、水に分解され、副生成物としてのバイオガスを得られる点が特徴です。
上述のように、生物処理では微生物が排水中の汚染物質を分解・無害化します。ただし処理に時間がかかるものの、大量の有機性排水を比較的低コストで処理でき、生成される汚泥(微生物の死骸など)も安定した性状になるという利点があります。一方で、温度やpH、溶存酸素など環境条件の影響を受けやすく、排水中に重金属などの有害物質が含まれると微生物が死滅してしまい適用できないという制約もあります。そのため、生物処理システムを設計・運用する際は、微生物が活発に働ける最適な環境条件を整えるとともに、排水の特性に応じて他の処理法(物理・化学処理)もうまく組み合わせることが重要です。
生物処理法の種類と特徴|活性汚泥法・生物膜法・MBBR・SBRの比較
一口に生物処理と言っても、微生物をどのように保持し活用するかによってさまざまなプロセスの種類があります。ここでは代表的な活性汚泥法(浮遊法)と生物膜法(付着法)を中心に、派生技術であるMBBRやSBRの特徴を比較します。
活性汚泥法(従来型好気性処理)の特徴
活性汚泥法は最も一般的な好気性生物処理方式で、下水処理場をはじめ工場排水でも広く採用されています。曝気槽(エアレーションタンク)内に微生物の群れである活性汚泥(フロック状の微生物凝集体)を浮遊させ、空気を吹き込んで有機物を分解させるプロセスです。活性汚泥法では有機物除去効率が高く、大量の排水にも対応できるという利点があります。例えば食品工場など高濃度有機排水でも、適切に管理された活性汚泥法によりBOD除去率95%以上を安定的に達成し、厳しい排水基準をクリアしたケースもあります。
一方で活性汚泥法は、沈殿分離の工程(二次沈殿槽)が必要になる点に留意が必要です。微生物フロックを処理水から分離するため、大きな沈殿槽を設けて十分な時間沈降させる必要があり、設備が大型化しがちです。沈殿槽で分離・回収された汚泥は一部を曝気槽へ返送(再利用)し、残りは余剰汚泥として排出します。この汚泥循環と排出(汚泥引き抜き)によって、微生物量(MLSS)や汚泥の滞留時間(SRT)を調節し、処理性能を維持するのが活性汚泥法運転のポイントです。適切なMLSS濃度に保つことで処理が安定し、効率的な有機物分解が可能になります。
活性汚泥法の課題としては、汚泥の沈降性が悪化するトラブル(バルキング)が挙げられます。後述するSVIの管理で詳述しますが、微生物の種類や栄養バランス、DO不足などが原因でフロック形成不良や糸状菌(フィラメント)の増殖が起こると、沈殿槽で汚泥が沈まず浮遊・流出してしまう現象が発生します。バルキングが起こると処理水中に汚泥が漏出して水質悪化を招くため、活性汚泥法では日々の汚泥性状の監視と予防策が重要です。以上のように沈殿槽や汚泥管理が必要ですが、総じて活性汚泥法は実績の豊富なオーソドックスな生物処理であり、多様な排水に適用可能な汎用性の高さが強みと言えます。
生物膜法(付着生物法)の特徴
生物膜法は、微生物をろ材や担体の表面に付着させて繁殖させる処理方式で、活性汚泥法に対して「付着固定式」の生物処理と呼ばれます。代表例として散水ろ床や回転生物板(RBC)など下水処理で古くから使われてきた方式があります。生物膜法では、微生物が付着したろ材に排水を接触・浸透させることで有機物を除去します。付着した微生物膜(バイオフィルム)が汚濁物質を吸着・分解し、ろ材のろ過効果も加わって処理水中の固形物も同時に低減できる点が特徴です。
生物膜法のメリットは、設備がコンパクトにできることです。活性汚泥法のような大きな沈殿槽を必要とせず、ろ材上で微生物と処理水を分離できるため、処理装置全体の省スペース化につながります。また、微生物の保持時間が長くなる傾向があり、負荷変動にも強いとされています。排水負荷が一時的に増減しても、生物膜上の微生物群が安定しているため処理水質が急激に悪化しにくい利点があります(活性汚泥法より衝撃負荷に耐性がある、とされます)。さらに、付着生物法では一般に汚泥発生量が少なめで、余剰汚泥の処理負担を低減できる場合もあります。
一方、デメリットとしてろ材の目詰まりがあります。固定式の生物膜法(例: 固定床ろ過法)では、微生物の繁茂や捕捉された懸濁物質によって徐々にろ材が詰まり、水流抵抗が増大します。そのため定期的に逆洗(逆方向から水や空気で洗浄)を行って余分な生物膜を剥離・排出する必要があります。逆洗設備や運用の手間がかかる点は留意すべきでしょう。また、処理能力当たりの微生物量が活性汚泥法に比べ少なく(ろ材の容積の一部しか微生物が占めないため)、高濃度の排水では単独では対応しきれない場合もあります。このため、生物膜法は活性汚泥法と組み合わせたハイブリッドで使われることも多く、後述のMBBRなどはその一例と言えます。
MBBR(担体流動床法)の特徴
MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor、担体流動床生物膜法)は、生物膜法の一種ですが小型の担体(キャリア)を曝気槽内で流動させることで、生物膜方式と活性汚泥方式の長所を併せ持つプロセスです。担体としては比重が水とほぼ等しいプラスチック製のチップなどが用いられ、曝気の気流や撹拌によって槽内を漂うように設計されています。その担体表面に微生物膜が形成され、有機物分解が行われます。
MBBRの最大の特徴は、担体が流動・衝突することで常に適度な厚みの生物膜が維持される点です。生物膜が厚くなりすぎると内部まで酸素や基質が行き渡らなくなりますが、MBBRでは担体同士がぶつかり合って過剰な生物膜を自動的に剥離してくれます。そのため固定式の生物膜法のように定期的な逆洗をせずとも、生物膜の自己更新が図れるメリットがあります。また、担体が槽内を移動することで微生物と基質(汚濁物質)がよく混合し、効率的な分解反応が進む利点もあります。担体を充填することで実質的な微生物担持面積が増え、同じ槽容積でも処理能力を高められるため、既存の活性汚泥槽に担体を追加投入して能力増強する改造も行われています。
一方でMBBRでは、剥離した生物膜(微生物フロック)が水中を漂った状態になります。固定床ろ過方式と違い、槽内で固形物を完全には捕捉できないため、処理水中のSS濃度はやや高めになります。河川や海域など環境中へ放流する場合には、後段に沈殿分離や凝集浮上処理を追加してSSを基準内までさらに低減させるのが一般的です(下水道に放流する場合は下水処理場側で除去されるため後処理を簡略化できるケースもあります)。このようにMBBRは単独で完結するというより他の工程との組み合わせを前提としたプロセスですが、高負荷有機排水のプレ処理や既存設備の性能向上策として世界的に普及が進んでいます。
SBR(回分式活性汚泥法)の特徴
SBR(Sequencing Batch Reactor、回分式活性汚泥法)は、活性汚泥法の一種ですが処理工程を時間的に区切って一つの槽で完結させる方式です。具体的には1つ(または複数)の反応槽で、「注水(充填)→曝気(反応)→沈殿→排水→待機」のサイクルを順次繰り返すことで連続的な処理を行います。この方式では沈殿槽を別途設ける必要がなく、同じタンクで処理と沈降分離を行うため、設備構成が簡素化・コンパクト化できる利点があります。特に中小規模の排水処理プラントで広く使われており、必要に応じて並列タンクで交互運転させることで連続流入にも対応します。
SBRのメリットは、運転の柔軟性と処理水質の良好さです。バッチ処理方式のため、流入負荷や水量の変動に合わせて曝気時間や沈殿時間を調整しやすく、多様な排水条件に適応できます。また、1サイクル内で無酸素状態と好気状態を作り出すことができるため、工夫次第で脱窒やリン除去など高度処理にも対応可能です。実際、SBR方式は都市下水の高度処理にも採用例があり、従来方式に比べ悪臭が少なく都市部にも適するとの報告もあります。処理水の水質も、適切に運転管理されたSBRでは安定して高い水準を維持できます。
一方でSBRの課題としては、エネルギー消費量が比較的多い点が指摘されます。好気性処理である以上、曝気による電力消費は避けられませんが、回分式では負荷対応のために過剰曝気しがちな運用となるケースもあり、運転コスト高につながる恐れがあります。また、適切な運転制御の重要性も挙げられます。各工程の時間配分やDO制御など管理が不十分だと処理効率が低下する可能性があり、オペレーターには一定の知識と経験が求められます。しかし総じて、SBRは下水・産業排水問わず世界中で導入が進む実証済み技術であり、日本国内でも中小規模の排水処理場で数多く稼働しています。その省スペースで高度処理が可能な点から、今後も適用範囲が広がることが期待される方式です。
なお、近年では活性汚泥法に膜分離技術を組み合わせた膜分離式活性汚泥法(MBR)も普及が進んでいます。MBRはろ過膜で微生物と処理水を分離するため沈殿槽を省略でき、高度な処理水質(SSや細菌類をほぼ含まない透明な処理水)を得られる最新技術の一つです。膜によって微生物を閉じ込めることでMLSS濃度を8,000~15,000mg/L程度の高濃度に維持できるため、反応槽をコンパクトにしつつ有機物をしっかり分解できます。ただし膜分離にはコストがかかるほか、膜の定期的な清掃や交換といったメンテナンスが必要です。MBRは高水質再利用やスペース制約の厳しい現場で導入が増えており、活性汚泥法の発展形として注目されています。
業界別生物処理システム|食品・化学・製薬工場での最適化事例
排水の性質は業種によって大きく異なり、それに伴い最適な生物処理プロセスや運用上のポイントも変わってきます。ここでは食品工場、化学工場、製薬工場それぞれの排水特性と、生物処理システム最適化の事例・ポイントを解説します。
食品工場の排水における生物処理最適化
食品工場排水は一般に有機物濃度(BOD値)が非常に高いことが特徴です。原料の残渣や油脂、糖分などが多量に含まれるため、排水をそのまま放流すれば環境中で微生物が急激に繁殖し、DOを消費して水域の酸欠(富栄養化)を招くおそれがあります。そのため食品工場では生物処理がほぼ必須であり、活性汚泥法を中心に有機物の徹底分解を図ります。
生物処理を導入することで、BODの大幅低減(90%以上の除去率)も十分可能です。例えばある食品工場では、生物処理設備の導入後に排水BODを95%以上削減し、安定的に排水基準を満たせるようになったとの報告があります。また食品排水には油脂分由来の悪臭も付きまといますが、生物処理によって臭気の原因となる有機物を分解することで臭気低減にも効果があります。嫌気性処理と好気性処理を組み合わせることで、より確実な脱臭が可能になった事例もあります。
さらに、食品工場排水には有機物だけでなく窒素やリンの濃度が高いケースがあります(原料由来のたんぱく質や添加物由来のリン酸塩など)。こうした栄養塩類の除去も環境保全上重要であり、河川・湖沼の富栄養化防止のため排水中の窒素・リンに規制が課される地域もあります。対策として、生物学的脱窒・脱リンが可能なプロセスが導入されます。その一例がA₂O法(嫌気-無酸素-好気法)で、嫌気→無酸素→好気の3槽を循環させることで窒素とリンを同時に生物的に除去できます。最新の研究では、A₂O法により窒素除去率94.6~95.2%、リン除去率97.0~98.1%**を達成した報告もあり、高度処理技術として食品工場でも実用化が進んでいます。食品工場ではこのように高濃度有機汚濁の除去を軸に、必要に応じて脱窒・脱リンまで含めたシステム最適化が図られます。
生物処理導入にあたっては、前処理として固形物や過剰な油分の除去も重要です。食品排水はSSや油脂が多いため、スクリーンやグリーストラップで大きな固形物・油を除去し負荷低減してから生物処理槽に送るのが一般的です。場合によってはUASBなどの嫌気性処理を前段に置き、高濃度BODをメタン化ガス化してから残留BODを好気処理する二段構成とし、全体の負荷とランニングコストを下げる手法もとられます。嫌気→好気の組み合わせは上述のように臭気対策にも有効で、得られたバイオガスをボイラー燃料に利用することでエネルギー回収することも可能です。食品工場では原料ロスや清掃工程から多量の有機汚泥(スラッジ)が発生しますが、嫌気処理併用により汚泥発生量自体を減らすことにもつながり、処理コスト削減効果があります。
化学工場の排水における生物処理最適化
化学工場排水は、微生物による分解が困難な難分解性物質を含む場合が多い点が特徴です。例えば有機合成化学工場の排水には、ベンゼン環やハロゲンを含む安定な化合物、揮発性有機物(VOC)、難生分解性の合成樹脂や界面活性剤などが含まれ、生物処理だけでは十分に分解できないことがあります。また、製造プロセスで使われる溶剤や触媒(金属類)、副産物としての有害化学物質が微量でも残留していると、前述のように微生物の活動を阻害し処理不調を招く可能性があります。
そのため化学工場の排水処理では、前処理と生物処理の組み合わせによって難分解性物質への対策を講じるのが効果的です。具体的には、排水中の手強い化合物を微生物が分解できる形に事前に部分分解するための高度酸化処理(AOP)を導入します。例えばオゾン処理やUV過酸化水素処理(UV/H₂O₂)といった強力な酸化手段で難分解性物質の構造を切断・改質し、その後の生物処理で分解可能な状態にします。ある適用例では、オゾンのマイクロナノバブル処理を前段に施し、その後に活性汚泥処理を行うことでCOD除去率が従来より30%以上向上したとの報告があります。このように化学的前処理+生物処理のハイブリッドは、難分解性CODを効果的に低減する有効策です。
また、排水中の特定有害物質を分解できる特殊な微生物を活用するアプローチもあります。実験室レベルでは、ある塩素系有機化合物を分解できる菌を用いることで、従来処理困難だった有害物を無害化できた例も報告されています。実プラントでも、例えば油分解菌を培養槽に添加してグリスや機械油を含む廃水の処理効率を高めたり、脱窒菌を投入して窒素除去性能を向上させたりといった応用が検討されています。もっとも、培養菌を排水処理に導入する際は既存の微生物群との生存競争や増殖条件の管理が課題となるため、専門家の指導のもと慎重に実施する必要があります。
なお、化学工場排水では重金属の混入も無視できません。触媒や顔料、腐食生成物などから銅・亜鉛・クロム等が含まれるケースでは、生物処理だけで重金属除去は困難なため薬品沈殿法との組み合わせが必須です。一般的には排水中の重金属は生物処理の前に中和沈殿させて除去し、その後残留有機物を生物処理するフローがとられます。一方で最近の研究では、微生物の還元作用を利用して重金属の毒性や溶解度を下げる試みも報告されています。たとえば、ある種の細菌は有毒な六価クロム(Cr⁶⁺)を三価クロム(Cr³⁺)に還元でき、後段の凝集沈殿処理の効率を高めるのに役立ちます。実際、この方法によりクロム除去率を90%以上に向上させた例もあります。最終的には生物処理で有機物を分解→化学処理で重金属を沈殿除去という多段階プロセスで、COD95%以上・重金属99%以上の高い除去率を達成したケースも報告されています。このように化学工場では、排水中の汚染物質ごとに適切な処理法を組み合わせるオーダーメイド設計が重要であり、生物処理はその中心的役割を果たします。
製薬工場の排水における生物処理最適化
製薬工場排水も化学工場と似た側面がありますが、特有の課題として抗生物質や生理活性物質の残留が挙げられます。医薬品製造プロセスでは、抗菌剤やホルモン剤、中間体など強い生物作用を持つ化合物が微量ながら排水中に混入する場合があります。これらは環境中での生態影響(例えば耐性菌の出現や内分泌かく乱)が懸念されるため、排水中で極力分解・除去することが望まれます。しかし、抗生物質などは処理槽内の微生物そのものにダメージを与え、生物処理の働きを低下させてしまう可能性があります。
そのため製薬排水では、微生物に対する毒性を緩和する工夫が求められます。一つは前述の高度処理(オゾン処理等)を用いて、薬剤成分をあらかじめ分解・失活させておく方法です。オゾンは医薬品成分の分解にも有効とされ、例えば抗生物質の一種をオゾン処理して分解率を高めた研究報告があります。また、活性炭吸着との組み合わせも有力です。難分解・有害な微量成分は生物処理ではなく活性炭に吸着させて物理的に除去し、処理水への残留を防ぐ手法です(実際、下水処理場の高度処理ではオゾン+活性炭が採用例あり)。製薬工場でも、生物処理では除去しきれないppbレベルの薬剤成分を、最終的に活性炭処理で補完して環境中への放出を防ぐケースがあります。
もちろん、生物処理自体の最適化も重要です。製薬排水は化学的酸素要求量(COD)や全有機炭素(TOC)が高い一方で、生物が利用できる栄養素(窒素・リン)が不足することがあります(製薬プロセスでは有機炭素源が多く、窒素やリンは添加しない場合がある)。そのような場合、適切な栄養比(BOD:N:P)になるよう不足分の窒素源・リン源を補給し、微生物の増殖を促す必要があります。栄養バランスが崩れると微生物の活性が低下し、処理不調やバルキングの一因となります。製薬排水では特に高度な処理水質が要求されることから、長時間曝気処理(延長エアレーション)やMBRの導入によって分解時間を確保し、生物懸濁固形物の流出を徹底的に防止する対策もとられます。
近年の取り組みとして、製薬排水中の特定物質を標的に分解できる酵素や微生物株の活用も研究されています。例えばホルモン剤や難燃性化合物について、それを基質に生育できる土壌由来菌をバイオスティミュレーション(活性刺激)することで処理槽内で分解させる手法などです。実プラント適用にはハードルもありますが、将来的には遺伝子改変微生物など先端技術の導入で、製薬排水の生物処理効率が飛躍的に高まる可能性もあります。
総じて製薬工場では、生物処理+高度処理+吸着処理といった多重防御で微量有害成分まで対策しつつ、安定した有機物除去を図る戦略が求められます。法規制上も製薬業は水質汚濁防止法の特定施設に該当するケースが多く、排水基準の遵守と環境リスク低減の両面から綿密な処理システム設計が必要です。
微生物管理と運転制御|MLSS・SVI・DO管理のポイント
生物処理システムを安定稼働させるには、微生物(汚泥)の状態を適切に管理し、処理槽の運転条件を制御することが欠かせません。ここでは代表的な管理指標であるMLSS、SVI、DOについて、その意味と管理のポイントを解説します。
- MLSS(Mixed Liquor Suspended Solids): MLSSは混合液浮遊物質量とも呼ばれ、曝気槽内に浮遊する活性汚泥(微生物+未分解有機物)の濃度を示す指標です。単位は mg/L で表し、数値が高いほど槽内の微生物量が多いことを意味します。適正なMLSS濃度は処理方式によって異なりますが、標準的な活性汚泥法ではおおよそ2,000~4,000 mg/L、長時間曝気法では4,000~8,000 mg/L程度が目安とされています(MBRでは8,000~15,000 mg/Lと高濃度で運転します)。MLSSは多すぎても少なすぎても問題で、濃度が高すぎると汚泥が沈降しにくくなり(後述のSVI悪化)反応槽内への酸素供給効率も下がります。逆に低すぎると処理すべき有機物に対して微生物数が不足し、分解能力が発揮できません。したがって設計上定められた適正範囲内にMLSSを維持することが重要です。運転管理では、定期的にMLSS濃度を計測し、余剰汚泥の引き抜き量を調整することで狙った濃度にコントロールします。例えば排水負荷の増加に伴いMLSSが低下傾向なら汚泥排出を減らして生物量を増やし、逆にMLSS過多で沈降不良の兆候があれば汚泥排出を増やして若返りを図る、といった具合です。また、MLSSの質も重要で、MLSS中の有機成分割合(MLVSS)や微生物群集の健全性にも目を配ります。
- SVI(Sludge Volume Index): 汚泥容積指数とも訳されるSVIは、活性汚泥の沈降性能(沈みやすさ)を表す指標です。測定方法は、曝気槽の混合液を採取して静置し、30分後に沈殿した汚泥の体積(SV)[%]を測定、それをMLSS濃度で割って算出します。単位は mL/g で、数値が小さいほど同じ濃度の汚泥がコンパクトに沈む、つまり沈降性が良好であることを意味します。一般に正常な活性汚泥のSVIは50~150 mL/g程度で、これくらいの範囲に収まっていれば沈降分離は順調と判断されます。SVIが200 mL/gを超えるようだと沈降性が悪化している状態で、汚泥が膨張して沈まないバルキングの可能性があります。実際、糸状性菌が増殖する糸状性バルキングや、汚泥の含水率が高まる非凝集性バルキングではSVIが300以上になることもありえます。SVIが高騰し沈殿槽の汚泥界面が上昇してきたら、早急に原因を調べ対策を講じる必要があります。対策例としては、DO不足の解消(低酸素が糸状菌増殖を招く場合)、栄養塩の添加(BODに比べ窒素・リンが不足すると菌体合成が滞りバルキングに至る場合がある)、負荷抑制(流入有機負荷が設計を超えると微生物増殖バランスが崩れる)などが挙げられます。糸状性バルキングが顕著な場合、最終手段として塩素剤の投与により糸状菌を選択的に死滅させる方法も実務的には採用されています(ただし効果は一時的で根本解決にはならないため、並行して長期的な原因除去策を講じる必要があります)。いずれにせよSVIは活性汚泥の健康状態を示す重要なバロメーターであり、定期的に計測して適正範囲(50~150程度)に収まるよう運転条件を調整することが、生物処理安定化の鍵となります。
- DO(溶存酸素): DOは曝気槽内の水中に溶けている酸素の濃度(mg/L)で、好気性生物処理では常にモニターすべき重要パラメータです。微生物が十分な代謝を行うには最低でも約0.1~0.3 mg/Lの酸素が必要とされ、実際の処理では少なくとも2 mg/L程度のDOを維持するのが一般的な目安となっています。多くの処理施設では、フロック内部まで酸素を行き渡らせるためDO約2 mg/L以上を確保する運転が推奨されています。DOが2 mg/Lを下回るとフロック中心部が無酸素状態となり、内部の微生物が死滅してフロックが崩壊することがあります。DO不足は微生物の代謝低下を招くだけでなく、嫌気的に増殖する糸状菌の繁殖を促してバルキングの原因にもなります。そのためエアレーションによる十分な酸素供給が不可欠ですが、一方でDOを高くしすぎることにも注意が必要です。DO過多の環境では不要なエネルギーを消費するだけでなく、低栄養条件下で好ましくない微生物(例えば一部の糸状性菌)が増殖しやすくなるとの指摘もあります。実際、曝気工程は排水処理プラント全体の30~60%の電力を消費するとされ、DO制御の適正化は省エネの観点から極めて重要です。米国EPAの試算によれば、DOセンサーを導入して自動制御することで曝気に伴うエネルギーコストを最大50%削減できた例もあるとのことです。したがって運転管理では、目標DO値(例えば2 mg/L前後)を設定し自動溶存酸素計と連動したブロワー制御を行うなど、適切なDO維持と省エネの両立を図るのが望ましいでしょう。
以上、MLSS・SVI・DOの3点は生物処理プロセス管理の柱となる指標です。このほかにもpH(中性付近が望ましい)、温度(メソフィル菌なら20~35℃程度が活発)、ORP(酸化還元電位)や残留アンモニア・硝酸濃度のモニタリングなど、必要に応じて様々な項目を管理します。最終的には「微生物が快適に働ける環境」を維持することが、生物処理を安定稼働させ高い処理性能を引き出すポイントと言えるでしょう。
生物処理の高度化技術|窒素・リン除去・難分解性物質対応
環境規制の強化や処理水の再利用ニーズの高まりに伴い、従来の生物処理をさらに発展させた高度処理技術が数多く開発・実用化されています。ここでは特に窒素・リンの生物学的除去と、難分解性物質への対応技術について概要を説明します。
- 窒素の除去(硝化・脱窒): 窒素は水域の富栄養化を引き起こす原因元素であり、工場排水中の窒素成分(主にアンモニア性窒素や有機性窒素)は環境基準達成のため除去が求められる場合があります。生物学的窒素除去は二段階のプロセスで行われます。一つ目は硝化で、好気性の硝化菌(亜硝酸菌・硝酸菌)がアンモニア(NH₄⁺)を酸化して硝酸(NO₃⁻)に変える反応です。これは十分な溶存酸素と長い滞留時間が必要なため、一般活性汚泥法ではひと工夫しないと完全には進みません。二つ目は脱窒で、通性嫌気性の脱窒菌が硝酸を窒素ガス(N₂)に還元する反応です。脱窒には酸素のない(無酸素)環境と、有機物(電子供与体)が必要です。これらを効率よく行うために考案されたのが循環式の嫌気・無酸素・好気プロセスです(前述のA₂O法など)。具体的には曝気槽をいくつかのゾーンに区切り、最初の無酸素槽で脱窒、後段の好気槽で硝化を行い、内循環で硝酸を前段に戻す仕組みを作ります。これにより最大で70~90%以上の全窒素除去率が期待できます。あるいはSBR方式で曝気と撹拌を時間制御して硝化と脱窒を交互に進める方法もあります。窒素除去には高度な制御が必要ですが、近年の下水・産業排水分野では標準的な技術となりつつあります。
- リンの除去(生物学的脱リン): リン(リン酸塩類)も富栄養化の原因元素であり、一部の湖沼や閉鎖性水域では排水中リン濃度に厳しい基準が設定されています。リン除去には従来、凝集沈殿による化学的除磷(薬品添加で難溶性リン酸塩を生成し沈殿させる)が行われてきましたが、近年は生物学的脱リン(生物化学的リン除去)が注目されています。これはPAO(リン蓄積菌)と呼ばれる微生物群の特性を利用した方法で、嫌気-好気のサイクルにより過剰なリン吸収を誘発してリンを除去します。具体的には、まず嫌気条件下でPAOが細胞内のポリリン酸を分解しリン酸を放出(同時に他の有機物を取り込む)します。続く好気条件で、PAOは先に取り込んだ有機物をエネルギー源にして大量のリン酸塩を再び細胞内に取り込み、通常以上に細胞内ポリリン酸を蓄積します。この時余分なリンが微生物体内に固定されるため、リンを含む汚泥を系外排出することで全体のリン量を削減できる仕組みです。生物脱リンを行うプロセスとしては、先述の窒素除去と組み合わせたA₂O法や、改良型のBardenphoプロセス、UCTプロセスなどがあります。生物脱リンでは最適な嫌気条件(硝酸や酸素が完全になく、かつ炭素源が豊富)の確保が鍵であり、時に外部炭素源(酢酸など)の添加も行われます。生物学的手法だけで達成困難な場合は、最終手段として薬品沈殿法(例えば塩化第二鉄やポリ塩化アルミニウムの添加)で微量残留リンを沈降除去して基準値を満たすケースもあります。いずれにせよリン除去は水域環境保全に直結するため、今後ますます高度処理技術の導入が進む分野です。
- 難分解性物質への対応: 先に化学工場の項で触れたように、生物処理だけでは分解しきれない難分解性有機物への対策としては高度酸化プロセス(AOP)の活用が有力です。オゾン、紫外線、過酸化水素、フェントン試薬(H₂O₂+Fe²⁺)などを駆使し、残留する頑固な化合物の化学結合を切断して小さく砕くことで、生物が扱いやすい形に変える手法です。これらAOPは電力や薬剤コストがかかるため適用範囲を見極める必要がありますが、特定の難分解性物質について処理効率が飛躍的に向上する例も多く報告されています。また、処理水のさらなる浄化を図る目的で活性炭吸着や膜処理を組み合わせるのも効果的です。生物処理後の処理水に粒状活性炭塔を通水すれば、微量残留する溶解性有機物や発色・臭気物質を吸着除去できます。あるいは精密ろ過膜や逆浸透膜で濾過すれば、難分解性物質のみならずイオンレベルの汚染物質まで物理的に除去可能です(もっともRO膜はコストと濃縮廃液処理の問題がありますが、再生水利用には選択肢となります)。
さらに、嫌気性生物処理技術の高度化も見逃せません。前述のUASB(アップフロー嫌気性汚泥床)プロセスは、嫌気性微生物を高密度に保持して高負荷有機排水を処理できる反応槽として発展してきました。UASBでは汚泥が顆粒化して沈降性が高まっており、長い滞留時間を確保することで増殖の遅いメタン生成菌も槽内に留め置けます。その結果、従来は難しかった高濃度排水の完全嫌気処理とバイオガス回収が可能となり、エネルギー創出型の排水処理として注目されています。実際、食品・飲料工場や畜産排水などでUASB導入が進み、好気処理と組み合わせて電力使用量を大幅に削減した例があります。また嫌気性処理では汚泥発生量が少なく抑えられるため、廃棄コスト低減や余剰汚泥の後処理負担軽減にも繋がります。今後は嫌気・好気ハイブリッドのAB法や、嫌気性と膜分離を組み合わせたAnMBR(嫌気性MBR)など、より効率的で省エネな生物処理プロセスが実用化していくでしょう。
このように、生物処理技術は窒素・リンなど栄養塩の同時除去や、難分解性汚染物質の対策など高度化が進んでいます。環境規制も年々強化される傾向にあり、新たな汚染物質(微量化学物質や医薬品残留など)への規制も拡大しつつあります。そうした将来ニーズに応えるためにも、生物処理技術のさらなる研究開発と、現場への適用が期待されます。
アクトの生物処理最適化実績|処理安定化と省エネルギー化の成功事例
ここまで生物処理システムの原理と技術について解説してきましたが、実際の現場で「どうやって安定運転や省エネ化を実現するか?」悩まれている方も多いでしょう。最後に、水処理専門企業である株式会社アクトが提供するソリューションによって生物処理の課題を解決し、法令遵守とコスト削減を両立した実績の一部をご紹介します。
アクトの技術力と実績: アクトは20年以上にわたり水処理技術の研究開発を続け、「一つとして同じ廃液はない」という理念のもとカスタマイズ対応力を磨いてきました。これまでに1,000社以上、延べ10,000種類を超える廃液に向き合って最適処理法を提案してきた実績があり、その膨大なデータベースに基づくノウハウは他社にない強みです。実際、官公庁・公共事業への技術採用(国土交通省・農水省認定)や福島原発汚染水の処理といった重大案件にも関わっており、累計340社以上の企業がアクトの製品を導入して排水課題を解決してきました。これはアクトの提供するソリューションが高品質基準を満たし信頼性が高いことの裏付けと言えるでしょう。
生物処理の安定運用・改善例: 例えば、ある塗料工場では従来の生物処理では対応困難だった水性塗料廃水に対し、アクト開発のゼオライト系凝集剤「水夢(SUIMU)」を用いた前処理と小型沈殿装置「ACT-200」を組み合わせることで、難処理だった顔料含有排水の固液分離に成功しました。その結果、同工場では年間処理コストを720万円から250万円へ約65%削減し、廃液発生量も月20トンから1トンへ約95%削減、さらには処理水の全項目で排水基準をクリアする高い環境効果を達成しています。処理作業も大幅に効率化され(1日3時間かかっていた作業が30分に短縮)、「驚くほど処理が簡便で短時間で誰でもできるようになった」というお客様の声もいただきました。この事例は、法令遵守と経済的メリットを同時に実現した好例と言えます。
他社との差別化ポイント: アクトの強みは、法規制の数値をただクリアするだけでなく「処理コスト削減」と「環境負荷低減」の両立を実現できる点にあります。自社開発した無機系凝集剤「水夢」は特許取得済みで、お客様それぞれの排水成分に合わせたオーダーメイド調合が可能です。従来の有機高分子凝集剤では処理困難だった排水(例えば水性塗料やインキ排水、重金属含有排水)にも対応でき、将来さらに厳格化する環境規制にも耐えうる高い浄化力を備えています。こうした革新的な薬剤技術と、装置・工程設計を含めた総合力によって、アクトは数多くの顧客企業から選ばれてきました。
今後ますます環境への責任が企業に求められる中、排水処理の最適化は事業継続の重要課題となります。アクトではこれまで培った高度な浄化技術と実績で、省エネ・高効率な生物処理システムを提案し、お客様の安定操業と環境保全を力強く支援いたします。生物処理システムの設計・運用でお困りの際は、ぜひ私たちアクトにご相談ください。

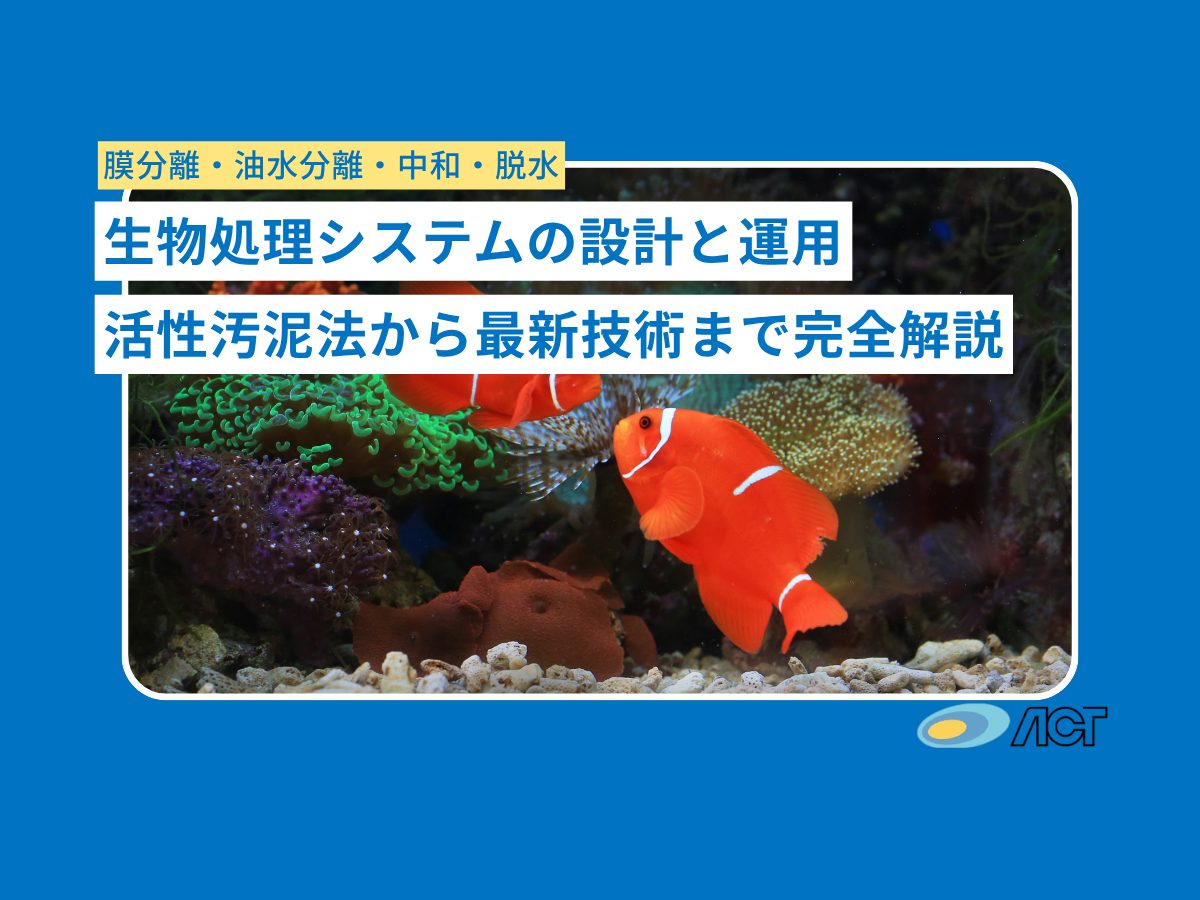
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)