工場や事業所から排出される水には、環境保護のため厳格な「排水基準」が設けられています。排水基準を正しく理解し遵守することは、企業の社会的責任であると同時に、罰則やトラブル回避のためにも欠かせません。本記事では、水質汚濁防止法に基づく排水基準の基本概念と法的根拠から、一律基準・上乗せ基準・横出し基準といった規制の種類、さらには業界別の規制ポイントまでをわかりやすく解説します。加えて、排水基準違反のリスクと罰則、基準をクリアするための対策技術、そして当社アクトの技術力と成功事例についても紹介します。工場の排水管理者や設備担当者の方は必見です。適切な対応によって法規制をクリアし、環境リスクとコストの両面を最適化するヒントをご提供します。
↑ 廃水処理に最適な凝集剤・アルカリ中和中和剤はこちら ↑
※モノタロウで購入するよりアクトから直接購入する方がお買い得。アクトから直接購入するにはinfo@act-yume.comに「購入希望」とメール
排水基準の基本概念と法的根拠
排水基準とは、工場や事業場から河川・湖沼・海域など公共の水域に排出される汚水中の汚染物質について定められた許容濃度の限度です。日本では水質汚濁防止法(1970年制定)に基づいて排水基準が設定されており、その目的は「国民の健康と生活環境を守ること」にあります。この法律により、特定施設を有する工場・事業場(特定事業場)は排出する水が排水基準を満たすよう義務づけられています。もし基準を超える汚水を流せば、人の健康や環境に悪影響を及ぼす恐れがあり、罰則の対象にもなります。
水質汚濁防止法では、規制対象となる設備を「特定施設」と定義しています。特定施設とは、有害な物質を含む水を排出しうる設備のことで、その種類は多岐にわたります。例えばメッキ槽や洗浄設備、湿式塗装ブースなど、業種ごとにさまざまな装置が特定施設に指定されています。自社の設備が特定施設に該当するかどうか判断が難しい場合は、所轄自治体や水処理の専門業者に相談するとよいでしょう。特定事業場(特定施設を設置する事業場)から公共用水域に排出される水は、すべて法で定められた排水基準に適合させなければなりません。
排水基準で規制される項目は大きく二種類に分類されます。一つは「人の健康項目」と呼ばれる有害物質で、もう一つは「生活環境項目」と呼ばれる水質汚濁の指標となる一般的な項目です。前者には重金属や有機溶剤など人の健康に害を及ぼす恐れのある物質が含まれ、後者にはBODやCODなど水環境の汚染状態を示す指標が含まれます。現行法では有害物質が27項目、生活環境項目が15項目設定されており、有害物質については排出量に関係なくすべての特定事業場に適用されます。一方、生活環境項目については1日あたり平均50m³以上の排水量がある事業場が規制対象となります(※50m³未満の場合でも、後述する条例により規制されるケースがあります)。これらの基準値は環境省令(排水基準を定める省令)によって細かく定められており、水質汚濁防止法の施行とともに全国一律で適用されます。
一律排水基準の項目と基準値
一律排水基準とは、国が全国共通で定めている排水中の汚染物質濃度の許容限度です。すべての特定事業場にまず適用される基本の基準で、水質汚濁防止法第3条に基づき定められています。一律基準の対象項目は前述のとおり「有害物質(健康項目)」と「その他の項目(生活環境項目)」に分かれています。有害物質には、カドミウム、鉛、シアン化合物、有機塩素系溶剤など工場排水に含まれる可能性のある毒性物質が網羅されており、それぞれ厳しい濃度上限が設定されています。例えばカドミウム及びその化合物は0.03mg/L、鉛及びその化合物は0.1mg/L、ジクロロメタン(有機塩素系溶剤の一種)は0.2mg/Lといった基準値が代表例です。これらの有害物質基準は健康被害を防ぐため極めて厳しく、検出下限値に近い濃度まで規制されています。
生活環境項目(一般排水項目)には、水質汚濁の程度を示す典型的な指標が含まれます。BOD(生物化学的酸素要求量)およびCOD(化学的酸素要求量)は各160mg/L(※日平均値は120mg/L)という基準が設定されており、SS(浮遊物質量)は200mg/L(※日平均150mg/L)が上限です。またpH(水素イオン濃度)については、排水先が河川など海以外の場合は5.8以上8.6以下、海域へ排出する場合は5.0以上9.0以下という範囲が定められています。油分についてはノルマルヘキサン抽出物質として規定され、鉱油類は5mg/L、動植物油脂類は30mg/L以下とされています。そのほか、大腸菌数(800個/mL〔日平均〕)や窒素・りんの含有量(窒素120mg/L〔日平均60mg/L〕、りん16mg/L〔日平均8mg/L〕)など、水域の富栄養化に関わる項目も基準化されています。これら生活環境項目の排水基準は、原則として1日50m³以上の排水を出す事業場に適用されます。
以上が国の定める一律排水基準ですが、各数値は科学的知見に基づいて環境省が設定しており、地域や業種を問わず共通に守るべき最低基準といえます。工場・事業者は、自らの排水中の各汚染物質濃度を測定し、これら基準を超えないよう適切な処理を施した上で放流する義務があります。万一基準を超えて排水した場合は、次に述べるような行政措置や罰則の対象となりますので、日頃から排水の水質管理を徹底する必要があります。
上乗せ基準・横出し基準の詳細
国の一律基準だけでは地域の水環境保全に不十分な場合、地方自治体(都道府県や市町村)は独自に上乗せ排水基準を条例で定めることが認められています。上乗せ基準とは、簡単に言えば**「国の基準より厳しい排水基準」のことです。たとえば国の一律基準でカドミウムが0.03mg/Lとされているところ、東京都の条例では0.003mg/Lというように10倍も厳しい値が設定されています。このような上乗せ規制は、工場の集積する湾岸地域など水質汚濁の深刻化を防ぐ必要がある地域で適用されます。また、多くの自治体では「裾下げ(すそさげ)基準」といって、国基準では規制対象外だった小規模事業場にも生活環境項目を適用するルールがあります。例えば熊本県では、1日平均排水量20~50m³未満の事業場にも生活環境項目の基準を適用する独自条例を定め、水質保全の強化を図っています。このように上乗せ基準や裾下げ基準により、各地域の実情に応じたきめ細かな水質管理が行われています。
一方で、水質汚濁防止法の対象外となっているケースを補完する目的で設けられるのが横出し基準です。横出し排水基準とは、国の法律では規制されていない物質や業種に対し、地方自治体が条例で独自に定める排水基準のことです。例えば、水質汚濁防止法上の特定施設を持たない小規模工場であっても、有害物質を含む排水を出している場合があります。法律の盲点となるそうした事業場を放置すれば地域の水質が悪化しかねません。そこで自治体は環境保全条例などにより、法の適用を受けない事業場にも横出し的に排水規制をかけることがあります。熊本県でも「生活環境の保全に関する条例」を制定し、水質汚濁防止法では対象外の施設や事業場を追加で規制対象に組み入れています。このように横出し基準によって、国の法律でカバーしきれない部分を自治体が補完し、地域の水環境悪化を未然に防いでいるのです。
まとめると、排水基準には(1)国の一律基準、(2)自治体の上乗せ基準(+裾下げ規制)、(3)自治体の横出し基準が存在し、それぞれ段階的・補完的に適用されます。事業者の皆様は、自社がどの基準まで遵守すべきかを把握する必要があります。特に排水先の地域によっては国の基準さえ守れば良いというわけではなく、都道府県条例で定められたより厳しい基準に適合しなければならない点に注意が必要です。「自社は小規模だから関係ない」と思われるかもしれませんが、自治体条例で横出し的に規制される場合もありますので、排水量が少ない事業所でも所轄自治体の環境担当部署に確認しておくと安心です。
業界別特定施設と排水規制
排水基準そのものは全国一律に定められていますが、業種や排水の性質によって留意すべきポイントがあります。水質汚濁防止法では、汚水を出すおそれのある設備を業種横断的に「特定施設」としていますが、その内容は実質的に各産業分野に対応しています。例えばメッキ工場で用いる電解槽や洗浄槽は重金属(シアンやクロムなど)を含む排水が出るため特定施設に該当し、厳しい有害物質基準を守らねばなりません。食品・飲料製造業では、有機物や油脂を多く含む排水が出るためBOD・CODや油分の管理が重要です。電子・半導体工場ではフッ素やホウ素など特殊な無機物質を含む排水が問題となるケースがあり、それらも有害物質として排水基準が定められています。さらに畜産業のように大量の窒素・リンを含む排水を出す分野では、環境中での富栄養化防止の観点から窒素・りんの含有量基準や、場合によっては暫定的な緩和基準が適用されることもあります。
このように業界別に排水中の汚染物質の特徴が異なるため、適用される基準値や規制の厳しさも異なる場合があります。たとえば畜産農場では、豚舎や牛舎の規模が一定以上であれば特定事業場とみなされ、通常の生活排水とは異なる高濃度の窒素・リンを含む排水として特別な管理が求められます。内陸の湖沼に排水が及ぶ地域では、畜産業等に対し窒素・りんの基準を一時的に緩和する暫定排水基準を設けつつ、徐々に技術開発を促して環境基準の達成を目指すといった措置も講じられてきました。
また自治体の条例も水域区分や業種ごとに細かな基準を設定している場合があります。東京都の環境確保条例では、水域(東京湾沿岸か多摩川水系か等)や業種・事業場の規模、新設・既設の別によって排水基準が細かく定められています。新設工場にはより厳しい基準が適用されるケースや、特定業種について独自項目の基準が設けられるケースもあります。事業者は、自社の業種・設備がどのような規制を受けるのか、国の基準だけでなく自治体の資料や業界団体のガイドラインも参考にして確認することが大切です。
なお、水質汚濁防止法の排水規制は公共用水域へ直接排出される水が対象ですが、都市部では工場排水を下水道に流す場合も多いでしょう。その場合は下水道法や各自治体の下水道条例に基づく下水への排除基準が別途存在します(例えばpHや有機物、油分について下水処理場に影響を与えない基準があります)。下水道へ放流する場合でも基本的な管理項目は似ていますが、下水道の場合は上下水道局の監督下で下水道排水基準を守る必要があります。したがって、自社の排水経路に応じて、水質汚濁防止法上の基準と下水道の排出基準の両方を確認し、適切な対応をとることが重要です。
排水基準違反のリスクと罰則
万が一、排水基準を満たさない汚水を流してしまった場合、事業者には重大なリスクと責任が生じます。まず法律上、排水基準違反は直罰の対象です。具体的には「排水口で排水基準に適合しない汚水を排出してはならない」と定められており、これに違反した場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(過失による違反でも3か月以下の禁錮または30万円以下の罰金)。まず自治体から改善命令が発せられ、従わない場合は操業の一時停止命令や罰則適用に進むのが通常の流れです。例えば都道府県知事は基準超過を確認すると改善命令を出し、それでも是正されない場合には操業停止等の行政処分を下します。改善命令を無視した場合など悪質なケースでは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といったより重い刑事罰が科される規定もあります。
罰則だけでなく、社会的信用の失墜というリスクも見逃せません。行政処分や法令違反が公表されれば、企業イメージは大きく傷つき、取引先や顧客からの信頼を失いかねません。実際に国内でも、違法な排水を繰り返して摘発・罰則を受けた事例が報道され、企業が社会的非難を浴びたケースがあります。環境コンプライアンス違反は株価や採用にも影響し、事業継続に支障をきたす恐れがあります。したがって「基準オーバーくらい大したことはない」)、基準値に接近しそうな兆候があれば直ちに処置を講じるなど、未然防止と早期是正が求められます。
まとめると、排水基準違反をすると(1)行政指導・処分(改善命令・操業停止等)、(2)刑事罰(懲役・罰金)、(3)企業イメージ悪化**という三重のリスクが発生します。こうしたリスクを回避するためにも、経営者から現場担当者まで排水規制の重要性を共有し、日常から確実な管理を行うことが肝要です。
排水基準クリアのための対策技術
厳しい排水基準を満たすためには、自社の排水特性に合わせた適切な排水処理技術を導入・運用することが不可欠です。排水処理の方法には様々な種類があり、それぞれ得意とする汚染物質やメリット・デメリットが存在します。ここでは代表的な処理技術をいくつか紹介します。
- 中和処理(pH調整):酸性またはアルカリ性の排水に中和剤(アルカリ剤や酸剤)を加え、排水基準で定められた適正なpH範囲(5.8~8.6など)に調整する基本技術です。例えば、コンクリート工場などの強アルカリ排水には酸を加えてpHを下げ、めっき工場等の酸性排水には苛性ソーダなどでpHを上げる対応をします。pHはすべての排水で重要な項目であり、中和タンクと簡易計測器を備えて自動制御する仕組みがよく利用されています。
- 凝集沈殿法(薬品沈殿法):排水に凝集剤や沈殿剤を添加し、汚濁成分を固形のフロック(おり)にまとめて沈降・除去する方法です。主にSS(浮遊物質)や重金属、一部の**有機物(COD)の除去に効果的で、幅広い汚染物質に適用可能な汎用性の高さがメリットです。装置も比較的コンパクトで導入しやすい一方、薬品スラッジ(汚泥)が多く発生する点や、処理後の汚泥の処分コストが課題となります。
- 活性汚泥法(生物処理):微生物の働きを利用して排水中の有機汚濁物質を分解させる生物学的処理法です。代表的なBOD削減技術であり、適切に維持管理すれば高濃度の有機物や窒素・りんまで除去可能です。メリットは処理効率が高くランニングコストも比較的低い点ですが、反応槽や沈殿槽など広い設置面積を要し、微生物の管理にも専門知識が必要です。食品工場や下水処理場などでは古くから使われる定番技術です。
- 膜分離活性汚泥法(MBR):活性汚泥法に膜分離技術を組み合わせた高度処理手法です。微生物処理の後段に超微細なろ過膜を設置し、固液分離を行うことで高品質な処理水を得られます。SSや細菌を完全に除去できるため、処理水を再利用する再生水システムにも適しています。また膜によって汚泥濃度を高く保てるため施設の小型化(省スペース化)が可能です。デメリットは膜が目詰まりしやすいことや、膜ユニット自体の初期コストが高価な点です。
- 活性炭吸着法:多孔質の活性炭に汚染物質を吸着させて水を浄化する方法です。残留する微量有機物質や着色・臭気成分の除去に効果的で、凝集沈殿や生物処理では取りきれないトリハロメタン前駆物質などの抑制にも用いられます。活性炭を充填した塔に排水を通水するだけと仕組みはシンプルですが、活性炭は一定量吸着すると交換・再生が必要で、そのコストがかかる点が課題です。一般に最終仕上げ処理(ポリッシング工程)として利用されます。
- 逆浸透膜(RO)処理:半透膜を用いて水中のイオンや溶解性物質までも除去する高度分離技術です。極めて純度の高い水が得られるため、上水の浄化や工場内リサイクル水の生成にも利用されています。排水処理では全般的な高度処理として位置づけられ、重金属・硝酸態窒素・微量有機物など広範囲の物質に効果があります。ただしRO膜は高価でエネルギーコストも大きく、処理過程で濃縮された廃液(濃縮水)が発生するため、その処理が新たに必要になるデメリットがあります。
以上のような技術を単独または組み合わせて、各事業場の排水特性に最適な処理システムを設計することが重要です。例えば、有機物と重金属の両方を含む複雑な排水の場合、まずpH調整と凝集沈殿で重金属とSSを除去し、その後活性汚泥や活性炭で有機物を減らす、といった段階的処理を採用します。また、処理設備を安定稼働させるためには日々の運転管理と定期メンテナンスが不可欠です。処理効率の低下を早期に察知するために水質測定データの監視を継続し、機器の故障や異常があれば迅速に対処する体制を整えましょう。適切な処理技術の導入と運用管理によって、排水基準を安定してクリアすることが可能になります。
排水基準対応のコスト最適化
排水処理は環境対策であると同時に、企業にとってコスト面の課題でもあります。しかし、適切な戦略と技術の選択によってコストは最適化が可能です。まず考えるべきは「自社で処理するか、外部委託するか」という点です。小規模事業者では、自前で設備を持たず排水そのものを産業廃棄物(液体)として収集運搬・処分業者に委託する場合があります。確かに設備投資を省けますが、排水量が多いと委託費用が経営を圧迫することもあります。実際、外部処理に年間数百万円以上を費やしている工場も珍しくなく、長期的には大きな負担です。
一方、自社で処理設備を導入すれば初期投資は必要ですが、運転コスト次第ではランニングコストを大幅に削減できます。例えば、ある建材製造工場T社では、従来すべて産廃委託していた水性塗料廃液を自社処理に切り替えた結果、年間処理コスト720万円が約250万円まで約65%削減され、設備投資の回収期間も約1.5年と試算されました。このケースでは最適な凝集剤と処理装置を組み合わせることで、廃液の月間発生量自体も95%削減(液体を脱水濃縮し固化)できたため、廃棄物処理費用と運搬コストが大幅に圧縮できたのです。処理水は全項目で排水基準をクリアしており、環境面の適合も確保しつつ経済メリットを得ています。
コスト最適化のポイントは、ムダな処理や過剰スペックを避けることです。排水量や汚染負荷に見合った適正規模の設備を選定し、薬剤も必要十分な種類・量に絞ります。例えば、汚泥処理費用が高い場合は薬剤処方を見直して汚泥発生量を抑える工夫をします。また、処理水を可能な範囲で再利用(トイレ洗浄水や冷却塔補給水への利用など)すれば、水道代や下水道料金の節減につながりトータルコスト低減に寄与します。さらに自治体や国の補助金・助成金制度も活用しましょう。中小企業向けに環境対応設備の導入補助が出ることもありますので、情報収集して申請すれば初期コストの一部を賄えます。
最後に、専門家の知見を取り入れることも重要です。排水処理のプロフェッショナル企業に相談すれば、排水サンプルの分析に基づき最適な処理プロセスを提案してくれます。例えば当社アクトでは無償の排水サンプルテストを行い、お客様の排水に最も効果的で経済的な処理方法を検証しています。こうしたサービスを利用すれば、自社で試行錯誤するより短時間でベストな解決策が見つかり、結果的にコスト削減に直結します。排水基準を確実に守りつつコスト最適化を図るには、技術面と経営面のバランスを考慮した総合的なアプローチが不可欠と言えるでしょう。
アクトの排水基準対応実績と成功事例
水処理専門企業である株式会社アクトは、これまで340社以上の様々な業種の企業に対し、排水処理ソリューションを提供してきた実績があります。アクトの強みは、お客様ごとの排水特性に合わせたオーダーメイドの処理技術を提案できる点にあります。自社開発した無機系凝集剤「水夢(すいむ)」シリーズ、アルカリ廃水中和剤「融夢(ゆうむ)」、小型凝集沈殿装置「ACT-200」を中心に、300種類以上の処理テストデータを活用して最適処方を設計します。品質の高さは国や自治体からも認められており、国土交通省・農水省の認定を受けた製品でもあります。さらには福島第一原発の放射能汚染水処理にも採用された実績があり、公共分野への納入が技術力の証明となっています。
アクトの提案するソリューションは、単に基準をクリアするだけでなくコスト削減と環境負荷低減の両立を目指したものです。例えば先述のT社(外壁パネル製造)では、水夢シリーズの専用凝集剤とACT-200装置を導入することで処理コストを65%削減し、かつ排水基準適合を達成しました。また別のケースでは、金属加工工場K社にて水溶性切削油廃液の処理で臭気問題を解消し作業環境を大幅改善するとともに、年間600万円の処理コストを半減させた事例もあります(油分を分離する凝集剤の活用)。このように「難処理廃水も固形化して産廃費用を最大70%削減」するといった成果を数多く上げています。
また、アクトでは自社工場での小ロット製造体制(1kgから対応)を整えており、必要最小限のコストで試薬を提供できるため、小規模事業者様でも導入ハードルが低いのが特徴です。
最後に、排水基準への対応は決して「排水処理担当者だけの問題」ではなく、企業全体のリスク管理・コスト管理の課題です。しかし専門家の知見と最新の技術を活用すれば、法規制をクリアすることはもちろん、コスト削減や環境価値向上というプラスの成果を得ることも可能です。株式会社アクトは貴社の排水に関するお悩みを解決し、法令遵守と経済効果の両立を実現するお手伝いをいたします。排水基準でお困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。適切な対応によって、安全・安心かつ持続可能な水環境の維持と企業発展を両立させていきましょう。

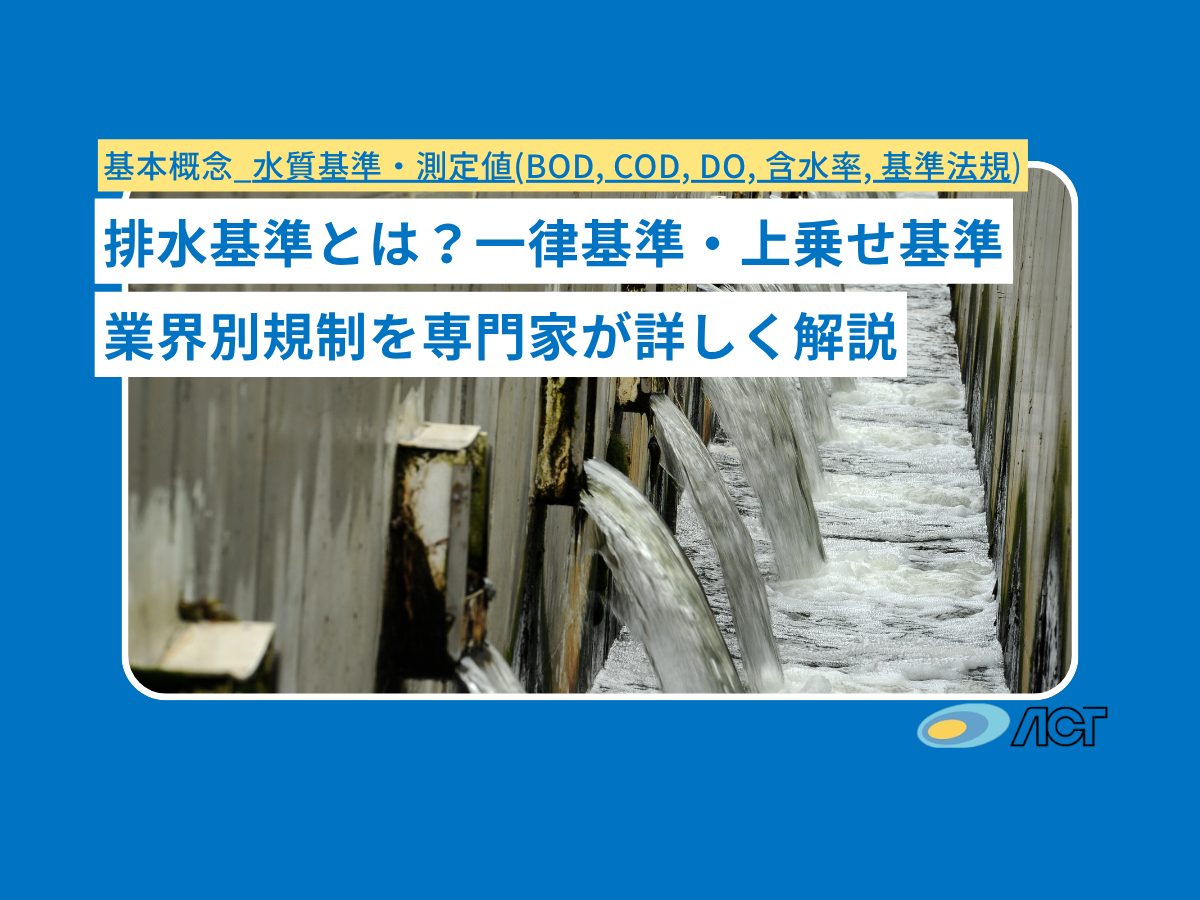





_安定稼働-300x225.jpg)
_四角-300x225.jpg)
_カーボン-300x225.jpg)
_BCP-300x225.jpg)
_DX-300x225.jpg)
_PFAS-300x225.jpg)