工場や事業所から排出される産業排水には、機械油や動植物油などの「油分」を含むケースが多く見られます。油水分離とは、この油分を排水から分離・除去する技術のことで、環境保護や設備の安定稼働のために欠かせません。油分を適切に除去しないまま排水を流せば、水質汚濁や悪臭の原因となるだけでなく、排水配管の詰まりや下水処理施設への負荷増大といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。
本記事では、油水分離の基本原理から装置の種類、業界別の最適事例、油分除去効率の向上策、さらには最新の自動化動向までを解説します。また、株式会社アクトの他社にはない凝集剤の性能によって実現した成功事例もご紹介します。工場の排水管理を任されているご担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
油水分離の基本原理|比重差・表面張力を利用した分離メカニズム
油と水は混ざり合わない(非混和)性質を持ち、これを利用するのが油水分離の基本です。比重差による分離がその代表例で、水より軽い油は時間を置くと自然に水面に浮かび上がります。一方、水より重い油(例えば一部の重油など)は沈降します。このように重力による静置分離では、密度の差によって油滴が浮上または沈降し、水と油の二相に分かれます。比重差を利用した方法はシンプルですが、大きな油滴であれば自然分離するものの、微細な油滴や乳化した油は重力だけでは分離しにくい点に注意が必要です。
油水分離には表面張力の作用も関係しています。水と油は互いに溶け込まず界面を作りますが、水に含まれる界面活性剤や洗剤成分などの影響で乳化が起きると、油滴が細かく分散して安定した混合状態(エマルション)になります。乳化状態では表面張力が低下し、油と水がなかなか分離しません。このため、破乳剤(はにゅうざい)と呼ばれる薬剤で乳化を解消し、再び油滴同士を集まりやすくしてあげることも重要です。基本原理としては、油と水の密度差と液体の界面の性質を上手に利用し、必要に応じて化学薬品で油滴を大きくまとめたり乳化を壊したりすることで、効率よく油分を取り除くことが可能になります。
油水分離装置の種類と特徴|重力分離・加圧浮上・遠心分離・膜分離の比較
油水分離を実現する装置や手法にはさまざまな種類があり、それぞれ原理や適した用途が異なります。ここでは代表的な4種類の油水分離方法について、その特徴を比較しながら解説します。
重力分離(隔槽・プレート式など)
重力分離は最も基本的な油水分離方法です。前述したように油と水の比重差を利用し、タンクや分離槽内で静置して油分が自然に浮いてくるのを待ちます。典型的な設備としては、油水分離槽(オイルセパレーター)やAPIセパレーター、また近年では傾斜板式分離装置(プレート式油水分離器)が用いられます。プレート式では、槽内部に多数の斜板を配置し、有効な分離面積を稼ぐことで小さな油滴でも捕集しやすくしています。重力分離法のメリットは構造がシンプルで維持管理が容易な点ですが、分離できる油滴の大きさに限界があり、乳化した油や微小な油粒子は十分に除去できない場合があります。そのため、重力分離槽の前後に他の処理を組み合わせて使うのが一般的です。
加圧浮上(DAF:溶存空気浮上法)
加圧浮上法(気泡浮上法とも言います)は、水中に微細な気泡を発生させ、その気泡が油滴に付着して浮力を高め、油分を水面に浮上させて除去する方法です。代表的な装置にDAF(溶存空気浮上装置)があります。DAFでは一度水を加圧タンク内で空気と接触させて溶解させ、急減圧することで直径数十マイクロメートル程度の非常に細かい気泡を大量に生成します。これらの気泡が油や固形物の粒子に付着すると、実質的な比重が下がって速やかに上昇し、浮上スカムとして表面に集められます。加圧浮上のメリットは、小さな油滴や比重差だけでは浮きにくい粒子まで効率良く回収できる点です。反面、設備としてはポンプや加圧槽などが必要になるためやや複雑で、圧縮空気の供給など運転コストがかかります。しかし、凝集剤との併用によって高い除去率を達成できるため、食品工場や下水処理場など幅広い分野で導入されています。
遠心分離(サイクロン・デカンターなど)
遠心分離は、油水混合液を高速回転させることで生じる強力な遠心力によって油と水を強制的に分離する方法です。遠心力により密度の大きい水相は外側へ、小さい油相は中心部へと移動させることで短時間で層分けを行います。装置の例として、ディスク型遠心分離機やデカンター遠心機、また簡易的な油水分離用サイクロン(油分離サイクロン)などが挙げられます。遠心分離の利点は、重力の数百倍に及ぶ加速度を利用できるため分離スピードが速く、小型の機器でも高い処理能力が得られることです。また、適切に調整すれば微細な油滴まである程度分離可能です。ただし、機械的な回転部を持つため設備費・維持費が高く、定期メンテナンスも必要になります。そのため、遠心分離は処理水量が少ない場合の高度処理や、装置占有スペースを極力小さくしたい特殊なケースで用いられることが多く、一般的な排水処理ラインでは重力分離槽や浮上分離装置の補助的な位置づけです。
膜分離(MF/UF膜ろ過など)
膜分離は、特殊なフィルタ膜を使って油分を物理的にろ過除去する方法です。精密ろ過膜(MF膜)や限外ろ過膜(UF膜)を使用することで、微小な油滴やエマルション状態の油まで捕捉できます。例えばMF膜はおおむね0.1~10µm程度の粒子を除去でき、UF膜なら0.01~0.1µm程度のもっと細かな粒子まで分離可能です。膜分離の最大の特徴は分離精度の高さで、他の方法では除去困難な乳化油もしっかり取り除ける点です。飲料水の処理や、排水を再利用する高度処理の工程など、極めてクリーンな水質が求められる場合に適しています。しかしデメリットとして、膜は使っているうちに油や汚れで目詰まり(ファウリング)を起こしやすく、定期的な洗浄や交換が必要です。また、膜モジュールや洗浄装置のコストもかかります。したがって膜分離は、最終的な磨き工程(ポリッシング)や排水再利用時の仕上げ段階として導入されることが多いです。通常は前段に凝集処理や浮上処理を行い、負荷を下げてから膜で仕上げるのが効果的です。
各手法をまとめると、重力分離は簡便だが大まかな分離に向き、加圧浮上は微細油滴まで含めた効率回収に優れ、遠心分離は高速処理が可能だがコスト高、膜分離は究極の高精度だが維持管理が大変、といった特徴があります。処理対象の排水特性や必要な水質レベル、設備予算に応じて、これらの手法を単独または組み合わせて油水分離システムを設計します。
業界別油水分離システム|機械加工・食品・石油化学工場での最適化事例
油を含む排水は発生源となる業界やプロセスによって性質が異なるため、最適な油水分離アプローチも業種ごとに変わってきます。ここでは機械加工業界、食品工場、石油化学工場の3つを例に、それぞれで効果を上げている油水分離システムの事例とポイントを紹介します。
機械加工業界の場合
自動車部品や金属部品の製造現場では、切削油や潤滑油、あるいは部品洗浄用の洗浄液に含まれる油分が排水に混入します。機械加工業の排水は油分だけでなく微細な金属粉なども含むことが多く、そのままでは水質汚濁の原因となるため確実な処理が必要です。典型的な対策として、加工機械のクーラントタンクや洗浄槽からあふれた油をまずオイルスキマー(浮上油回収装置)で回収します。オイルスキマーはベルトやディスクで液面に浮いた油膜を掬い取る装置で、一次的に浮上油をできるだけ取り除いておくことで後工程の負荷を軽減できます。
その後の本格的な処理では、凝集剤を添加して油分と懸濁物質の凝集処理を行い、浮上分離槽でフロックと一緒に油分を分離除去する方法がよく用いられます。例えば、ある金属加工工場では従来市販の小型オイルスキマーを複数台使っていたものの十分に油を除去しきれず、凝集・浮上処理設備への負荷が高い課題がありました。そこで高効率タイプのオイルスキマーと適切な凝集剤処理を組み合わせたシステムに更新した結果、浮上油回収率が飛躍的に向上し、後段の負荷が低減して放流水質が安定した例があります。機械加工業界ではこのように、前処理での油回収+凝集浮上処理による多段階の油水分離システムが効果的です。
食品工場の場合
食品産業では動物性・植物性の油脂やグリースが排水中に含まれる代表例です。食肉加工場や惣菜工場、乳製品工場などでは、洗浄工程で流れた脂肪分が配管内で固まってしまい、配管閉塞や悪臭の原因となる問題がしばしば発生します。その対策として多くの食品関連施設では、排水経路にグリーストラップ(油脂分離槽)を設置し、温水や洗剤で乳化しがちな油脂を排水本管に流す前に捕集しています。グリーストラップでは比重差により油脂を浮かせて捕まえますが、動物油脂は冷えると固体化しやすく、長時間放置すると凝固した塊が沈んだりして性能が低下します。そこで、適切な温度管理や加温によって油脂が固まらないようにしたり、定期的な引き抜き清掃が重要となります。
さらに高度な事例では、工場から排水処理場へ向かう配管に特殊な処置を施し、油脂が付着・固着しにくい工夫をしているところもあります。例えば配管にコイルを巻いて弱い電磁波を与えることで油脂分子の凝集を妨げ、固まりにくくする試みなども行われています。また、排水貯留槽の表面に浮いた油脂分をスカムスキマー(表面撹拌除去装置)で吸引除去し、その回収油をコンパクトな油水分離機で脱水処理して廃油として分離するシステムもあります。ある食肉加工工場では、このような多段階の対策によって配管内に油脂がほとんど蓄積しなくなり、外部業者による高圧洗浄清掃のコストがゼロになった例も報告されています。また放流水中の油分濃度が大幅に低減し、BOD値も改善したことで排水処理施設の負荷が軽減されました。食品工場ではグリーストラップ+凝集浮上処理+必要に応じて高度処理という形で、油脂対策と水質向上の両面からアプローチするのが効果的です。
石油化学工場の場合
石油精製プラントや化学工場では、原油や有機溶剤由来の油分を多量に含む廃水が発生します。これらの工場では排水処理設備も大規模で、法規制による排出基準も厳しいため、段階的かつ綿密な油水分離システムが構築されています。典型的には、まずAPI油水分離槽や傾斜板式分離槽による重力分離で大量の遊離油を回収します。その後、加圧浮上装置(DAF)を用いて微細な油滴や乳化油を除去し、必要に応じて活性炭吸着や膜ろ過といった仕上げ処理を追加することで、排水中の油分濃度を厳格な基準値以下にまで低減させます。
石油化学系の廃水は乳化剤や添加剤が混入している場合も多く、化学的に安定なエマルションが形成されていることがあります。そのため、処理プロセス内で破乳剤(乳化破壊剤)の添加やpH調整・加温などを行って乳化状態を解消し、油滴の凝集を促す工夫が重要になります。実際に、とある化学工場では、常温では分離しにくかった油分を前処理で温度を上げ粘度を下げた上で凝集剤と破乳剤を投入し、その後のDAF処理で油分除去率99%以上を達成した例があります。最終的な放流水中の油分は数ppm(数mg/L)以下となり、環境基準を十分にクリアしました。石油化学工場のような大規模プラントでは、重力→浮上→仕上げ処理と段階を追ったシステムに加え、原水の性状に応じた薬品注入や条件調節によって、安定した油水分離を実現しています。
油分除去効率の向上|凝集剤・破乳剤の活用と条件最適化
油水分離の効率を高めるためには、物理的な装置の工夫だけでなく化学的な助剤の活用や、処理条件の細かな最適化が不可欠です。ここでは、油分除去率を向上させるための代表的なポイントを解説します。
- 高性能な凝集剤の使用: 微細な油滴が散在する排水には、凝集剤(フロック剤)を加えることで小さな油粒子同士をくっつけて大きな固まり(フロック)にします。フロックに取り込まれた油は浮上分離や沈降分離で回収しやすくなるため、凝集剤の選定は油水分離効率を左右する重要事項です。一般的な凝集剤には無機系のPAC(ポリ塩化アルミニウム)や硫酸鉄など、および有機高分子系のポリアクリルアミドなどがあります。それぞれ特性が異なるため、排水中の油の種類や他成分に応じて最適な種類と投与量を選ぶ必要があります。例えば、乳化油を含む排水には無機系の凝集剤が有効な場合が多く、油滴表面の電荷を中和して凝集させることで迅速に油水分離が進みます。
- 破乳剤の活用: 油と水が乳化して分離しにくい場合、破乳剤(デムルシファイヤー)の添加が効果的です。破乳剤は乳化を安定させている界面膜を破壊し、油滴同士が再結合しやすい状態にします。具体例として、切削油などに含まれる界面活性剤によってできた乳化排水に破乳剤を加えると、白濁していた液体がしだいに透明な水層と浮上油層に分かれていく、といった現象が見られます。破乳剤にも様々なタイプがありますが、油の性質に合ったものを選定しないと十分な効果が得られません。適切な破乳剤を使えば、従来は分離困難だった安定エマルションを短時間で分離でき、凝集剤や浮上装置との併用でトータルの処理効率が飛躍的に高まります。
- 条件設定の最適化(pH・温度・撹拌など): 薬品を用いた処理では、pHや温度、撹拌方法といった処理条件も結果に大きく影響します。たとえば無機系凝集剤はpHが中性付近で最も効果を発揮するものが多く、排水が酸性・アルカリ性に偏っている場合は事前に中和調整が必要です。また、動植物油が主成分の排水では温度を上げて油脂を溶解・液状にしてあげると凝集・分離が進みやすくなります。さらに、薬品を加えた際の撹拌の強さと時間も重要です。最初は全体に薬剤を行き渡らせるため速い撹拌を行い、その後フロック生成の段階ではゆっくりと混ぜて粒子を育てる、といった手順を踏むことで理想的な凝集が起こります。このように、薬剤選定+条件最適化のセットで油水分離の性能は大きく向上します。現場では事前にビーカー試験(ジャーテスト)を行って最適条件を見極め、本番設備にフィードバックすることが大切です。
- 装置・システムの適切運転と保守: 油水分離装置そのものの運転条件を適切に維持することも基本ですが重要です。たとえば浮上分離槽では、滞留時間を十分に確保し過負荷運転を避ける、スクレーパーやオイルスキマーで浮上油を定期除去する、凝集沈殿槽ではスラッジ抜きを怠らない、といった日常管理が性能維持に直結します。せっかく良い装置や薬剤を導入しても、運転管理が不十分だと想定された性能を発揮できません。定期点検と清掃・消耗品交換を計画的に実施し、常にベストコンディションで稼働させることが高い油分除去率を長く維持するポイントです。
以上のように、油水分離の効率化にはハード(装置)とソフト(薬剤・条件)両面からのアプローチが欠かせません。特に凝集剤や破乳剤については各メーカーから特徴の異なる製品が出ており、専門家の助言を仰ぎながら自社排水に最も適したものを選ぶことで、驚くほど処理効果が向上するケースもあります。
油水分離システムの自動化|油分濃度監視・自動制御システム
近年のIoT技術やセンサー技術の発展により、排水処理プロセスの自動化が進んでいます。油水分離の分野でも、センサーを活用したリアルタイム監視や、自動制御による最適運転が実現しつつあります。
油分濃度の連続モニタリング: 従来、排水中の油分濃度(油分値)は分析室での抽出測定や、人間の目視(油膜の有無)によって確認することが多く、リアルタイム性に欠けていました。現在では、排水中に含まれる油分をオンラインで検知する油分計や油濃度センサーが普及し始めています。たとえば赤外線を利用した検知器やUV蛍光を利用する計測器によって、ppmレベルの油分濃度を連続測定することが可能です。これらを排水処理システムに組み込めば、処理後の水質を24時間監視し、基準値を超える前にアラームを出したり、自動的に処理工程を調整したりできます。
薬注やポンプの自動制御: 油水分離システム内の各種装置に自動制御を取り入れることで、人手に頼らず安定運転が可能になります。具体例として、凝集剤や薬品の投加ポンプを油分濃度や流量に応じて自動調節するシステムがあります。排水の性状は工場の稼働状況によって日々変動することがありますが、自動制御ならばリアルタイムのデータに基づき投薬量を増減できるため、常に適切な処理条件をキープできます。また、浮上分離槽や油分離槽においても、油層の厚みをセンサーで検知してスキマーを自動起動し、一定量の油が溜まったら自動回収する仕組みなどが導入されています。これによって、担当者が逐一現場を巡回しなくても装置が自律的に動作し、トラブル時のみ通知を受けるといった省力運転が実現します。
データ記録と遠隔監視: 自動化システムは同時に運転データの記録や遠隔地からの監視を容易にします。油水分離プロセスの各種センサー値(油分濃度、pH、流量、ポンプ稼働状況など)をPLCやコンピュータに蓄積しておけば、処理性能の傾向把握やトラブル発生時の原因追跡に役立ちます。さらにインターネットを通じて専門業者が遠隔から監視・サポートするサービスも増えており、異常値検出時にはメールやアラームで知らせて迅速対応することも可能です。例えば株式会社アクトでも、導入先の要望に応じてIoT対応の排水処理装置をカスタマイズ提供し、遠隔で処理状況を確認できるような仕組みを構築するケースがあります。自動化と遠隔監視を組み合わせることで、人手不足の解消、処理の安定化、緊急時の迅速な対応が実現し、結果的に環境コンプライアンスの強化と運用コストの削減につながっています。
アクトの油水分離改善実績|除去効率向上と運用コスト削減の成功事例
株式会社アクトでは、今まで多くの企業の排水課題を解決してきました。他社製品では処理が難しかった油含み排水にも結果を出している、その成功事例の一部をご紹介します。
- 事例① 金属加工工場での油分処理効率向上: ある自動車部品メーカーでは、水溶性切削油を含む排水の処理コストがかさみ、しかも放流水に微量の油が残留してしまうことに悩んでいました。アクトの技術者はまず排水サンプルをテストし、アクト独自の無機凝集剤「水夢(すいむ)」シリーズの中から当該排水にマッチする配合を選定しました。その結果、難乳化状態だった油が素早く凝集・分離され、油分除去率99%以上を達成。処理後の水は下水放流基準を悠々とクリアし、残留油によるトラブルも解消しました。また液体廃油として処理していたものの多くを固形化できたため産廃処理コストが約50%削減し、投資回収も短期間で達成できました。
- 事例② 食品工場でのグリース対策と省力化: ある食品加工工場では、揚げ物製造ラインの洗浄排水に含まれる植物油が排水配管に付着し、頻繁な詰まりと悪臭に困っていました。アクトは凝集剤「水夢」と、食品工場向けに安全性の高い消泡剤・破乳剤を組み合わせることで、油脂が確実に浮上分離されるプロセスを構築しました。この対策により、排水管閉塞の問題は解消し、年間数百万円に及んでいた外部清掃業者への依頼コストもゼロになりました。同時に放流水中の油分濃度は大幅に低下し、水質悪化による臭気も発生しなくなったため、工場内外の環境が改善しています。
- 事例③ 化学工場での難処理廃水への挑戦: オイルエマルション廃液を多量に出す化学メーカーでは、従来使っていた高分子凝集剤では油分が十分に固まらず、処理後も水に濁りが残るという課題がありました。そこでアクトのゼオライト系無機凝集剤「水夢」をベースにした処理を提案しました。無機系の凝集剤は油滴の電荷を中和して微細な油も取り込みやすく、同時に重金属など他の不純物も一緒に凝集できるメリットがあります。実際のテストでは、これまで分離できなかった微細油滴が次々とフロック化し、短時間で上澄みの水が澄明になることを確認しました。また、お客様の要望に合わせて凝集剤の配合を調整し、処理後の汚泥性状(含水率)も圧縮しやすいよう最適化しました。その結果、新システム導入後は処理水の透明度が飛躍的に向上し、排水基準の油分項目を安定的にクリア。固形化したスラッジはフィルタプレスで脱水・減容できるため廃棄コストも削減し、トータルのランニングコストが約60%削減する見通しとなりました。これにより難処理といわれた含油廃水の問題が解決し、環境規制順守と経費削減の両立を実現しています。
以上のように、株式会社アクトでは高性能な凝集剤の性能を最大限に引き出し、かつお客様それぞれの廃液に寄り添った対応を行うことで、油水分離に関する様々な課題を解決してきました。油分を含む排水処理でお困りの際は、ぜひアクトにご相談ください。環境保全とコスト削減の両面から最適なソリューションをご提供いたします。

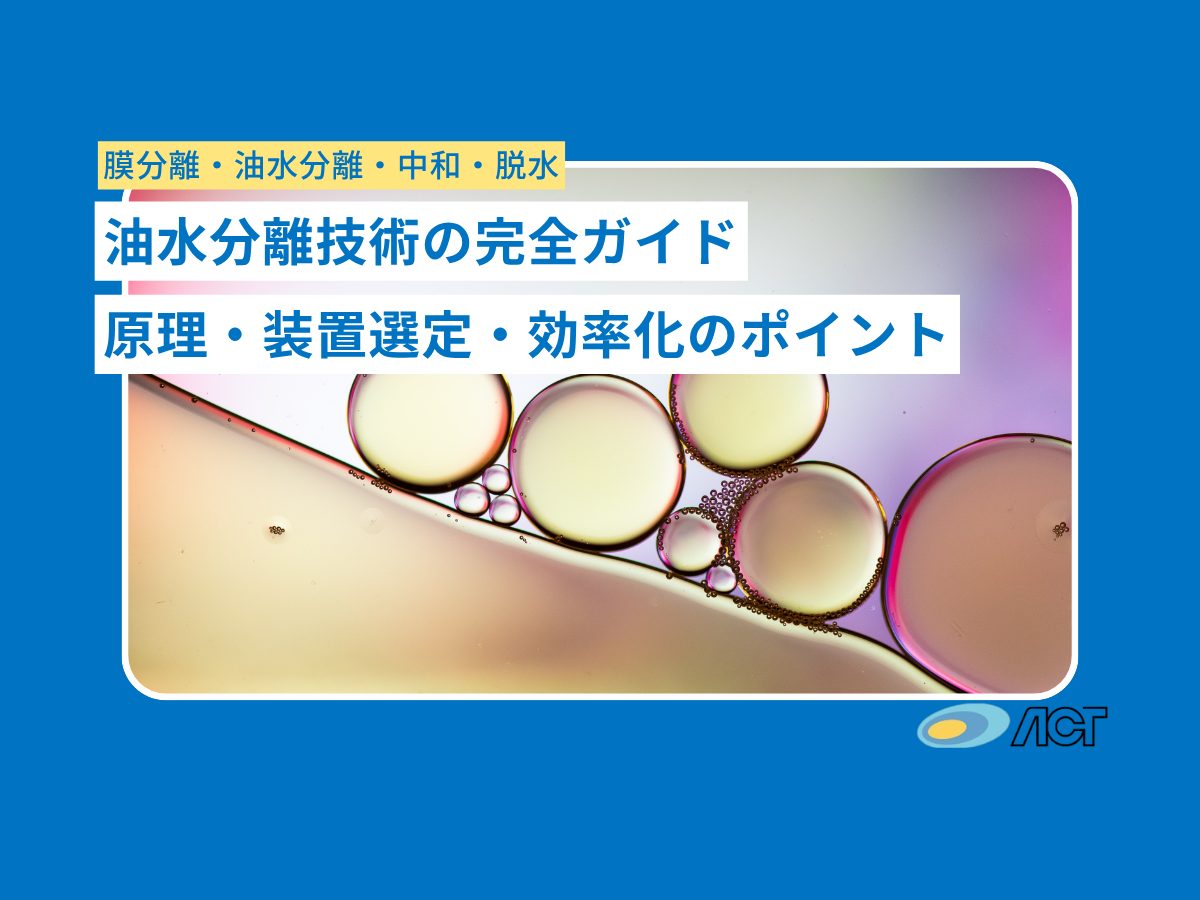
-2-300x225.jpg)

-5-300x225.jpg)
-4-300x225.jpg)
-3-300x225.jpg)
-2-300x225.jpg)
-1-300x225.jpg)
-300x225.jpg)